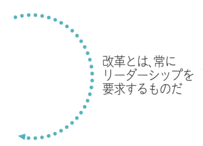適応型の変革が成長をもたらす
――改善目標は適切なものでなければ意味がないと思いますが、どのようにしてその妥当性を確認すればよいでしょうか。
いくつかの方法があると思います。個人的な目標、たとえば「痩せたい」「時間を有効に使いたい」といったものであれば、本人の意志の問題です。よほど病的なものでない限り、周囲がそうした目標に対してとやかく言うことはないでしょう。つまり、自分でこうしたいと思うからこそ立てる改善目標であれば、妥当性はそれほど重要ではありません。
しかし、仕事の目標であれば話は別です。改善目標が会社のためにならなければ意味はありません。ですから、まずは目標が正しく設定できているか、評価を受けることが重要です。あるいはフィードバックを受けることも有効です。周囲の人々、つまり上司や同僚、部下といった人々から、その目標が適切かどうか判断してもらうのがいいでしょう。そうしたプロセスを経ることで、設定する改善目標をよりよいものに磨き上げるのです。
――改善目標は内発的なものであるべきでしょうか。
内発的な要素と外発的な要素とが組み合わさっているのが理想と言えます。ほかの人がやっているからではなく、「私がこうしたい」という内発的なものは、きわめて重要です。しかし、仕事に関しては自分の思いと会社側の期待がうまく連動することが、より重要となります。外からの期待に応える変革に成功すれば、その人が会社のなかでさらにステップアップしていくことに繋がるからです。
――自分の思いと会社側の期待が合致しないケースもあると思います。あるいは会社側の期待が過大なプレッシャーになることもあるのではないでしょうか。
たとえば自分がチーム・リーダーとして、いい仕事をしているとしましょう。部下に素早く的確な指示を下し、細かいところまで気づくことのできるリーダーで、それが自分の強みだと考えています。しかし、会社からは、もっと周囲と協調的に動きなさいと言われ、改善点を示唆されたとします。その改善目標を達成できれば、別のチームのリーダーにしてあげると言われたならば、自分の強みを変えなさい、と言われたということです。
先導型のリーダーから協調型に変わるよう促されたわけですが、そこにジレンマが生じるわけですね。この場合、協調的で、人に仕事を任せられるようなリーダーになりたいと心底思えるかどうかがカギとなります。そうはなりたくないと思うのであれば、会社を辞めるか別の仕事を探した方がいいでしょう。しかし、そういうリーダーになりたいと思うのであれば、改善目標に向かって取り組む必要があります。もちろん、すぐになれるわけではありませんし、自分はそうなれるのかという不安を持つこともあるでしょう。
この不安こそが、私たちのアプローチにおける中核的なポイントです。改善目標を掲げ、それに対して、本当にこれで大丈夫だろうか、うまくいくのだろうか、と不安を感じる人は多くいます。私たちが提案する免疫マップは、そうした人たちの支援のためにつくられたものです。「新しいプログラミング言語を覚えたい」といったような技術的な問題や、達成可能と思える目標に対しては、免疫マップは不要です。私たちが支援するのは適応型の変革です。人は無意識に変化を恐れ、避けようとするものです。だからこそこうした適応型の変革は難しく、免疫マップの支援ツールのようなものが求められるのです。人間として成長するために不安はつきものです。現状維持でよしとするか、それを乗り越えて成長を目指すのか。成長のためには、今あるところから、一歩飛び出したところに向かわなければなりません。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)