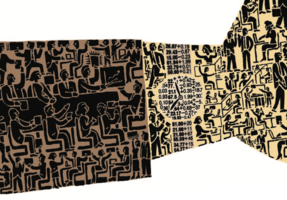-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
顧客の目を価格からそらす価格戦略
ある有名な消費財メーカーで、自社製品のことを「コモディティ」と呼んだりする役員はおそらく一人もいないだろう。
彼ら彼女らは、競争によって何が生じるのか、また自社製品と競合製品は何が違っているのかについて、むろん承知している。どのような特長があって、その価値がいかなるものか説明できるし、その強みが失われないよう、どれほどイノベーションに投資してきたかについても語れるだろう。
問題は、これらのことがどうも顧客に伝わっていないことである。店の棚にはさまざまな製品が並んでおり、顧客は「買うかどうかは価格次第」といった様子である。実際、顧客たちはこの消費財メーカーの製品をコモディティと見なしている。この問題は何ともしがたいだけでなく、同社に限ったことでもない。
いまや多くの、いやほとんどの市場が成熟化し、まさしく激しい価格競争が繰り広げられている。顧客を逃がすまいと安売りを続ければ、効率は上がるかもしれないが、それ以上にブランド・エクイティが損なわれ、利益率はだんだん低下していく。
さらに悪いことに、これらの市場の顧客は期待や関心に乏しい。つまり、価格にはこだわるが、よほどのイノベーションでない限り、マーケティング・コミュニケーションなどには見向きもしない(囲み「顧客もコモディティ化している」を参照)。
顧客もコモディティ化している
製品カテゴリーのコモディティ化が進行しているとは、どのような場合だろう。経営者や経営研究家の大半が、目に見える特徴や性能において競合製品と大差がなくなった時であると説明するだろう。
しかし我々の調査によると、物理的なコモディティ化のみならず、心理的なコモディティ化もある。実際、コモディティ化した市場では、買い手は次のような反応を示す。
・懐疑的な態度
・惰性的な行動
・最小限の期待
・製品の差別化には無関心で、短時間で簡単な取引の選好
したがって、コモディティ化から逃れるには、製品をどうするかではなく、「顧客をどうするか」がカギを握る。つまり、いまや何事にも無関心になっている買い手との関係を再構築することを考える必要がある。
このようにコモディティ化した顧客が価格で購買を判断しているのは、実はどの選択肢でも問題なく、ちょっとした違いなどいちいち調べるまでもないと考えているからである。いまや、顧客たちは「どれが自分にいちばんふさわしいのか」と自問することをやめてしまった。
この状況を変えるのは難しい。斬新なイノベーションにも目をくれず、考えに考え抜いたマーケティング・メッセージも響かない。消費者をハッとさせない限り、この状況は続いていく。
その一番の方法は、消費者が何より注目しているもの、すなわち製品やサービスの価格に焦点を当て、予想外の、あるいは型破りなプライシングを試みることである。
とはいえ、ショック療法によって、品質や顧客にとっての個人的な重要性など、製品やサービスの価値についてあらためて考えさせることは可能である。満足のいく判断を下せることを顧客にわからせるには、逆説的ではあるが、最後の手段に訴えればよい。そう、価格である。