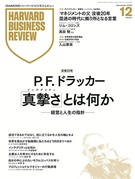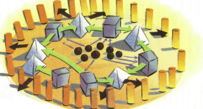なぜ巨人たちはいまなお探究を続けているのか
コトラーは、これからのマーケティングにとってビッグデータの活用が欠かせないこと、そして今後はマーケティング・オートメーションなどをいかに駆使していくかを主張しました。アーカーは、今後はブランド間の競争ではなく、新しいカテゴリー創造の競争になると、次なる競争の次元を提示します。シュルツは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのデジタルメディアを含めた、さらに統合されたマーケティング・コミュニケーションの可能性を力説します。
80歳にも迫る論者が、SNSやビッグデータの最新事例を語る。年齢を重ねるごとに、新しいことを覚えるのが億劫になるのが人の常ですが、彼らにこの常識は通用しないようです。
このように、3人の関心は過去の業績ではなく、いまの動向にあるのです。ここに、いわゆる「上がり感」はまったくありません。巨匠たちからオーラを感じたのは、過去に積み上げた業績ではなく、いまなお探究を続ける様子を目の当りにしたからでしょう。
ちょうどデービッド・アーカーの新しい著書『ブランド論』が弊社から発売になりました。内容はブランド・マネジメントの全体像を凝縮させてコンパクトにまとめたものです。アーカーの著書と言えば、大著で、多くの事例と細部にわたる理論的整合性にこだわった内容ですが、エッセンスを凝縮した本書は、アーカーにとっても新しい試みです。
この本で驚いたことは、世界中の企業の事例とともに、日本企業の新しい事例も数々紹介されていることです。ユニクロ、無印良品、セブン‐イレブンなといったグローバル企業はもちろん、ヘルスメーターを製造するタニタが健康関連のレシピ本をつくり、タニタ食堂までオープンさせた事例が紹介されています。
「サミット」の合間にアーカーにインタビューさせてもらう機会がありました(詳細は後日、掲載します)。そこで、「どうやって新しい事例を集めているのか」と素朴な疑問を投げかけてみると、彼は、「成功している企業を知ると、その理由を知りたくなる。そこで自分で情報を集め分析し、自分の理論に当てはまるかを分析する」と答えてくれました。もし、成功の理由をこれまで構築した理論で説明できなければ、持論に固執することはなく、新しい理論を生み出すのでしょう。アーカーのブランド論を深めたいという好奇心は、いまなお衰えていないようです。
過去の圧倒的な業績は、それだけで人を納得させる力があります。しかし、いまなお探究している姿をまざまざと見せられると、それ以上の説得力があるものです。「圧巻」とはこういう時に使う言葉なのでしょう。(編集長・岩佐文夫)