-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「なぜこのような不合理な選択を行うのだろうか」と疑問を抱く判断が、組織内で下されることは意外と多い。なぜ適切な判断を迅速に下すことは難しいのか。組織が囚われがちな「埋没コスト」と、それに囚われないための方策を考える。
組織が不合理な選択を行う理由
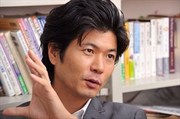
組織をはたからみていて「なぜあんな不合理な失敗をするのだろう」と不思議に思ったことはないだろうか。多くの人が「臨機応変は大事だ」というが、実際の組織は大きくなるほど「臨機応変」にほど遠い「前例不変」に陥ってしまうことは珍しくない。なぜ、組織は時間経過にともない機動性を失うのか。保守的になり新しいことにチャレンジできなくなるのか。なぜ優秀な人が集まっている組織が「あれじゃダメだと考えたらわかりそうなものなのに」といった失敗をしてしまうのだろうか。
「埋没コスト」という概念は、このなぞを解く手がかりになる。「埋没コスト」とは、これまでに積み重ねてきた実績や信頼、費やした時間や資金といった回収不可能なコストのことである。したがって、基本的に時間経過にともない埋没コストは増大していくことになる。
この観点からみると、戦争をやめられなかったのも、原発を止められないのも、方針転換することで、これまでの費やした多くのコストが回収不能になるためだとわかる。そうであれば、ほんのわずかな可能性であっても好転する(悪化しない)ことに賭けたいという心理が働き、外部からみれば不合理ともみえる行動を続けてしまうのだ。ギャンブルで損切りできないのも、これまで費やしたお金が回収不可能な「埋没コスト」になることを怖れるため起こるものであり、これと同じ心理が組織運営においても起こるのである。
「埋没コスト」自体は、ある程度広く知られているものであり、新しいものではない。しかし、この「埋没コスト」と前回紹介した「方法の原理」を組み合わせると、組織の不合理に関する洞察を深めていくことができる。方法の原理とは、次のようなものであった。方法とは「特定の状況において、何らかの目的を達成するための手段」である。つまり、方法の有効性とは、⑴状況と⑵目的によって変化するのである。
この観点からみれば、ワンマン社長が「おれはこれで成功してきたのだ!」と部下の進言に耳を傾けず会社を潰してしまうという現象は、状況が変わったにもかかわらず過去の成功方法に囚われることによって起こることがわかる。これは第三者からすると、不合理極まりないようだが、当人にはそこに囚われる十分な理由があるものなのだ。まずもって、これまで成功してきたという揺るがぬ事実がある。しかし、これまで成功してきたことは、これからの成功を保証するものではない。状況によって正しい方法は変わるためだ。さらに厄介なのは、その方法が有効なものであればあるほど、その人の中でその方法は絶対的なものとなってしまうのである(方法の絶対化)。また、方法自体がその人のアイデンティティと一体化している場合には、それを変更することはそれまでの人生を否定すること、つまり埋没コストになってしまう。そのため、新たな方法を採用すべきという意見に耳を傾けることができなくなるのだ。




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









