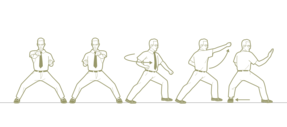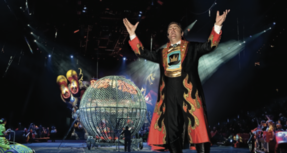-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
金融工学の権威に聞く
世界金融危機とデリバティブの関係
金融危機やリスク・マネジメントについて議論する際、デリバティブ(金融派生商品)の役割を避けては通れない。ハーバード・ビジネススクール教授のロバート C. マートンこそ、この話題を語るのにふさわしい。
彼は、現代リスク・マネジメントの枠組みをつくった人物であり、元シカゴ大学教授のフィッシャー S. ブラック(1995年没)とスタンフォード大学名誉教授のマイロン S. ショールズが開発した「ブラック・ショールズ・モデル」を数学的に証明した功績が認められ、97年、彼らと一緒にノーベル経済学賞を受賞している。
このブラック・ショールズ・モデルが73年に発表されて以来、デリバティブ市場は爆発的に拡大し、既存契約の総取引残高はいまなお500兆ドルを超えるという。
HBR誌シニア・エディターのデイビッド・チャンピオンがマートンに、今回の世界金融危機とデリバティブの関係について聞く。
デリバティブが今回の金融危機の張本人ではない
HBR(以下色文字):金融イノベーション、とりわけデリバティブが今回の世界金融危機を招いた原因であると考える人が少なくありません。どのように思われますか。
マートン(以下略):まったく見当外れです。デリバティブはいまや金融市場にすっかり浸透しており、それゆえ金融危機の影響から逃れられません。
そもそも、ツールそのものが危機を招くことなどありません。デリバティブは、本来の機能としてはリスクを低減したり、またさらに発展して、メリットを犠牲にすることなくリスクを増大したりするための一ツールにすぎません。
とはいえ、一般的にいわれているように、イノベーションというものは、その性質上、危機の可能性と切っても切れない関係にあるのも事実です。