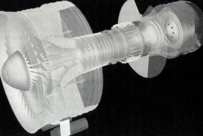システム思考を理解する、体を使ったゲーム
枝廣:なるほど。ではちょっと体を使ったゲームをやって、皆さんに篠田さんの原体験を追体験していただきましょうか。
(7人が直線でつながっている場合と、システムとして円でつながっている場合の現象の違いを体験。直線でつながっているときは一つの現象が端の人まで伝わるとそこで終わりだが、円の場合はいつまでもその現象が継続することを理解する)
篠田:ああ、なるほどねぇ。よくわかりました。事業も結果的にシステムになっていることが多いんですね。
枝廣:そうなんです。そこに関わっている人の意識にかかわらず、システム自体が仕事をしてくれる場合が多いんです。システム思考を身につけると、それを意識してより効果的につくり出したり、システムを邪魔する要素を弱めたりすることができます。
篠田:本を読んでわからないと思ってしまったのは、自分の周りの事象で考えられなかったからかもしれません。本のなかで紹介されている事例はそれぞれ納得できるんですが、自力では自分を取り巻く事象には結び付けられない。
当社の主力商品は『ほぼ日手帳』です。発売を始めて14年目で、2014年版は50万部売れました。私たちとしてはもっと伸ばしたいんですが、当然、未来永劫伸び続けるわけはない。どこまで伸びてくれるかをシステム的に考えるために、どんな要素を選んでつなげていけばいいかがわからないんです。
ほぼ日手帳の売上げを伸ばす施策を、
システム思考で考えるとどうなるか
枝廣:システム思考はループ図を描いて整理して考えることが特徴です。じゃ、ほぼ日手帳を増やすためのループ図を描いてみましょうか。

ホワイトボードにループ図を描く
ユーザーの数はストックですよね。ストックは直接変えることができませんから、フローを変えることになります。ある期間の新規のお客さんはインフローで、出て行くお客さんがアウトフロー。手帳の販売数を増やしたいのなら、新規顧客に影響を与える要素と、やめる人の要素を考えていくことになります。
篠田:新規が何で増えるかは——、まず存在を知りますよね、あるいは知ったことで自分が使うイメージが湧くということもあるでしょう。きっかけも、たまたま店頭で見た、お友達が使っているのを見た、メディアで見たとか様々です。
枝廣:たまたまというなかにも、ほぼ日手帳を知っていてたまたま店頭で見た人もいれば、何の予備知識もなく本当にたまたま買った人もいるでしょう。たとえばお友達が使っているから買ったという人がどのくらいいるのか、それを強めるにはどうしたらいいか。またユーザー側の要素として、どういうユーザーが口コミで伝える力が強いのか、あるいは人に影響されやすい潜在顧客はどんなタイプか、といった要素を考えていくことになります。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)