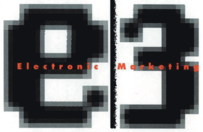-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
IoTによって企業は顧客情報をさらにきめ細かく収集できることになる。そして個々の顧客のニーズに即したコミュニケーションが可能になる。その一方、企業にとって不利な顧客の情報も取得できることになり、それが企業の新たなジレンマを生む。
IoTで顧客の生活が逐一把握できるようになる
ネット社会によって、企業が取れる顧客データは、「購買データ」から「行動データ」へ、そして「使用データ」へとその範囲が拡大しています。
購買データの威力を見せつけたのが、コンビニエンスストアのPOSシステムでした。販売予測の精度が大幅に上がり、キメの細かい品揃えを実現しました。また、小売店では店舗に設置したカメラなどから、消費者が購買にいたった行動データまで取得できるようになり、何が買われたかだけでなく、買われなかった理由も解明が進んだことで商品開発に活かされるようになりました。
購買データや行動データとともに、特にネット小売りなどでは一人ひとりの顧客に紐づいたデータまで取得できるようになりました。アマゾンは各人の購買データをもとに「リコメンド・メール」を送ります。一人ひとりの正確な購買データからその人の嗜好が理解できるようになり、その結果、効果的なマーケティングコミュニケーションが可能となりました。
企業が顧客毎の詳細な情報を手に入れることによって、顧客一人ひとりのニーズを把握できるようになる。「顧客のために」を標榜する企業にとっては、限りなくビジネスチャンスが広がるツールが揃ったわけです。
とりわけIoTはこの流れを加速します。すなわちモノがインターネットにつながる世界では、製品を通して顧客の生活データが詳細に取れるようになります。冷蔵庫がインターネットにつながり、その中にある食材のデータをすべて集積できれば、その家庭で毎日どのような食材が消費されているかわかります。牛乳や玉子が消費される頻度、さらにはその消費具合から、食べた料理の種類まで類推することができるでしょう。書籍にICチップが組み込まれインターネットに接続されれば、読者がその本をいつどこまで読んだかが正確にわかることになります。
こうした詳細な使用データが取れることから、製品の販売という、所有権の移転による課金から、製品やサービスの使用に応じた課金という新たなビジネスモデルも生まれています。その代表がカーシェアリングです。ユーザーがクルマを購入するのではなく、使用した時間に応じてお金を支払うモデルです。
この使用に応じた料金モデルは、従来の会費制ビジネスに新たな可能性と悩ましい現象をもたらします。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)