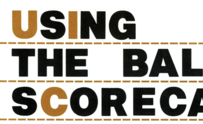ここで重要なのは、邪悪な特性による個人的成功が、集団の犠牲によって成り立つということだ。
邪悪な3大特性には確かに、適応力を高める効果がある(だからこそ悪しき輩の成功につながる)。しかしその成功には代償が伴い、代償を払うのは組織である。邪悪な特性には、進化論で言う「ただ乗り」の要素が見られる。そして環境が(政治的な意味で)汚れ堕落していけばいくほど、この種の寄生的な人格は繁栄する。
意外ではないが、邪悪な3大特性と職場でのいじめの相関を示す研究は数多い(英語論文)。また、あるメタ分析による研究では、邪悪な特性とマイナスの職務行動(窃盗、常習的欠勤、離職、破壊行為など)との間に強い関連が示された(英語論文)。この優れた研究は、1951年から2011年までに発表された邪悪な3大特性に関するすべての科学論文を分析した。その結果、マキャベリズム、ナルシシズム、サイコパシーはいずれも、マイナスの職務行動と関連し、組織市民行動(組織への自発的で無償の貢献行動)の欠如ともつながりが見られた。さらにマキャベリズムとサイコパシーは、「実際の職務パフォーマンス」と負の相関を示した(「キャリア上の成功」ではなく)。
また別の研究によれば、架空投資詐欺、インターネット詐欺、横領、インサイダー取引、汚職、不正行為は、すべて邪悪な3大特性と関連している。
しかし、よく言われるように「何事もほどほどがよい」というのも事実だ。ある研究は、(軽度ではなく)中程度のマキャベリズムが、最も高度の組織市民行動につながることを示している(英語論文)。その理由はおそらく、マキャベル的な人が政治力や人脈づくり、上司への対応に長けているからだろう。
軍のリーダー候補(士官候補生)を調べた別の研究では、特に優秀なリーダーは、ナルシシズムのポジティブな面を示しながら、悪しき面を抑えていたという(英語論文)。自負心と自己肯定感は高いが、人心操作と印象操作(自分を実際より大きく見せる)の傾向は低かった。
こうして見てくると、邪悪な特性とは「強みを発揮しすぎた結果」だと思えなくもない。適応力と短期的な成功には貢献するが、長期的には問題をもたらすのだ。特に、本人に自覚がない場合は厄介だ。
つまり邪悪な特性とは、人間の「有益にも有害にもなる人格特性」を表している。確かにそれはキャリア上の武器になることもあるが、それによる個人の成功が大きいほど、チームの被害も大きくなる。
チームや組織でライバルに勝つことが最大の目的であるのなら、邪悪な3大特性の持ち主がリーダーになるような事態はなるべく防ぐほうがいい。性格はキャリアを発展させる重要な要因ではあるが、邪悪な特性が有効なのは個人レベルであって、集団には寄与しないのだ。
HBR.ORG原文:Why Bad Guys Win at Work November 02, 2015
■こちらの記事もおすすめします
腐ったリンゴは例外ではない:倫理観の低い従業員をマネジメントする法
堅実な「リスク回避型」の人が、危険なリスクテイカーに変わる時





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)