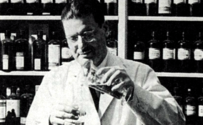リボンフレーム 各ステップのポイント
ブランディングは、シンプルな3つのステップで実行できると書きました。しかし、当然ながら、インプットは調査をすればいいというものではありません。コンセプトも規定すればいいというものではないし、アウトプットは作ればいいというものではない。それぞれのステップで工夫が必要です。まさにそこに、ブランディングにデザイン思考を取り入れ、融合させることの意義があります。
●インプットのポイント
表層的な調査によって、ブランドの本質価値や生活者のインサイトが見えてくることはまずありません。言葉にならないような、人の無意識にアプローチすることが不可欠です。
さまざまなリサーチのなかでも、人間の行動観察と深層心理の洞察が特に重要です。ブランドとファンとの間にはどんな関係が構築されているのか。ユーザーにとってそのブランドの本質的な価値は何なのか。反対に、そのブランドをまったく利用しない人にとっては何が障壁なのか。どのあたりに機会があるのか、等々。
観察型・洞察型リサーチのポイントとして、以下の点が挙げられます。
・先入観を捨て、虚心坦懐に現場に臨むこと。
・対象者の発言や行動に対する「小さな違和感」を大切にし、見逃さないこと。
・発言や行動そのものだけでなく、背景にある「生活文脈」をまるごと理解するよう努めること。
観察型・洞察型調査の代表的な手法として、エスノグラフィ・リサーチが注目されています。もともと人類学や社会学の領域で使われてきた方法が、ビジネスの世界でも有効ということでさかんに活用されるようになってきたことをご存知の方も多いと思います。
●コンセプトのポイント
コンセプトには、「概念、観念」という意味のほかに、「創造された作品や商品の全体につらぬかれた、骨格となる発想や観点」という意味があります(『大辞泉』)。ブランディングでは、後者の意味を重視します。
インプットで得られたさまざまな情報は、他の情報と関連づけられ、統合されてはじめて「コンセプト」へと昇華され、ブランド全体をつらぬく骨格となります。一見無関係のように見える事実どうしの間に関係性を見出し、統合する作業は、難しいけれど、知的刺激にあふれたクリエイティブな作業です。
すぐれたコンセプトには、少なくとも以下の3つの効果があります。
・ブランドが目指す姿がわかりやすく、関係者間で共有しやすくなる効果。【共有力】
・さまざまな活動の起点となり、新たなアイデアが生まれるきっかけとなる効果。【起点力】
・そのブランドから生み出されるアクションに対する期待を高める効果。【期待力】
コンセプト開発にあたっては、ブランドに関わる多様な関係者を集め、さまざまな視点と知見をあわせ、共創スタイルで集合知を形成していくことが非常に大切です。
●アウトプット
アウトプットは、ブランドのコンセプトを具現化し、展開するフェーズです。
ここでは特に、「プロトタイピング」を大切にしています。頭だけで考えるのではなく、まずカタチにし、そこから得られる気づきを大切にするというやり方です。
プロトタイプをつくる際、最初から完成度の高いものをつくる必要はありません。むしろ逆に、どんなに粗っぽくてもいいから早くカタチにしてみる、という考え方が推奨されます。かのIDEOは、“We Think to build, build to think.”(「つくるために考え、考えるためにつくる」)というモットーを掲げています。
3Dプリンタ等のツールの普及によりプロトタイプ制作が容易になったことはご存知の通りですが、プロトタイピングは、有形のモノだけにあてはまるものではありません。例えば、ビジネスモデルをブロックを使って表現することで、うまくいくところ・いかないところを可視化したり、サービスアイデアをスキット(寸劇)で具現化することで、真に顧客にとって価値があるものになっているかを検討する作業等はとても有効です。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)