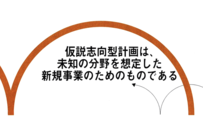言葉が封印された40分間。
そこで何が起きたのか?
ワークショップは、参加者全員が1つの同じ絵を見て、それぞれの感想を言い合うところからスタートします。
「亡くなった母がいる天国の様子かな」と、小田社長。
「火が水に飲まれていくみたいですね」。そう表現したのは文英さん。
「眠る直前に目を閉じたとき、見える光景に似てる」と西川さん。
まさに三者三様。互いの感想を聞きながら「ほー、そうきたか」「なるほどね」という言葉が飛び交います。その直後、長谷部さんが突然絵を90度傾けました。目の前の絵が、ガラッと印象を変えます。
「絵の見方に正解はありません。いつも近くにいる人が、同じ絵を見て、自分とまったく違う感じ方をしていることを、理解し合っていただきたいのです」
たった1つのワークを通して、長谷部さんの言葉の説得力がグッと高まりました。
鑑賞ワークが終わると、進行役をアーティストの谷澤邦彦さん(Kuniさん)にバトンタッチ。絵を描くための簡単なレクチャーに入ります。使う画材はパステルと正方形の画用紙と消しゴム、そして自らの手。画用紙にパステルの色を乗せ、指でこすることで絵を作り上げていきます。これは、人類が最初に絵を描いた時に近い方法なのだそうです。
「人類は、言葉も貨幣もなかった4万年前から絵を描いています。それ以来、絵は歴史から消えたことがありません。なぜ、消えないのか。淘汰が厳しいビジネスの世界に生きるみなさんに、消えないものから何かを感じとってもらいたい。絵のテーマは“働くうえで大切にしていること”です」
ワークショップへの熱い思いを語るkuniさん。当初、3人が「描く」にもっていた不安や猜疑心が、じわじわと溶けていくのを感じました。
1つの机に3人が向き合い、いざ絵を描き始める段になって、ちょっとした事件が起きます。「3人で向き合って描かなくちゃいけないの?1人でじっくり描きたいなあ」と小田社長から提案があったのです。本連載初、会場に新たな机が運び込まれ、3人全員が違う方を向いて描くことになりました。
ここから3人が描き上げるまでの40分間、応接室から言葉が消えました。途中、「いつもこれくらい集中して考えていれば、仕事もうまくいくのになぁ」という小田社長のつぶやきを除いて、会場にはパステルと画用紙と指が接する摩擦音が静かに響きます。
私は、机を分けて互いの姿が見えない配置になったことが、結果としてある種の魅力を引き立てる結果になったと、後から感じました。なぜなら、言葉を交わすきっかけを失ったことで、3人が「描く」過程の違いが鮮明になったからです。
まずは小田社長。なんと、当日の新聞を開き始めました。隅々まで目を通しては、ボールペンでメモを箇条書き。そのメモを見ながら絵の構図を下書きし、パステルの質感を確かめています。30分後、「よし」と呟いてようやく深紅の画用紙を手にとった後も、1つの線を何度も描き直したり、下書きと画用紙を繰り返し見比べたりしながら、細かく丁寧に色を重ねていきます。
3人の中でいちばん表情豊かに描いていたのが、ティファニーブルーの画用紙を選んだ文英さん。ちょっと描いては、くすっと笑う。パステルを空中に浮かせながら、眉を寄せてしばらく悩む。頬をふくらまして腕組みする。「絵が苦手」という言葉が嘘のように、楽しんで描いているように見えます。
迷いなくグレーの紙を選んで誰よりも早くスタートし、淡々としたペースで描き進めていたのは西川さん。大胆な手つきと、明確な線。ほとんど手を休めることなく、最後まで一気に描き上げました。その姿は「没頭」という言葉がぴったりです。
小田社長は、剛胆に見えて繊細。文英さんは慎重で実直。西川さんはまっすぐな職人気質。すべて私の勝手な印象に過ぎませんが、はっきりとそう感じさせるほど、3人が「描く」過程には、それぞれの個性が色濃く現れていました。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)