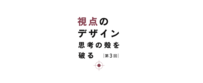テクノロジーの進化によって
新たに生まれた仕事

工学博士、英オックスフォード大学工学部准教授。2012年より現職。専門分野は機械学習。15年から同大学・技術と雇用研究プログラム共同代表。共著論文に「The Future of Employment(雇用の未来): How Susceptible are Jobs to Computerisation?』。人工知能が日本の労働力人口に与える影響の研究を野村総合研究所と実施し発表、注目を集めた。
オズボーン:雇用の乗数効果について具体的な例を示しましょう。米国シリコンバレーで働くIT関係のスタッフは生産性を高めるための圧倒的なテクノロジーを生み出して高給を得ています。そのテクノロジーによって、ある産業では人間の雇用は失われているかもしれません。しかし、そのスタッフの周りには別の仕事が生まれています。ドライクリーニングをピックアップしたり、食事をデリバリーしたり、飼っている犬をきれいにシャンプーしたりするといった仕事です。テクノロジーが生み出すものは効率化だけではないのです。
この乗数効果は、先進国よりも開発途上国の方が顕著です。シリコンバレーでは5つ、インドのIT関係のスタッフの周りでは20の新たな仕事が生まれたといわれています。
川崎:マイクロソフト社のエクセルが普及したら、会計士が要らなくなるといわれた時代もありましたが、私たちの業界ではむしろ、エクセルが浸透したおかげで新しい雇用が生まれました。AIやロボットでも同様のことが当てはまり、現在の私たちの仕事を担ってくれる代わりに、それを支えるためのビッグデータを扱えるエンジニアやデータサイエンティストなどの新しい職業が生まれています。
その通りですね。2000年代、欧州では1000万の仕事が失われました。多くは自動化による影響です。しかし、自動化によって商品やサービスの価格が下がり、消費者のニーズを刺激した結果、900万の仕事が生まれています。さらに先ほどの乗数効果によって、600万の仕事が創られました。新しい未来が開かれると、新たな職業が創り出されることは歴史が証明しています。そんなに「たくさん」の職業を創出するわけではありませんが、新しい職業が実際に生まれてきたことは事実です。
川崎:しかしながら、変化そのものが避けられないとすれば、産業分野や職種によっては仕事を喪失するという厳しい見通しを立てざるを得ないのではないでしょうか。
オズボーン:会計士や弁護士、特に若手弁護士が担っている仕事は、アルゴリズムとの競争に直面しています。ジャーナリストの仕事の中でも、過去の膨大なデータから証拠を見つけたり、裏付けを取ったりという仕事はコンピュータによって代替えされ、そのポジションにいた人たちは、一般的に魅力的でない仕事への転職を余儀なくされています。自動化の負担は、ミドルからボトムの仕事において本格的になりつつあります。
確かに新しい仕事が創出されたとしても、必ずしも人々が望む仕事が増えるとは限らず、社会の新たな不都合と巡り合うこともあるわけです。