-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業は成長とともに、複雑化という病を患う。「一時的競争優位」の提唱者マグレイスが、それを解消するために、4つの要素に基づく選択と集中の方法を説く。
成長する企業は、お決まりの問題に直面する。時とともに事業があまりに複雑化して、自社がその悪影響を被ってしまうのだ。
私が見るところ、この現象に陥る企業はたいてい、競争優位のライフサイクルにおける「利益化(exploitation)」フェーズの只中にある。つまり、事業の立ち上げとスケールアップに成功した後、利益や市場シェアを拡大し、享受する段階だ。ベイン・アンド・カンパニーのクリス・ズックとジェームズ・アレンも、先頃のHBR論文「創業者精神を取り戻せ」の中でこの問題を論じている。
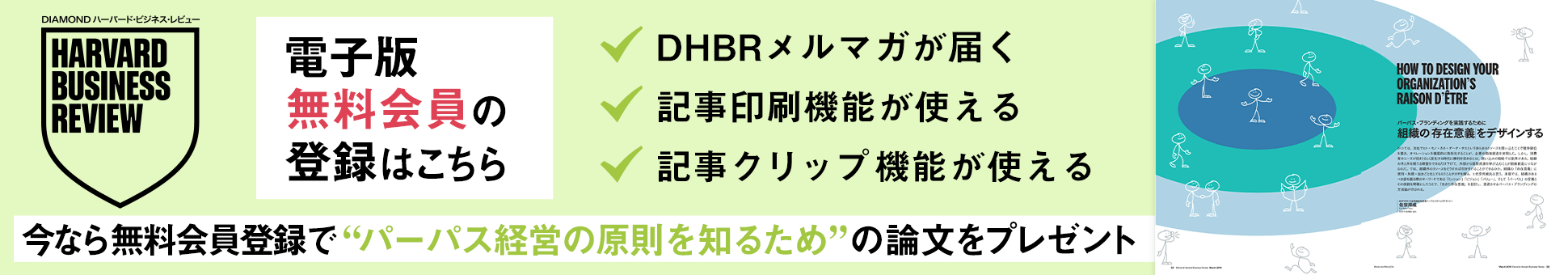




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









