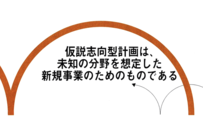ワークショップで
参加者に持ち帰ってほしいものとは
このワークショップはもともと、「絵はもっと自由に描いていい」という思いを伝えようと子ども向けに考案され、2002年に始まった取り組みです。その後、これを大人向けに実施できないかという要請があり、2004年からは大人向けにアレンジしたワークショップがスタートします。今では、企業向けにアレンジした「Vision Forest」という組織変革アプローチとして発展。2015年には、参加者がのべ1万人を突破しました。
ワークショップを共同で提供するのは、アート教育の企画・運営やアーティストのマネジメントを行うホワイトシップと、ビジネスコンサルティングサービスのシグマクシスです。本誌の連載企画「リーダーは『描く』」では、両社の全面協力のもとにワークショップを実施し、その様子を記事化するという形式をとっています。
オープニングトークを終え、ワークショップはホワイトシップアーティストの谷澤邦彦さん(kuniさん)の絵を鑑賞するワークへと進みます。この鑑賞ワークは、参加者の絵に対する先入観を取り払い、絵を見ること、絵を描くことは自由だというイメージを持ってもらうためのワークです。参加者はkuniさんが描いた1枚の絵を見つめ、それぞれが自由に抱いた印象を付箋に書いていきます。起業家の感性とはどのようなものなのか。4人がイメージしたものをすべてご紹介しましょう。
その前に、読者のみなさんもこの絵からイメージされるものを気楽に考えてみてください。格好いい言葉を選ぼうとせず、素直な言葉で。そのうえで、参加者がイメージしたものを読んでいただくと、自分の感性との違いに気づくはずです。どちらが優れているという価値基準はありません。どちらも正解です。鑑賞ワークはイメージの優劣を競うものではなく、それぞれの違いを体感することが重要なのです。
孫さん。
「共感覚」「観る音楽」「セレナーデ」「カディンスキーを思い出した」「放出」
片山さん。
「ねむい」「ねむり」「夢」「ラセン」「奥に何が?」「聴こえる」「潮」
渡邉さん。
「旅立ちの朝」「不安とワクワク」「朝焼け」「日の出」「海」「未知」「くもり」「孤独」「波」
小島さん。
「中央の赤は“情熱”であり“胎児”にも見える」「海=羊水?」「安心」「おだやかであたたかい」
鑑賞ワークの最後に、長谷部さんが参加者に語りかけます。
「人間の脳には、一度そうだと思ったら、そうとしか見えなくなる『認知バイアス』があります。過去に見たことのあるものを基準にして、自分の見たいようにしか見ない性質に縛られているのです。これだけ変化の激しい時代、過去の経験によって決めつけてしまっていいのでしょうか。少し立ち止まって、じっくりと見て感じるという作業を日常にも取り入れると、発想、人間関係、世界の見方も変わってくるのではないでしょうか」
ご覧いただいたとおり、参加者の言葉には一つとして同じ言葉が出てきていません。長谷部さんが言葉を続けます。
「たった4人が同じ絵を見ただけで、これだけ多様な見方が出てくるのです。これが10人100人となってくれば、さらに多様な見方が出てくるはずです。人によって感じ方は違うことがおわかりいただけると思います。でも日常では、自分と考え方が違う人に対してイライラしたり、受け入れることができなかったりする場面が多い。この鑑賞ワークで、違うことが当たり前、違うほうが面白いという感覚を持っていただければと思います」
ワークショップは、kuniさんによる描き方の説明に移ります。いつもはここで、定番となっている参加者とkuniさんの「絶妙(?)な」やり取りをご紹介するのですが、その内容は前回の富士ゼロックスさん、前々回のJリーグさんの記事に譲ります。今回は、kuniさんが真剣に語る、ワークショップの狙いについてご紹介することにしましょう。まずはkuniさんの言葉から。
「洞窟画として残っていますが、人類は4万年前ぐらいから絵を描いていたと言われています。それ以来、人類は絵を捨てたことがありません。大切なメッセージを残す手段として考えられていたからです。でも、当時は筆や絵の具など、絵を描く道具がない。自然界にあるものと、自分の指を使って描いていたのです。今日はそのころと同じ条件で、ご自分のメッセージを描いていただきます」
ワークショップでは、パステルという色つきのチョークのような画材と自分の指だけを使って、4万年前と同じ感覚を味わいながら描きます。冒頭の鑑賞ワークで参加者が鑑賞したkuniさんの絵も、同じ手法で描いたといいます。
「おお!」
参加者にどよめきが起こります。kuniさんはジョークで応酬しました。
「だって、僕、プロですから(笑)」
ひとしきり笑ってから、kuniさんが言葉をつなげます。
「このワークショップは、絵を上手に描くことが目的ではありません。正解を導き出すわけでもありません。描きながら、人間の目的や欲求を描いていた4万年前に思いを馳せ、当時の人々の息吹を想像しながら描く。それができれば、今日のワークショップに参加していただいた意味があると思います」
ワークショップはパステルの使い方、描き方のルール、画用紙の説明に続いて、この日の描くテーマの発表へと移ります。
「働くうえで大切にしていること」
まずは、自分が心の奥底で大切にしている思いを引っ張り出し、それをワークシートに言語化していきます。そして、改めて可視化した思いを絵に表現します。参加者は思い思いのスタイルで描くことに没頭し、およそ50分後には絵を完成させました。4人の絵はもちろんまったく異なります。そこには、どのような思いが込められているのでしょうか。











![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)