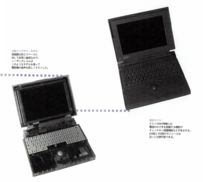イノベーションに運は必要ない
この事例は、本書で紹介されていたほんの一例だが、セグメント情報を注視していては、その企業は間違った方向に進んでしまうことを、わかりやすく示している。「企業が本当に狙いを定めるべきなのは、ある状況下で顧客が進歩を遂げようとしていること、つまり、彼らが達成したいと望んでいること」なのである。どのような「顧客」なのかを見るのではなく、どのような「ジョブ」か、に注意を払う必要があるのだ。その「ジョブ」を解決するものこそ、イノベーションへと通じていく。
クリステンセンと聞くと、イノベーションのジレンマや破壊的イノベーションを思い浮かべる方が多いだろう。氏は破壊的イノベーションの理論を構築し『イノベーションのジレンマ』にまとめるまでに8年の時間を要したという。一方、この「片づけるべきジョブ」理論について氏が初めて『ハーバード・ビジネス・レビュー』に寄稿したのは2005年(日本語版では2006年)と10年以上も前のことで、この理論を本にまとめるまでに、およそ20年の時間をかけたという。
破壊的イノベーションの理論では、市場で確固たる地位を築いた企業が、破壊的イノベータの脅威にどう立ち向かうかを示してくれる。これは守りの側面が強い理論とも言えよう。しかし、ジョブ理論は、より前向きな理論である。
クリステンセンは本書の中で、「『顧客が片づけようとしているジョブ』というレンズを通してイノベーションをとらえ直すことは、私にとって壁が打ち破られた瞬間だった。このレンズがあれば、破壊理論ではなしえなかった、顧客が彼らの生活になんらかのプロダクト/サービスを取りこもうとする原因は何なのかを理解することができる」「イノベーションを運任せから予測可能なものに転換する道程を大きく進展させるのはジョブ理論であると確信している」と述べている。
ジョブ理論は、既存の大企業をはじめ、あらゆる企業が真の競争相手を知り、顧客のニーズを掴み、イノベーションを起こしていくために有効な思考の軸となるはずだ。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)