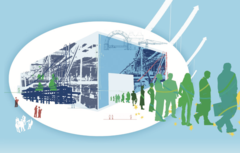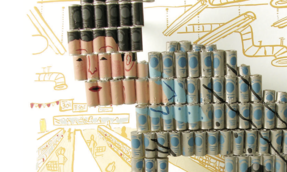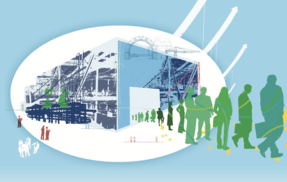-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
近視眼的販売戦略の悲劇
データは、ブランド・ビジネスの現状をありのままに伝えてくれる。2003年から2005年にかけて、世界の消費財市場全体におけるブランド・ビジネスのシェアは13%という驚異的な伸びを示した。
ところが、価格プレミアムは低下し、それに伴ってマージンも減少している。また、消費者の価格感度は、25年前に比べて50%も上昇している。消費財メーカーの経営者を対象にした最近の調査では、10人中7人がとりわけ関心の高い問題として「価格圧力」と「顧客ロイヤルティの低下」を挙げている。
ブランドの効果は減少している。このような状況で四苦八苦している消費財メーカーのなかには、大型ディスカウント・ストアの責任を追及したいところも多いことだろう。実際、これを裏づけるエピソードも少なくない。
アメリカの一般家庭では半世紀前からおなじみのピクルス・ブランド、〈ブラシック〉が1990年代後半、ガロン・サイズの大瓶入りを値引き販売された時のことを思い出してほしい。
ウォルマート・ストアーズが前代未聞の2.99ドルでこのアイテムの販売を始めると、低価格効果で、ウォルマートの売上げが〈ブラシック〉の総売上げに占める割合は30%にも達した。
この激安の大瓶ピクルスは、ブラシック・ピクルス(現在ピナクル・フーズ・グループの傘下)の販路を食いつぶし、マージンを25%も減少させた。ブラシックが価格の適正化を求めると、ウォルマートは当面は値上げしないと拒否し、同製品の販売協力を見直すことにした。そして2001年、ブラシックは連邦破産法11(チャプター・イレブン)条を申請した。
ウォルマートをはじめ、大手小売業者が一部のブランドを衰弱させているのはまぎれもない事実だが、ブラシックとは違い、小売業者と自社ブランドの関係をうまく管理している消費財メーカーも多い。
たとえば、アパレル小売りのフット・ロッカーが、ナイキから提示された価格と商品ラインに抗議して発注を約2億ドル削減した際、ナイキはフット・ロッカーへの割り当てを4億ドル減らして、これに対抗した。消費者はほしい商品を見つけられないことに不満を募らせ、フット・ロッカーで買い物をしなくなり、競合のフィニッシュ・ラインが売上げを伸ばした。最終的に、フット・ロッカーはナイキの条件を飲むことになった。