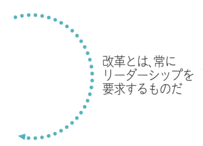最小単位でテストして、
学んだ後に前へ進む
――日本企業の経営者はリスクを取ろうとしないという課題も、多くの識者や投資家が指摘します。
これに対しては、できるだけ実行可能な最小単位でテストをしてから、行動を起こすということが必要です。
大企業では、新たなビジネスへのトライアルの際に、プロジェクトチームを組んで、さまざまな情報を集めて念入りに調査し、検討を重ね、経営上の大きな決断をして、いったんやると決めたら社運を賭けて大規模なプロジェクトとして行うといったプロセスを踏むケースが多いものです。
しかし、このやり方では、プロジェクトを推進するために多数の関係部署のさまざまな合意形成と大きなエネルギーが必要となります。とても時間がかかる上、失敗した場合のロスが大きくなります。
昨今は、ステージゲートシステムというR&Dや事業化のプロセスが一般化しつつあります。プロセスを複数のステージに分け、次のステージに移行する前に収益性と実現性を評価する「ゲート」を設け、それらが低いと評価されたプロジェクトをストップさせる仕組みです。これは多くのケースにおいて有効で、当社は推奨しています。
――米国には、失敗を奨励し、挑戦を促す文化があります。
私は、そうした考え方には賛同しません。そう考えるのは、過去の失敗に学んだためでもあります。
Forbesに所属していた2000年、雑誌の広告面にバーコードを付けて、専用バーコードリーダーで読者がそれをスキャンするとウェブサイトの広告ページに飛んで、読者がさらに情報を得るという仕組みを導入しました。そして、90万人の読者に、無料でバーコードリーダーを配布したのです。
結果は、期待した通りではありませんでした。読者は必ずしもデスクトップの前で本を読んでいるのではなく、ソファーや電車や飛行機のなかで読んでいる人が多かったのです。
結局Forbesはこの事業を中止しましたが、当時の経営者は、「失敗は成功のもと」と言い、失敗をとがめられませんでした。
しかし今では、その行動は誤りだったと明言できます。なぜなら、90万人ではなく、50人にテストマーケティングをしても、同じ結論を導き出せたと推測できるからです。当時、小規模なテストを行っていれば、即座に修正してより良いものに繋げられた可能性があると考えます。
必要以上の規模でテストをして失敗したのであれば、それを祝福してはいけません。間違った選択をしたことを、事後に正当化するために、「失敗は成功のもと」と言ってはいけません。
最小限の単位で行動を起こし、試してみて、その結果、失敗したら、そこから学んでやり方を変えることが重要です。
──ゴールドバッシュさんは今年5月、『Detonate: Why - And How - Corporations Must Blow Up Best Practices (and bring a beginner's mind) To Survive』(日本未訳)を著わしました。本書でも、過去の慣習ややり方に縛られる問題を指摘していますね。
企業が生き残るためには、イノベーションを起こし続けなければいけません。そのためには、多くの組織において築かれてきた悪い習慣、すなわち過去の「ベストプラクティス」を吹き飛ばさないといけない、と本書では書いています。米国のメジャーリーグにおいて、送りバントという戦略がいかに悪い習慣であったかなどの例を挙げて、その論証としました。
これからの時代のイノベーションは、プロダクトを革新するだけではだめで、複合的な革新が重要です。モニター デロイトとその傘下にあるイノベーション専門ファーム・Doblin(ドブリン)は、プロダクト、カスタマーエクスペリエンス、ブランド、プロフィットモデルなど、10タイプのイノベーションのフレームワークを持っています(10 types of Innovation)。それらをどのように組み合わせるかで、イノベーションを起こす可能性を高めることができるでしょう。
繰り返しますが、企業が立てた戦略が成功するかどうかを試すにあたって、過去の例を見て、分析することでは答えは見つかりません。過去をもって、将来の成功を検証することはできないのです。
そうではなくて、最小限の単位で行動を起こして、試して、そこから学ぶことです。その結果、失敗したら、その原因を考えて、やり方を変えて、またトライするという手順で、徐々に前に進んでいくことが大切です。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)