ちなみに、かくいう私も、ニューヨーク市でフリーランスのジャーナリストとして、健康関連のさまざまな顧客へのコンサルティング、コピーライティング、編集をしながら生計を立てている。瞑想アプリについてのフォーカスグループのディスカッションを主催したり、有名なスキンケア商品やジュースクレンズ会社、メンタルヘルスアプリなどの、ウェブサイトやキャンペーン・コンテンツの制作にも携わってきたりした。
最近、ある女性顧客が次のように語ってくれた。瞑想を習慣にするという目標が頓挫したのだが、それは自己管理を含む何もかもを「作業」にしてしまう傾向があるからだそうだ。彼女は日々、20分間の瞑想を続けたところ、結果的にストレスが減るどころか増していることに気づいた。そのせいで罪悪感を抱き、自己嫌悪に陥ったのだという。
現在ではマインドフルネス瞑想は、10億ドル規模のビジネスになるほど人気があるのは事実だが、科学的な裏付けはいまだ不十分だ。
カーネギーメロン大学のヘルス・アンド・ヒューマンパフォーマンス研究所を率いる心理学者であり、著述家のデイビッド・クレスウェルは、過去20年間に行われた瞑想研究を分析し、その論評を2017年に発表。昨今のマインドフルネス研究の方法論的限界を考察している。彼はその中で、マインドフルネスとは不安、鬱、慢性痛、ストレスなどに対する実証された万能薬だという誤解を払拭している。
しかし一方で、素晴らしい発見も指摘している。マインドフルネスは、扁桃体(闘争・逃走反応を司る脳領域)の活動を抑える可能性がある。また、マインドフルネス瞑想にはインターロイキン6(高ストレス者の血中で濃度が高くなるバイオマーカー)を抑える効能があることもわかっている。
将来、科学的発見によってマインドフルネスの効果が立証されるかどうかにかかわらず、覚えておくべきことがある。それは、万人に効くストレス解消法は存在しないということだ。
瞑想が「作業」のように感じるなら、それは自分を開放するどころか、縛りつけるものになりかねない。瞑想を、ワークライフバランスという困難な目標を達成するうえで必要な手段だと見なしていると、「作業リストの項目を消化する」という直線的な思考になってしまう。時間がない日や、やる気が起きない日の対処法を考えず、必ず瞑想をするのだと決めてかかると、結局は罪悪感や自己批判に陥るかもしれない。
とはいえ、瞑想を難しいと感じたらただ諦めればよい、というわけではない。重要なのは、古代から続くこの習慣が、米国の現代文化によって、自己改善のツールとしていかに商品化されているかを知ることである。
そもそも、「やることリストを消化しよう」という意識がストレスの主な要因ならば、わざわざそこに瞑想を追加する意味があるだろうか。目標は、自分の心に余裕をつくり、好奇心を持って、重圧を感じずに探求することなのに。
たとえば、通勤中に少しの間、呼吸に意識を集中させてみるのもよい。家を出る前に、その日に自分はどうありたいか、という目標や心構えを設定してもよい。覚えておいてほしいのは、自分自身を苦しめることは本質的に善良な行為ではないということだ(参考までに、私はこの「自分を苦しめない」を1日の心構えにすることが多い)。




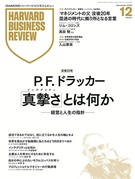
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









