さらに極端なケースでは、自己改善が強迫観念と化すこともある。歩数や睡眠周期を追跡するFitbit(フィットビット〉のようなウェアラブル機器が増えたことで、完璧主義の傾向が増長されうるからだ。
英国のマーケティング学教授、リッケ・デュースとマイク・クーレイは、女性200人のグループを対象に、フィットビットの使用がもたらす影響を分析した。女性たちは、この機器で目標を達成できなかったときに、必ず罪悪感を抱いたと答えている。被験者の79%が日々の目標達成への重圧を感じ、59%は「機器にコントロールされている」とさえ感じたという。そして、30%近くがフィットビットを「敵」と呼んだ。
日々の歩数がわかれば、自分で生活をコントロールしていると思い込めるかもしれない。しかし、自分の体が(表向きには自分のために)している「作業」を数値化することで、「自己管理は作業としてやるべき」という考え方が助長されるだけでなく、自己批判の機会も増えてしまう可能性がある。歩数、睡眠、呼吸、歩行速度、カロリー消費量などに関する進捗状況が四六時中レポートされるため、数値化された自己改善は、きわめて些細な目標を達成できなかったときでも気に病むという傾向を助長してしまうのだ。
自分を責めることは、自分に活を入れるための最善の方法と思われがちだ。しかし、自分を批判すると失敗が頭から離れなくなり、鬱や不安、薬物乱用につながり、否定的な自己イメージを抱きやすくなることがわかっている。
この種の自己管理が容易に自己批判へと転換しうる、という点から考えると、ソーシャルメディアは危険な誘因だ。特にインスタグラムは、自分の「勝利」をシェアし、それを自己マーケティングの機会に変えなければ、という重圧をもたらす。カラフルなサラダや運動後の自撮り写真に「いいね!」をもらおうと躍起になることは、モチベーションの大きな源である。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校での2016年の研究によると、インスタグラムの投稿に「いいね!」をもらうと、側坐核という脳の領域が活性化されるという。これは、チョコレートを食べたり、賞金を得たりすることで活性化する領域だ。
だが同時に、この「何でもシェア」が強制される文化によって、だれもが自分と他人とを比較するようになっている。私は本稿を書いている際も、気づけば「#自己管理」(selfcare)というハッシュタグを使い、自分の日課をインスタグラム内の500万件以上の投稿と比較している。ろうそくを灯した泡風呂から、「自分を肯定しよう」という心打つ引用句が書かれたモノクロの背景を前に料理している場面まで、これらの投稿は、さまざまな活動を写真に収めて披露している。
インスタグラムでの「#自己管理」の盛り上がりにもかかわらず、人々の幸福感は高まっていない。それどころか、最近のある研究では、インスタグラムはメンタルヘルスにとって「最悪」なソーシャルメディア・プラットフォームだと指摘されている。非現実的な期待を抱かせ、研究者らが言うところの「比較して失望する」という態度を植え付けることで、ユーザーの無力感と不安感を高めるというのだ。
ある友人は私に、次のように語った。「旅行の写真を見ると、自分が貧しくなった気がする。ジムの写真を見ると、自分が不健康な気がする。食べ物の写真を見ると、おなかが空く。よい写真が精選されているのを見ると、自分は大雑把だなぁ、と不安になる」




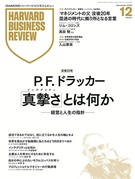
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









