もちろん、「改善」のために自己鍛錬の儀式に取り組むのは、古くから続く気晴らし法だ。絶食や極端な食事制限による自制は、多くの主要な宗教の中核を成し、しばしば精神の浄化、贖罪、悟りを得る手段となる。現代でも、人々が心身のコントロールに努める根底には、それが道徳的責務なのだという思想がある。
しかし、今日の解決主義(どんな問題にも解決策が見つかるという考え方)とテクノロジーの世界では、上記とは異なる部分がある。健康アプリや健康食品などの消費財の助けを借りて自己管理を優先することは、単なる自己鍛錬や道徳的美徳の証ではない。それは、成功と文化的ノウハウの象徴なのだ。
ジャーナリストのエイミー・ラロッカは、昨年執筆した"The Wellness Epidemic"(健康病のまん延)という記事の中で、次のように述べている。豪華な瞑想スタジオ、アーユルベーダ・クレンズ、アルコールなしの早朝ダンスパーティといった世界では、健康という空想的目標は富裕層だけが手に入れられるものとなっている。「セリアック病っぽい症状」(グルテンによって生じる自己免疫性疾患)の診断を受けたり、1000ドルのスキンケア商品を購入したりする時間とお金のある人々だけのものなのだ。
「健康志向の世界で少し過ごしてみると、誰もが何らかの病気と診断されているように見える」とラロッカは述べる。健康志向文化の皮肉なところは、完璧でいることは可能(または不可能)だという思いに駆られて、常に病気の不安に注意を向けなければならない点だ。
1本9ドルのグリーンジュースや、35ドル以上もする高級な室内自転車エクササイズといった野心的な今日の自己改善活動は、ほとんどの人の手に届く代物ではない。これらは習慣の順守と達成という価値観に支えられた自己管理をさらに抑制することにつながる。ただし同時に、自己管理の負の部分――無力感と自己批判の感情――も抑制される。
お金やハードなエクササイズを必要とせず、目標必達主義や測定主義の思考から離れても、個人の成長や自己管理、純粋なストレス発散ができる機会は無限に存在する。予定していたほど成果の上がらなかった日には、自分のことを大目に見てやってはどうだろう。あるいは、笑いには癒しの効果があることを思い出してもよいだろう。
我々は記録・シェアできる行動や、収集・追跡できるデータを理想としがちだ。しかし、気分を晴らすために(そして実際に健康になるために)、それらを必要としない場合も少なくない。よくも悪くも、やるべきことを減らすために役立つアプリは存在せず、お金をかければできるわけでもないのだ。
HBR.ORG原文:How Self-Care Became So Much Work, August 10, 2018.
■こちらの記事もおすすめします
マインドフルネスは目標達成のお役立ちツールではない
幸福を追求するがあまりパラドックスに陥ってはいないか
誰にも邪魔されない「不可侵の日」を週に1日は設けるべき理由
シャーロット・リーバーマン(Charlotte Lieberman)
ニューヨークを拠点とするライター、編集者、コンテンツ・コンサルタント。『ニューヨーク・タイムズ』紙、『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌、『マリ・クレール』誌、『ゲルニカ』誌などに寄稿している。ツイッターは@clieberwoman。




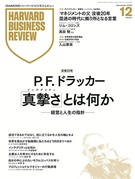
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









