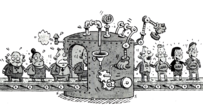●ネットフリックスは、すべての市場に同時に参入しようとは試みなかった
そうではなく、地理的・心理的な距離、つまり市場間での認識の差異が少ない隣接市場を慎重に選んだ。たとえば、同社が2010年に最初に国外進出先として選んだカナダは、米国の隣国であり、多くの類似点を共有している。
このように、「よそ者」としての障壁がさほど大きくない国々で、国際展開のケイパビリティを伸ばすことができた。その過程で、自社の中核をなすケイパビリティを、自国市場の外で拡大し高める方法を学んでいった。
つまり、ネットフリックスのグローバル化のプロセスの第1段階は、市場拡張の伝統的なモデルに沿ったものであった。とはいえ、その過程で得た経験と学びから、数年で多様な市場へと進出するためのケイパビリティを伸ばした。そして、第2段階が来る。
この第2段階は、より迅速で広範囲な国外展開を伴うものであった。ネットフリックスは、より多様な市場で運営するために、第1段階で学んだ教訓を生かしながら約50ヵ国に進出した。これらの市場は魅力度を考慮して選ばれた。それは、市場間の類似性、富裕な消費者層の存在、ブロードバンド・インターネットの利用可能性などである。
第2段階では引き続き、国際展開のノウハウに加え、地元の利害関係者との提携についても学ぶことができ、この間に収益も拡大している。より遠距離の市場への展開を支えるために、各地域の嗜好に合わせたコンテンツへの投資、およびビッグデータやアナリティクスの技術への投資が行われた。
第3段階でのネットフリックスは、市場参入のペースにますます弾みをつけ、これまで学んできたすべてを活かして190ヵ国へと展開した。そうしてコンテンツに関する人々の嗜好、現地に見合ったマーケティング、自社の組織運営について、ノウハウを獲得した。
その後に重視しているは、対応言語の追加(字幕を含む)と、コンテンツのグローバルな品揃えに対応するパーソナライズ・アルゴリズムの最適化だ。そして、デバイスやオペレーション、支払いシステムをめぐる他社との幅広い提携を進めることにも注力した。たとえば、2016年にポーランドとトルコに参入した6ヵ月後には、ユーザーインターフェース、字幕、吹き替えに現地語を追加した。
これまで参入してきた市場と同様に、アーリーアダプター(新し物好き)をターゲットにサービスを開始し、その後は幅広い視聴者を引きつけるために機能追加を迅速に繰り返していった。
一部の国、特に新興国や発展途上国では、ほとんどの人は携帯電話でインターネットにアクセスする。このことを認識していたネットフリックスは、モバイル体験(携帯向けの登録手続き、本人確認と認証、ユーザーインターフェース、ストリーミング効率など)の向上に、より重点を置き始めた。機器の製造会社、携帯電話やテレビの事業者、インターネットサービスのプロバイダーとも関係を構築している。
●新市場では他社と手を組み、現地の状況・文脈に対応
同社は地元でカギを握る企業と提携して、ウィン・ウィンの関係を構築している。携帯電話やケーブルテレビの事業者らと手を組み、ネットフリックスのコンテンツを彼らの既存のオンデマンド配信サービスに加えた例もある。
たとえば、ボーダフォンがアイルランドの顧客に向けてテレビサービスを始めたときには、テレビのリモコンにネットフリックス専用のボタンを加えた。最近では、スペインとラテンアメリカのテレフォニカ、日本のKDDIとの取引を発表している。
そしてネットフリックスは、最高コンテンツ責任者であるテッド・サランドスの言葉、「優れたストーリーテリングは国境を超える」を信念としながら、現地のコンテンツに対する顧客の嗜好にも応えている。現在では17ヵ国でオリジナルのコンテンツを制作している。
重要なのは、このようなコンテンツは「ローカルからローカルへ」だけでなく、「ローカルからグローバルへ」という視点でつくられていることである。言い換えれば、コンテンツが制作された当地の視聴者のみではなく、もっと幅広い視聴者を惹きつけることを目指しているのだ。こうしてネットフリックスは、世界中でローカルコンテンツに投資することで利益を得ようとしている。
各地域や国で、大手制作会社とのコンテンツ契約のプロセスが長引いてしまうことへの対処として、ネットフリックスはグローバルなライセンス契約を増やしている。これにより、コンテンツを同社のすべての市場に同時提供することが可能になる。
同社はまた、現地で制作されたコンテンツの採用も始めている。おかげで、それらの制作者はグローバルでの視聴者を獲得することができ、双方にメリットがもたらされている。
ネットフリックスはまた、顧客に関する自社の深い洞察を国際市場に適用している。その知識を活用して、幅広い顧客層を引きつけるコンテンツをつくるのだ。
同社は、非常に急速に世界展開する一方で、顧客中心のオペレーションモデルは、すべての市場で貫いている。米国で成功のカギとなった、顧客の利用データを用いて、どのサービスが最も効果的かを判断するやり方だ。非常に多くの国々で運営しているため、それぞれの市場で異なるアプローチを試すこともできる。世界の会員数が伸びるにつれて、同社の予測アルゴリズムの性能は向上し続けている。
ネットフリックスは、各国特有の知識を得ることが、現地市場での成功には欠かせないことを実証した。政治、制度、規制、技術、文化、顧客、競合他社に関する広く深い知識である。各地域の文化を理解することで、その違いに敏感となり、対応できるようになったのだ。これによって同社の信頼性が高まり、カギを握る利害関係者と円滑な関係を構築するのに役立っている。
ネットフリックスの拡張戦略におけるこれらの要素は、私が「エクスポネンシャル(指数関数的)・グローバリゼーション」と呼ぶ、新たなアプローチを構成している。それは入念に練り上げられた拡張のサイクルであり、ますます迅速に、ますます多くの国々と顧客に対して実行されている。このアプローチにより、同社は競合他社よりもはるかに急速に拡張できた。
今後、アマゾン・プライムなどのグローバルプレーヤーのみならず、新規参入者や現地企業をも相手に、ますます熾烈な競争に直面するだろう。その点を踏まえると、同社はグローバルとローカルのコンテンツをミックスさせる戦略を引き続き拡大していく必要がある。
市場と技術上のさまざまな要因から、エクスポネンシャル・グローバリゼーションは数年前まで不可能であった。世界の多くの地域で高速ブロードバンドがなかったこと、インターネットの普及レベルが非常に低かったことなどもその一因である。スマートフォン、タブレット、スマートテレビ上などでのインターネットの一般的な広がりに伴い、ネットフリックスは、いまや上述の戦略が実行可能な選択肢であることを実証した。
ただし、それには現地の状況・文脈に精通することが求められる。現地の知識を得て、文化的な敏感さと対応力を示すことが必要なのだ。勝者独り勝ちの市場がますます増えていく中、そのような環境にいる企業は、ネットフリックスと似たような国際化戦略を採る必要があるだろう。
ネットフリックスは次の成長段階をどう迎え、新たな課題にどう対応するのか――その物語はこれまでと同様、目が離せないものになりそうだ。
HBR.ORG原文:How Netflix Expanded to 190 Countries in 8 Years, October 12, 2018.
■こちらの記事もおすすめします
ネットフリックスの元最高人事責任者は、ベンチャーの従業員特典に警鐘を鳴らす
経営知識が国境を越えられない理由
ルイス・ブレナン(Louis Brennan)
ダブリン大学トリニティ・カレッジのトリニティ・ビジネス・スクール教授。国際的なビジネスおよびオペレーション戦略を教授・研究対象とする。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)