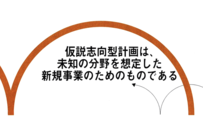残念ながら、開放性の定義とその程度を決定する要因について、研究者は数十年にわたり堂々めぐりの議論を繰り返してきた。その原因の1つは、これらを測定する信頼の置ける方法がなかったからだ。ところが最近になって、心理学界が開放性の定義や、それを定量化するための適切な方法を提供してくれるようになった。
画期的だったのは、「知的謙遜」と呼ばれる宗教的コンセプトに研究者が着目したことだ。信仰を捨てるべきだという証拠を示されても固執する人がいる一方で、新しい信仰を早々に受け入れる人がいるのはなぜかを、哲学者は研究してきた。知的謙遜は、これら2つの極端な行動の中間に位置する美徳である、と哲学者は言う。それは変化を受け入れる意思であり、変わるべきではない時を知る知恵である。
ここ数年、さまざまな大学の科学者たちが、この考え方を心理学の世界に取り入れ始めた。そして2016年、ペパーダイン大学の教授陣が、知的謙遜のコンセプトを4つの要素に分解し、それを測定する評価方法を発表した。
1. 他者の意見を尊重する
2. 自分の知性を過信しない
3. 自我と知性を区別する
4. 自分の見解を見直す意志を持つ
知的で謙虚な人は、これらの要素すべての点数が高くなる。ペパーダイン大学の教授らは、このように分解することで、私たちが開放的な心を持てないとき、何が妨げとなっているかを特定する賢明な方法を考え出したのだ(たとえば私の場合、「自我と知性を区別する」の項目で点数が低かった……痛恨だ!)。
しかし、これらのコンセプトに注目した哲学者たちは、この問題にはもう1つの要素があると考える。ロヨラ・メリーマウント大学のジェイソン・ビア教授は、「私はそこにこだわっている」と説明する。彼は開放性を「異なる認知的視点のメリットを真摯に取り入れるために、既定の認知的視点を超越できる特性」と定義する。要は、知的で謙虚でも(物事の考え方を変える用意はあっても)、他者の意見を聞こうという好奇心がなければ、真の意味で開放的にはならないということだ。
ビア教授は、有効性が実証されているビッグ・ファイブ性格診断に、そのギャップを埋めるための要素があると指摘する。その要素とは「経験への開放性」、すなわち新しいことを試してみたり、新しい情報を取り入れようとしたりする意欲だ。
経験への開放性が、ピクルス味のアイスクリームを食べてみることだとすれば、知的謙遜とは、初めは好きになれないだろうと思っていたとしても、実は好きだと認める意志を持つことを指す。双方の点数が高い人は、相手が誰であろうと他者の話を聞いた後に、ベンジャミン・フランクリンのような認知的柔軟性を持つ傾向がある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)