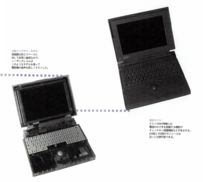-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
新年度、期待に胸を膨らませて、新しい仕事に就いたり、新たな職場で働いたりする人が多いことでしょう。しかし、思い通りの成果が出せなかったり、新環境に馴染めなかったりで、気分が落ち込むビジネスパーソンもいるかと存じます。そうした人や、そうした部下を持つ管理職にとって有効な処方策を提示するのが、DHBR最新号の特集「セルフ・コンパッション」です。特集の背景には、日常的なストレス環境があります。近年、グーグルなど米国の先進企業で導入されている「マインドフルネス」と密接に関連する考え方を論じています。
セルフ・コンパッションとは、あるがままの自分を認め、自分に対して寛容になる態度です。
特集の第1論文では、この傾向が強い人は、自己を成長させるモチベーションと、自分に誠実であるオーセンティシティが強いことを示します。いずれも、リーダーシップを加速させる要素です。そのため、セルフ・コンパッションは、自分とチームを成長させるために重要であり、学んで伸ばすことができると説明します。
特集2番目の論文は、総論的位置付けです。まず、セルフ・コンパッションという考え方の、他のストレスマネジメントとの違い、誕生までの歴史的経緯、マインドフルネスとの関係性が整理されます。そのうえで、効用と高め方、実践法の一つである「慈悲の瞑想」を詳述しています。
3番目の論考は、3つの小論文の組み合わせです。1つ目は、セルフ・コンパッションを高める方法がどのように機能するかを、事例で示します。功績を上げたのに上司が評価してくれないという身近なケースの分析で、分かりやすい説明になっています。
2つ目は、ストレスによって受けるダメージにどう対処するか、「レジリエンス」(再起力)を育む方法を紹介します。ベストセラー『サーチ・インサイド・ユアセルフ』(チャディー・メン・タン著、英治出版)で注目を集めたグーグル。同社が設立したNPOのCEOが筆者です。
3つ目は、ストレスが高まるのに先んじて、それを制する機会を提供する手法として有名なRAINを紹介します。RAINは、「Recognition=認識する」「Acceptance=受容する」「Investigation=探求する」「Non-Identification=自分そのものではない」の頭文字を撮ったもので、この手法を使えるようになれば、ストレス環境下でも、理性的に対処できるようになると説きます。
セルフ・コンパッションもマインドフルネスも、導入して成果を出している日本企業はまだ多くありません。ただしスポーツの世界では、個々のアスリートが経験的に、類似した考え方を実践しています。
その典型例をガンバ大阪の監督、宮本恒靖氏に見て、インタビューしました。サッカー日本代表でキャプテンシーを発揮していて、そのリーダー論は秀逸ですが、特集関連で言えば、そこに至るまでの経験(小学生時代の体験やシドニーオリンピックの時の苦い経験など)を経ての、自分を客観視する力が参考になります。
最後は、特集テーマの歴史的な意味合いを東京大学東洋文化研究所教授の中島隆博氏に伺いました。宗教革命を経て個が確立した近代以降、「自分とは何か」の問いは近代以前よりやっかいな苦しさを持つに至りますが、セルフ・コンパッションはそれへの"中和剤"ととらえられるとのことです。
自分で自分をそんなに厳しく問い質さなくてもよい、というのです。その苦しみからの解放をご自身の体験から説いてくださり、読み手の肩の荷が下りる感じがするかと思います。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)