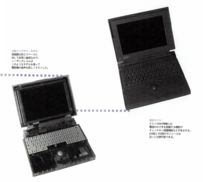宇沢弘文氏が追究した社会的費用
国内総生産(GDP)は、国内で1年間に創出された付加価値の総和で、経済力を示す重要な指標です。巻頭論文では、そのGDPが今日のデジタル化経済を捕捉しきれていない、と主張します。例えばウィキペディアは、調べごとにおける付加価値を高めているが、無料サービスのためGDPにカウントされていない、などの指摘は納得がいきます。
同様の研究は近年、増えています。野村総合研究所(NRI)は2017年度から本格的に研究を始め、2018年に『デジタル資本主義』、今年3月に『デジタル国富論』(共に此本臣吾・監修、森健ほか著、東洋経済新報社)を発表し、GDPでは捕捉できていない経済変化を理論と調査によって分析しています(具体的にはNRI社長の此本臣吾氏のインタビュー記事をご参照ください)。
同社の研究にインスピレーションを与えたとされるのが、今号の巻頭論文の著者であるMIT教授エリック・ブリニョルフソン氏や、『限界費用ゼロ社会』(NHK出版)の著者のジェレミー・リフキン氏です。
以上は、GDPにプラスオンされるべき付加価値についての研究です。一方、マイナスされるべき費用を無視しているという視点からの見直し論も、多くあります。代表例が、社会的費用。例えば、環境への負荷です(「グリーンGDP」という指標がありますが、完全ではありません)。その中で、今日、最も注目されるのが地球温暖化問題からの視点です。
世界的経済学者の故・宇沢弘文氏は1974年の『自動車の社会的費用』以来、社会的費用を包括した経済学の確立を志向されていました。1995年の『地球温暖化の経済学』や2000年の『社会的共通資本』(3冊とも岩波書店)などでは、市場経済制度下で地球温暖化問題を解決する策として、炭素税を説いています。
前述のリフキン氏の今年2月刊の『グローバル・グリーン・ニューディール』(NHK出版)でも、炭素税が温暖化防止策として世界の合意を取りやすいという話から始まって、その他の制度やビジネスの転換を詳述しています。
測定しにくく影響が未知であるために放置されていた温暖化問題は、科学的追究の結果、制度やビジネスに織り込んで制御しないと深刻な事態を招く、人類最大のリスクと認知されてきたのです。
冒頭で言及しました『ペスト』では、ペストという不条理への対処策は、人々の記憶であるとして、この小説の記録としての意義を示します。感染症禍は一時的に終息しても、菌は消滅することなく、いつかどこかで暴れ出す。その時のために、記憶し、記録するのです。急激に収縮する実体経済への対処策では、リーマンショックの記憶と記録が役立てられることを切に願います(編集長・大坪 亮)。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)