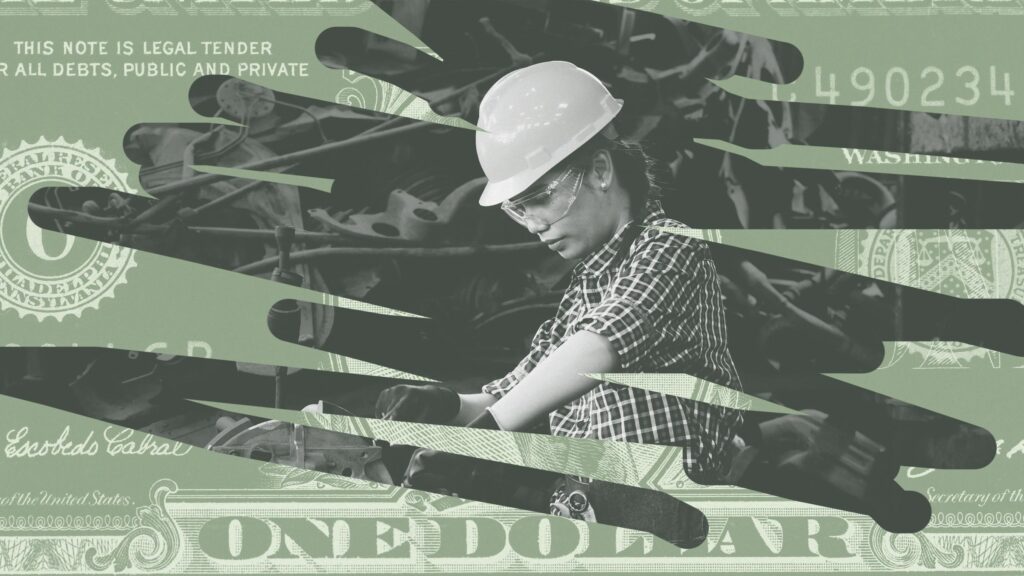
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
給与の透明化はよいことか
米国の従業員の約半数は、非公式な規範あるいは公式な方針として、給与情報を秘密事項としているが、企業は給与の透明化を求める声に直面している。世界中の地方政府や中央政府はいま、給与の透明性を高めることを目的とした法律を相次ぎ制定している。
これらの法律は、男女別の給与統計を集計して報告することを義務づけるものから、個人の給与や納税申告書まで全面的に開示することを求めるものまでさまざまだ。ニューヨーク市も2022年11月から、すべての新規求人情報に「誠実な」給与範囲を掲載することを義務づけた。
一方で、グラスドア・ドットコム、ペイスケール・ドットコム、サラリー・ドットコムなどのウェブサイトや、簡単なスプレッドシートを使った各地の従業員の取り組みによって、雇用者の給与情報に自由にアクセスできるようになっている。こうした給与の透明性を求める声が高まることに伴い、給与を秘密にする長年の規範や方針は実効性を失っている。
しかし、この給与の透明化はよいものなのだろうか。個人や組織にとって望ましい結果をもたらしているのだろうか。この疑問に対し、最近の学術研究において、重要だが、複雑になりがちな答えが示されている。本稿では、給与の透明性が仕事のさまざまな側面にどのような影響をもたらすのか、解説していく。
給与の公平性
プラスの面では、給与の透明化によって性別、民族、性的指向、その他の側面による給与の不平等が減少している。たとえば、筆者らが最近『ネイチャー・ヒューマン・ビヘイビア』で発表した研究では、給与の透明化が米国の公的学術機関で急速に進んだことで、男女間の給与格差が劇的に縮小し、一部の州では格差が解消されたことが明らかになった。さらに、
この重要かつ明らかに望ましい結果を除いては、給与の透明化の影響を評価することはとても難しい。他の実証研究によると、ニューヨーク市の法律が義務づけているような給与の透明性は、不公平に低い給与を上昇させるものの、従業員の全体的な賃金を低下させる。
その根本的な原因は、現在の給与や給与範囲を公にすることで、雇用主が採用候補者や既存の従業員と交渉しないことを後ろ盾のある形で約束するためだと考えられる。個人と交渉をすると、他のすべての(あるいは多くの)従業員と交渉しなければならなくなると雇用主は主張できるのだ。言い換えれば、このような給与の透明性は、雇用者が期待する給与を明らかにするものの、従業員の相対的な交渉力を低下させるおそれがある。
生産性
筆者らが『ナイチャー・ヒューマン・ビヘイビア』に発表した研究では、透明化によってより公平な給与、つまり従業員全体の業績と一貫して結びついた給与につながる一方で、より均一で業績に基づかない給与になることもわかった。
このように給与と業績の関連性が弱くなると、従業員の生産性が低下する可能性がある。それは、給与の透明化によって何が明らかになるのか、そして誰に示されるのかによって左右されると考えられる。
筆者らの別の研究では、給与の透明化によって、会社が業績に対して給与を公平かつ一貫して配分していることが従業員に明らかになった場合、従業員の全体の生産性は向上することが示された。しかし、たとえば性別による差別など、給与が不公平に配分されていることが明らかになった場合は、全体の生産性が低下した。
個人の生産性も、給与の透明化によって従業員の待遇がどのように変化したかに応じて、予測可能な形で影響を受けた。たとえば、自分の給与が不当に低いことがわかった従業員は、生産性が低下した。一方、自分の給与が不公平に高すぎる(つまり業績に見合った以上の報酬を得ていた)ことがわかった従業員は、驚くことに生産性が上がった。後者の従業員の動機は、自分の高給を他者に対し正当化したいか、あるいは給与が透明化されたことでさらなる昇給には業績を飛躍的に向上させるしかないという意識を反映しているからかもしれない。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









