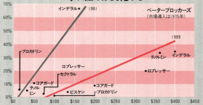顧客がよりコントロールできるようにする
人々(特に若い世代)は、自分の体験を「選択する」のではなく、「指示する」世界に慣れ親しんでいる。必要なデータはすぐに手に入り、自分で簡単に対応でき、顧客体験は双方向の対話となる。デジタルエンパシーでは、顧客体験は顧客に対して行われるものでも、顧客のために行われるものでもないと認識されている。顧客が主体的に調整できるものなのだ。
非接触型サービスがしばしば失敗するのは、融通が利かず、非人間的で、不必要に複雑だからである。ラスベガスのホテル、コスモポリタンのデジタルコンシェルジュ「ローズ」は、顧客がチャットボットと人間の介入の境目がわからなくなるところまで急速に進化している。部屋の環境からルームサービス、ディナーの予約、請求書に関する問い合わせまで、ローズはゲストの手足となって働き、完全で適切な情報に瞬時にアクセスする。
直感的に、頭を使わずに使えるようにする
デジタル技術をいち早く取り入れることは、技術に詳しい人たちにとって必然的なことだ。しかし、私たちはいま、あらゆるやり取りが自然でスムーズに行われなければならない段階に来ている。世界では事実上、誰でも技術者になることができ、物事は機能するのが当然だと考えるようになっている。取扱説明書に対する寛容さは、ゼロに等しい。
スマートホームのプラットフォームとなった賢いデジタルサーモスタット「ネスト」は、手動で設定することもできる。しかし、ほとんどの住宅所有者がこのデバイスに任せ切りであることに、ネストの開発会社を買収したアルファベットは気づいているに違いない。ネストは、最小限の調整で、適切な時間帯に適切な場所で適切な温度を設定している。
顧客の不安をかき立てるポイントを可視化する
ちょっとした透明性があれば安心感につながることが、これまでに繰り返し示されてきた。映画の残り時間やダウンロードの進捗状況を示すプログレスバーもその一つだ。
UPSはこの心理を荷物の配送状況に応用し、倉庫から自宅玄関までの各段階における配送状況を案内する通知を積極的に送信している。顧客は、配送トラックの位置をリアルタイムで確認し、配達時間を変更することもできる。ウーバーも、配車サービスで同様のサービスを提供している。
全体的な観点を持って体系づける
顧客の中でデジタルとリアルが融合してきたのと同じように、企業も顧客サービス戦略においてデジタルとリアルの境界線を曖昧にする必要がある。
ジェットブルー航空は、自社のソーシャルメディアアカウントを独立したデジタル領域として扱うのではなく、他の業務と本質的に結びついた重要なチャネルとしてとらえている。たとえば、ツイッターのフィードを積極的に監視し、運用の手掛かりを探って地上のスタッフに即座に伝えている。
今日のデジタルツールは、ここ数世代にはなかったような破壊的な力を持っている。多くの業界において市場の秩序を揺るがすだろう。この新しい力はたしかに魅力的な機会を与えてくれるが、それはデジタルエンパシーを中心に据えた場合に限ってのことだ。
次世代の成功するビジネスモデルは、デジタルエンパシーの原則を取り入れ、顧客との関係を積極的に強化するものである。このコンセプトが強力なのは、テクノロジーを使って、人間らしさを人間の体験に取り戻すからにほかならない。
"4 Principles for Improving Customers' Digital Experience," HBR.org, March 10, 2023.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)