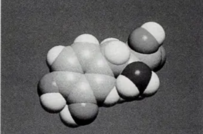問題発見を評価する
「問題ではなく解決策を持ってこい」というリーダーシップの定番の格言を、真に革新的なリーダーが口にすることはない。問題解決の重要性は誰もが認めるところだが、問題の発見という繊細なスキルはあまり培われていない。イノベーションを知っているリーダーは、斬新な解決策を生み出すためには問題の発見が必要であることを知っており、チーム全体で問題を発見する力を養っている。
スタンフォード大学の教授でビジュアル思考を唱え、デザイン思考のルーツにも関連しているロバート・マッキムは、コンピュータのプログラミングが一般的になるずっと前から、学生に「バグリスト」をつくらせていた。自分のなかの「バグ」、すなわち自分を悩ませていることを書き留めるのだ。問題に注意を払うことがイノベーションの種が育つ土壌をつくると、マッキムは知っていた。
アップルがiPhoneをつくったのは、スティーブ・ジョブズをはじめとする多くのリーダーが当時の携帯電話を「役立たずのガラクタ」と思っていたからだ。トニー・ファデルが学習機能つきのネスト・サーモスタットを開発したのは、タホ湖のスキー小屋に行くたびに、到着するまでサーモスタットを調整できずに初日は寒すぎる夜を過ごすはめになったからだ。
多くの組織には「提案箱」や「アイデアコンペ」がある。その横に「問題箱」を目立つように設置しよう。
決断を遅らせる
直感に反するが非常に効果的な戦略の一つは、新しい解決策のうちどれを進めるかについて、決断を遅らせることだ。アイデアを選択する際に効率に執着するのは、心理学者が「認知的終結」と呼ぶものを求めるからである。物事を未解決のままにしておくことは苦痛でたまらない。しかし、チームとして最善の決断の一つは、「まだ決めない」と決めることだ。
アイデアを共有したのちに、意思決定をする時間を別に設けよう。問題を「未解決」のままにすると「ツァイガルニク効果」が生じる。これはロシアの心理学者ブリューマ・ツァイガルニクにちなんで名付けられた心理的状態で、人は達成できたことより達成していないことが記憶に残りやすいというものだ。ワーキングメモリは問題を検討し続け、多く場合、よりよい解決策を生み出す。
* * *
ここで紹介した戦術は、チームが新しいものを生み出すために必要なエネルギーを呼び起こす手助けをする。日々の仕事が創造性を支えるものでなければ、大きな野心も失速するばかりだろう。
結局のところ重要なのは、リーダーが「仕事」とは何かを再定義し、同僚や従業員にも再定義させることだ。スラックのメッセージの応答にかかる時間や出席した会議の数など、効率重視の指標がすべてという環境では、従業員が持つ創造性の大きな可能性を無駄にし続けることになる。
リーダーが有効性の観点から考えるようになれば、新鮮な思考を促す豊かなインプットを世界中に探し求め、正しい答えを絞り込む前に問題に対する解決策を大量に生み出すようチームを後押しして、イノベーションを味方にできるだろう。
"5 Ways to Boost Creativity on Your Team," HBR.org, March 28, 2023.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)