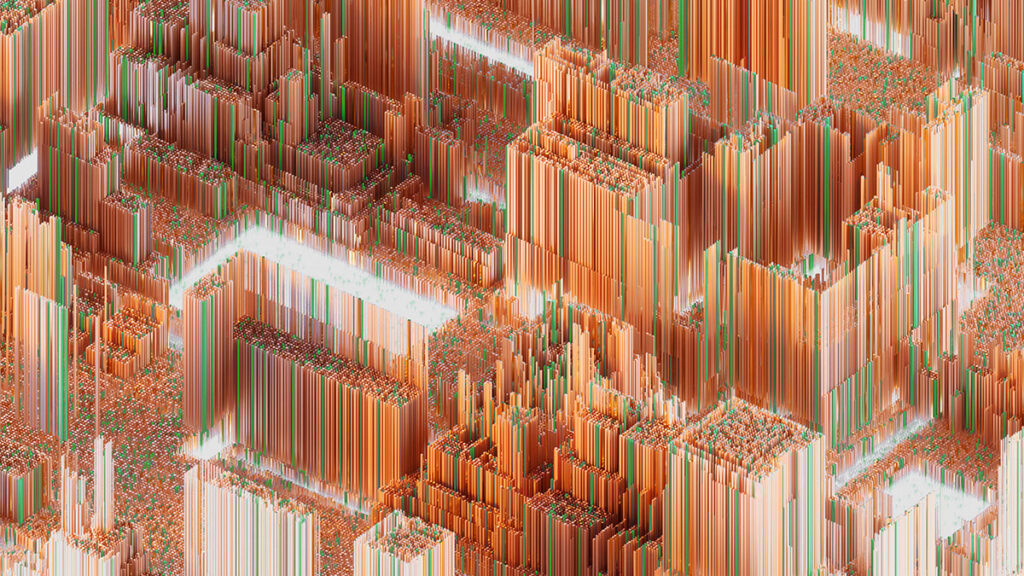
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
米国とインドがテクノロジー分野で関係を深めることのメリット
いまインドは、世界でも有数の有利な立場にある国だ。人口は世界最多の14億人余り。しかも、この30年間、力強い経済成長を続け、国民1人当たりのGDPは3.45倍に跳ね上がった。それでも、世界の中では、まだ比較的発展していない国であることも事実だ。2019年のデータによれば、インドでは6億人以上の人たちが1日当たり3.65ドル未満で生活している。
それは裏を返せば、経済成長と人々の幸福度を改善できる潜在的可能性が極めて大きいことを意味する。米国が中国に対する懸念を強めるなかで、インドは、サプライチェーンにおける調達先として、またイノベーションの拠点として、そして合弁事業のパートナーとして、中国に取って代わりうる国として魅力が高まっている。世界で最も人口の多い民主主義国であり、経済の自由化が進展しつつあり、しかも強力なテクノロジー産業を擁しているインドは、経済活動の規模をいっそう拡大させられる潜在能力を持っている。
これらの点を考えると、国家安全保障と自国のレジリエンスに関する不安によって突き動かされて、筆者らが言うところの「リグローバリゼーション」(re-globalization)を推し進めようとしている米国にとって、インドは最も重要な地政学的、経済的パートナーになる可能性を秘めた国といえるだろう。
一方、インドが世界でリーダーシップを発揮しようとするのであれば、テクノロジー産業におけるイノベーションを実行する力を強化し、ソフトウェアとハードウェアにおけるバリューチェーンの上流へ移行するための包括的な能力を高めなくてはならない。そのためには、政府レベルでも民間レベルでも、米国との関係をより緊密なものにすることが不可欠だ。
つまり、両国の状況を見ると、米国とインドはテクノロジーの分野で協働を深めていく必要がありそうだ。両国の政府当局者とビジネスリーダーたちは、両国を結ぶ「米印テクノロジー回廊」を構築するための戦略を確立しなくてはならない。それを通じて、インドをテクノロジー分野における世界のリーダーに押し上げる。米国は安定したサプライチェーンと強力なパートナーを確保できる。両国に利益をもたらす好循環を生み出すべきなのだ。
「リグローバリゼーション」とテクノロジーの「デカップリング」
今日の世界は、新しい経済関係の時代に突入しつつある。筆者らは、この新しい時代を「リグローバリゼーション」という言葉で表現している。米国が唯一の超大国として世界に君臨する時代が終わり、大国が競い合う世界が戻ってきたことに加えて、気候変動、新型コロナウイルス感染症の世界的流行、2008年の世界金融危機といった世界的な危機の影響も相まって、世界の国々は、自国経済のレジリエンスを強化し、国防、エネルギー、製造などの重要産業で他国に依存することを避け始めた。これが筆者らの言う「リグローバリゼーション」である。
「リグローバリゼーション」の時代における経済システムは、過去にまったく例のないものだ。第1次世界大戦前と、現在から遡ること過去30年間(1990年頃から2020年頃)は、世界が結びつくことが当たり前だった。自由な市場と好ましい規制環境に後押しされて、モノとサービスが容易に世界中を移動していた。一方、1950年頃から1990年頃までの冷戦時代には、米国とソ連の間の緊張が高まり、世界経済が完全に分断されていた。
いま私たちが目の当たりにしているのは、このいずれとも異なり、きわめて特殊で複雑な状況だ。世界経済が完全に結びついているわけでもなければ、完全に分断されているわけでもない。その両方の要素が混ざり合っているのである。
他方では、消費者余剰が大きく、国の存立を脅かすリスクが小さい分野(単純な消費者向け商品はその典型だ)など、一部の産業においては、グローバリゼーションが当然のこととして進展し続けている。しかし、世界経済のデカップリング(2者の間で連動していないこと)が進行している業種もある。その最たる例がテクノロジー分野だ。テクノロジープラットフォームの世界はすでに、米国と中国という2つの覇権国に属する2つの世界に分裂し始めている。
これらのことは、インドにとって何を意味するのか。基本的に、インドは米中双方と行っている大規模なビジネスを失うわけにいかない。インドの対米貿易は年間1000億ドル規模に達しているが、隣国である中国との貿易額はその2倍に上る。インドは、今後も両方の国との貿易を積極的に継続するだろう。しかし、テクノロジー分野では世界経済のデカップリングが進行しつつあり、どちらの国とのパートナーシップを優先させるかを選ばなくてはならない。
歴史に照らして考えると、インドのテクノロジー産業のエコシステムが発展を遂げるためには、ほかの国との協力が不可欠と言えそうだ。インドのテクノロジー産業が本格的に成長し始めたのは、1990年代以降のことである。これは、インドが世界規模のITアウトソーシング産業の有力プレーヤーとして台頭した時期である。1950年代と60年代にインド工科大学のテクノロジー教育が確立されたことにより、インドは高度なスキルを持ったテクノロジー人材を大量に擁していた。そうした豊富な労働力と、安価なコスト、そして英語が公用語の一つであるという言語面の環境を追い風に、インドはITサービスのアウトソーシングビジネスを目指す多国籍企業にとって、魅力的な国になっていったのである。
アウトソーシング産業の成長に後押しされて、インドではスタートアップ企業の活気あるエコシステムが形成され、多くの起業家がこのチャンスを利用して自分のビジネスを立ち上げた。2010年代に入る頃にインドは、SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)プラットフォームの分野で大きな存在感を発揮するようになっていた。ほかの国々のテクノロジー企業よりも、コストが低いことが大きな強みになったのだ。
そしていま、インドはそこからさらに一歩前進している。国内で生まれたユニコーン企業が世界市場でトップに立ち、活発にイノベーションを成し遂げるようになったのだ。今後もインドのテクノロジー産業が成長と近代化への歩みを続けるためには、インド政府が国際的なパートナーとの関わり方を戦略的に考える必要がある。
インド政府が取っている多くの行動から推察できるのは、






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









