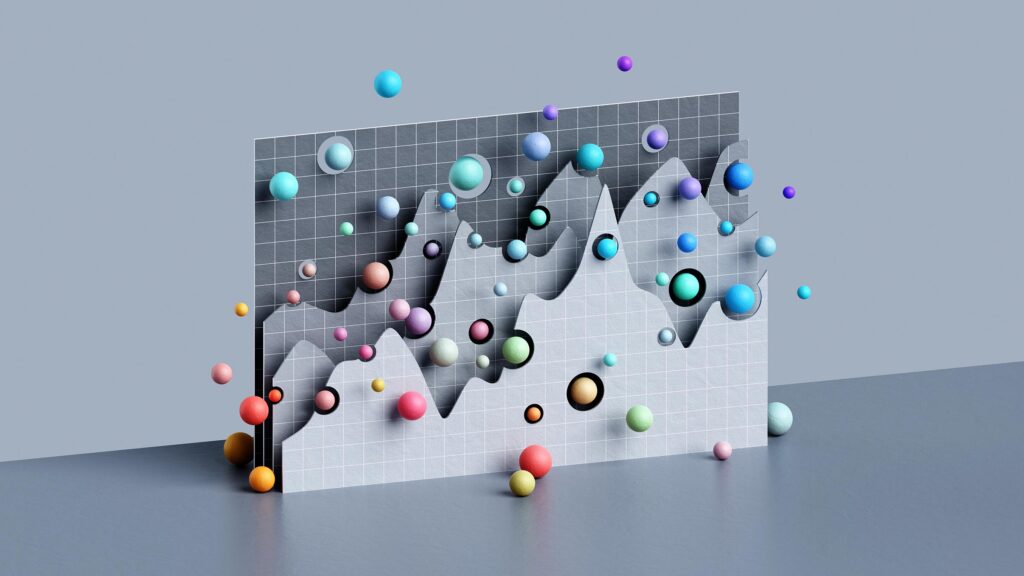
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
株式報酬が提示された際に注意すべき点
スタートアップ企業は、現金と株式を組み合わせた形で従業員に報酬を支払うことが多い。株式報酬の種類には、あらかじめ決まった価格で自社株を購入できる「ストックオプション」(自社株購入権)や、一定期間の勤務継続などを条件に株式を受け取れる「譲渡制限付き株式ユニット」(RSU)などがある。
しかし、企業から提示された採用条件(採用オファー)が株式報酬を伴う場合、入社を検討している働き手がそれを正しく評価することは容易でない。筆者らが最近行った調査では、人々が採用オファーをどう評価するのかについて、一貫したパターンがはっきりと見て取れた。つまり、働き手は、支給される株式の株数が多いほど、報酬面で優遇されていると考えていた。株式の株数が多ければ多いほど、その経済的価値に違いがなくても、現金報酬を犠牲にすることを厭わなくなる。いってみれば「株式幻想」とでも呼ぶべき状態に陥っていた。
スタートアップ企業は、株式報酬を含んだ採用オファーをする際、提供するストックオプションの株数を具体的に示すことがある。だが、現在の米国の制度において、非上場企業が発行済み株式の総数を開示することは義務づけられていない。そのため、提供される株数を知ることはできても、それが全体の何割に相当するのかまで理解している働き手はほとんどいない。
このような状況では、働き手が企業から「あなたに『10万』を支払いましょう」と言われているのに等しい。働き手には、それが10万ドルなのか、10万ユーロなのか、10万円なのか、10万元なのかがわからない。同様に、働き手が複数のスタートアップ企業から採用オファーを受けたとして、株式報酬で提供される株式の株数だけを基準にそれぞれ比較するのは、リンゴとオレンジを比べるようなものである。これでは、大事なキャリア選択時において賢明な判断が下せない。
そもそも働き手は、株式報酬の価値をどの程度、正確に評価できているのだろうか。筆者らは、その点を明らかにするために、STEM(科学、技術、工学、数学)関連の学位を持つ米国の働き手1000人以上を対象に実験を行った。彼らは、スタートアップ企業の可能性に惹きつけられやすい人々であるからだ。実際、実験参加者の15%は、過去に株式報酬を受け取った経験があった。
この実験では、参加者たちに対して、あるスタートアップ企業による架空の採用オファーを何通りか送った。現金報酬と株式報酬の割合は、オファーごとに変えたが、いずれの場合も、提供される株式が「企業の株式総数の0.5%に相当する」という注釈を入れた。
すると、参加者たちは、株式報酬の経済的価値がまったく等しいにもかかわらず、提示される株式の株数が多いほど、現金報酬が少なくても採用オファーに同意する傾向があった。たとえば、1000株の株式と引き換えに、現金報酬を1万ドル減額するオファーを受け入れた人は、全体の74%だった。一方、同じ現金報酬の1万ドル減額によって、5万株の株式を付与するとしたオファーは、数量が増えただけで価値は変わらないのに、81%の人がその提案を受け入れた。同様に、1000株の株式と引き換えに現金を3万ドル減額するオファーを受け入れる人は60%だったが、その株数が5万株に増えると、オファーを受け入れる人は64%に増加した。
筆者らは、この実験後、人々がスタートアップ企業の株式報酬についてどれほど理解しているのかを調査した。具体的には、ストックオプションの経済的価値、優先残余財産分配権(その企業が企業買収によるエグジットもしくは清算を実行する際に、どのような優先順位で株主への支払いを行うかに関わるもの)、RSUとストックオプションに対する投資のリスクレベルの違いといったことを尋ねる質問を用意した。ここに挙げた要素はすべて、株式報酬の価値を評価するうえで極めて重要なものである。
この調査結果は、現実を理解するのに役立つものであると同時に、非常に気掛かりなものであった。調査対象者の44%近くは、スタートアップ企業の株式報酬に関する質問に一つも正解できなかった。一方、全問正解できた人は、わずか5%に留まった。しかし、おそらくそれ以上に懸念すべきなのは、調査対象者たちが自身の知識レベルについて過剰な自信を持っていたことだ。「わかりません」という選択肢が用意されていたにもかかわらず、誤った解答を選択した人が大勢いた。たとえば、優先残余財産分配権が従業員の株式価値に及ぼす影響についての質問に対し、正しい解答を選べた人は18%しかおらず、わからないと認めた人は16%に留まり、66%近くの人が誤った解答を選択していた。
株式報酬に関する金融知識が不足しているにもかかわらず、やっかいなことに、多くの人々が自身の知識を過信していた。過去に株式報酬を提示された経験を持つ人たちに尋ねたところ、オファーの内容を評価するために専門家に相談したという人は25%に満たなかった。こうした状況は、人々が重要な知識を欠いていることを反映しているだけでなく、株式報酬に関わる複雑な判断を失敗した可能性も示唆している。意思決定の際、株式幻想に強く影響されたのかもしれない。
株式幻想の犠牲にならないようにするためには、以下の5つの実践が有効だ。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









