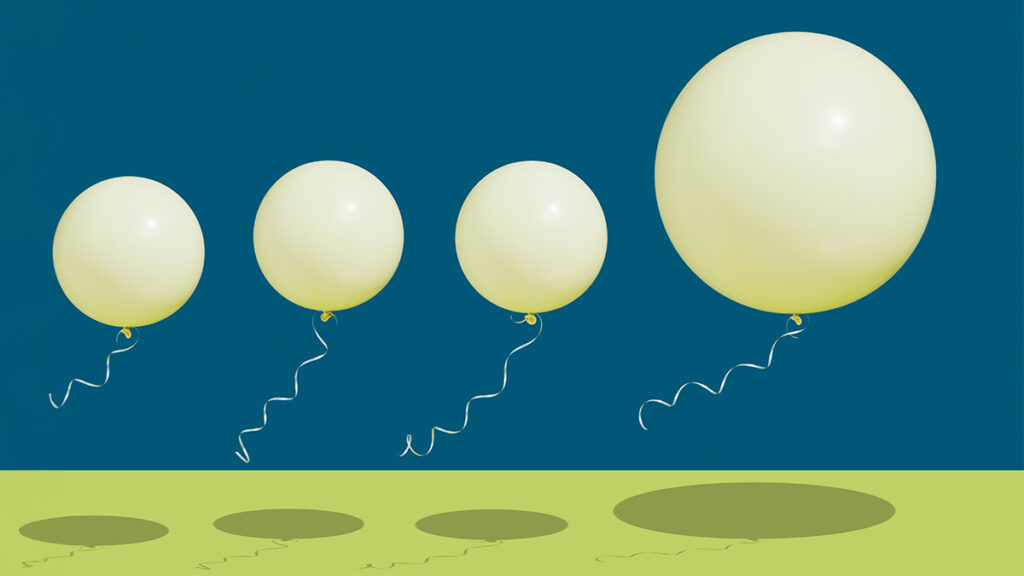
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
自分自身が問題の一因をつくったことに気づいていない
組織を変革するには、リーダーが新しい優先事項に取り組み、それまでの優先事項を誰かに委ね、チームとの関わり方を変える必要がある。しかし、筆者が30年にわたるコンサルティングと教育、そしてコーチングを通して気づいたことがある。それは、リーダーは往々にして、組織の変革をリードするために必要な行動をみずから身につけることにほとんど関心を払わず、それゆえ変革の取り組みを頓挫させかねない、ということである。
リーダーが、自分を現在の地位へと導いた行動にこだわるのは、理解できる。しかし、変革を首尾よくリードするには、自身の行動を進化させる必要があると認識し、行動することを学ばなければならない。
ピーターがCEOの職を失ったのは、彼が率いていた変革プロジェクトが結果を残せなかったからだった。ナオミは新しく雇用された会社の文化を変えようとしたが、予想よりも時間がかかったため、昇進を逃した。ユーセフは価値観のずれを感じたために、キャリア人生を捧げてきた会社を危うく辞めそうになった。
こうした芳しくない経験の背景には、それぞれに異なる事情があったと彼らは言う。ピーターは、国内市況の悪化によって、会社の収益予測が実現不可能になったと説明した。ナオミは、国内の求人市場が活況だったため、チームの離職者が予想以上に多く、文化の変革が進まなかったと考えていた。ユーセフは、自分が馴染めないのは一緒に働く若い世代のリーダーのビジネスライクな価値観のせいだと思っていた。
3人とも、自分自身が問題の一因をつくっていたことに気づいていなかった。
ピーターの場合、変革を成功させるには、組織の非効率性を改善することに専念し、収益については営業のリーダーに委ねる必要があった。この新しい仕事の分担は、途中までうまくいっていた。ところが、ある大きな取引を逃したことをきっかけに、ピーターは再び営業に介入するようになり、非効率性の問題にあまり力をそそがなくなった。その結果、会社は営業と効率性の両方の目標において後れを取ることになった。
ナオミが雇用されたのは、チームの文化を変革し、官僚的で命令されたことしかしないマインドセットを、機敏で顧客のニーズに的確に対応するマインドセットへと転換するためだった。それを達成するためには、変革に対するチームの不安に耳を傾け、不安を和らげることが不可欠であることを、彼女は理解していた。ところが離職者の増加に直面すると、忍耐力が急激に低下し、一方的に指示を出すリーダーシップに逆戻りして、むしろ離職を増やす結果となった。
ユーセフが会社のカントリーマネジャーの職を引き受けたのは、家族の近くに住むためだった。以前はグローバルな仕事をする上級職に就いていたが、給料が下がる点は気にしておらず、かえって柔軟な働き方ができることをありがたく思っていた。しかし、自分よりも若く経験も浅い新しい上司にどのような態度で接するべきかについては、よく考えたことがなかった。
行動を変えるためのプロセス
ピーターもナオミも、そしてユーセフも、自分の行動を変える必要があることに注意を払っていなかった。だが、ピーターとナオミは変革プロジェクトを首尾よく行うために自分を変える必要があったし、ユーセフは新しい役割に適応する必要があった。
行動を変えることは容易ではない。やってみた人ならば誰でもそう証言できるだろう。本稿では、必要に応じて行動を変える4つのステップとそのプロセスを概説する。筆者は自分の事業や多くのエグゼクティブ向けプログラムで、このプロセスを活用して成果を上げることができた。
ステップ1:自己認識を高める
自分の行動が他人にどう受け止められているかを認識した時、そして変化に伴い、どのような思考と感情を経験することになるかを理解した時に初めて、リーダーは自分の行動を変えられる。
ピーターは気づいていなかったのだが、取締役会が彼にコスト効率の向上に集中するよう提案したのは、彼が営業のボトルネックになっていると見抜いていたからだった。もしピーターがその点を理解していたら、営業に再び口出ししようとは思わなかったかもしれない。
職を失って、ピーターの自信は揺らいだ。彼はこれからの仕事に思いをめぐらしながら、「こんなことは二度と繰り返したくありません」と筆者に言った。「順調な時は、私の行動をどう思うか、チームにフィードバックを求めたものです。でも状況が厳しくなると、やめてしまいました。いまは忙しいからと、自分に言いわけをして。言われそうなことが無意識のうちにわかっていて、聞きたくなかったのかもしれません」
ピーターは、自己認識について2つの重要な見解を述べている。第1に、リーダーは自分がどう認識されているかについて、常にフィードバックを求める必要があり、環境任せにしてはならないということ。第2に、リーダーは、フィードバックは不必要だとか不適切だとほのめかすような思考や感情を警戒すべきということである。そうした思考に気づくことが、克服する最初のステップとなる。
ステップ2:約束する
他人が自分をどう見ているかを自覚することは、それ自体、変化を促進するきっかけになる(「変化の最強の推進力は鏡である」という格言もある)。そして、周囲に約束することで、成功の可能性が高まる。
昇進できないとわかった時、ナオミは選択を迫られた。別の仕事を探すか、このまま残って文化の変革をうまく進められるようになって、将来、昇進することを期待するか。彼女は後者を選んだ。
ナオミは、「時間を無駄にする」ことを恐れすぎたために、ていねいに耳を傾けずに解決を急いでしまったと感じていた。さらによく話を聞くためには、助けが必要だった。そこで、彼女は直属の部下たちの前で約束をした。「もっとよく話を聞くことを約束します。効果的に変化を起こすためには、それが有益だからです。ただし、皆さんの協力が必要になります」と彼女は言った。そして彼女が話を聞いていない時には、それを指摘してほしいとチームに頼んだ。
それから数週間後、ナオミが早急に問題解決に移りたいという衝動にかられた時、みんなの前で約束した記憶がたびたび抑止力になった。うっかり、声を荒げて解決策を指示してしまった時、チームのメンバーはニヤリと笑ってこう言った。「話を聞くと言いましたよね」






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









