
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
柔軟な働き方はウェルビーイングを損ない、出社義務付けは生産性を低下させる
ギャラップの最新調査によると、柔軟な働き方は、従業員のウェルビーイングに影響を与えているという。世界140カ国以上で行われた同社の「グローバル職場環境調査」において、勤務時間のすべてをリモートワークにしているか、一部をリモートワーク(ハイブリッド勤務)にしている従業員は、100%出社勤務している従業員よりもストレスや怒りを感じていた。
ギャラップは、フォーチュン500の企業の人事リーダー(その会社の福利厚生の責任者であることが多い)にも、仕事が従業員のメンタルヘルスに及ぼす影響について尋ねた。すると、仕事が従業員のメンタルヘルスにポジティブな影響を与えていると答えたのは、最も柔軟な働き方を認めている(出社義務がある日はゼロ)最高人事責任者(CHRO)の27%に留まり、週1~2日出社させているCHROでは29%、週3日では37%、週4~5日出社させているリーダーでは47%だった。
一方、リモート勤務やハイブリッド勤務の従業員は、完全出社勤務の従業員よりも、一貫して仕事に対する熱意が高く、それに応じて生産性や成果も高かった。フォーチュン500の人事リーダーも同意見だ。過去1年間に生産性が総じて上昇したと答えたのは、最も柔軟な働き方を認めている人事リーダーで41%、週1~2日出社を求める人事リーダーで33%、週3日出社を求める人事リーダーで32%、週4~5日出社させている人事リーダーでは32%だった。
これは、企業リーダーに難しい問題を突きつけている。完全に柔軟な働き方は、従業員のウェルビーイングを危険にさらすおそれがあるが、完全出社勤務を義務づけると仕事への熱意や生産性が低下するおそれがあるのだ。
どこで働くのであれ、従業員のウェルビーイングと生産性の両方を高めるため、組織には何ができるのか。
従業員がバランスに応じた生活をできるようにする
柔軟な働き方についてリーダーにありがちな誤解は、「従業員は日中、仕事とプライベートが混在する状況を望んでいる」というものだ。ギャラップは米国の代表的な労働者のサンプルに次のような質問をした。
「あなたにとっての最高の暮らし方として、月曜日から金曜日まで次のどちらの働き方を希望しますか」
1. 勤務時間は午前9時~午後5時で、仕事の前または後にプライベートな活動ができる仕事(ギャラップはこのような従業員を、仕事とプライベートを分けている人「スプリッター」と呼ぶ)。
2. 一日の間に仕事とプライベートを行き来する仕事(ギャラップではこのような従業員を、仕事とプライベートをミックスしている人「ブレンダー」と呼ぶ)。
すると、予想外の結果が出た。米国の労働者の50%がスプリッターに、50%がブレンダーになりたいと答えたのだ。ただ、職種によって結果は多少異なる。スプリッター希望者はホワイトカラーでは45%、ブルーカラーでは62%だったのに対し、ブレンダー希望者は、ホワイトカラーでは55%、ブルーカラーでは28%だった。大企業のCHROを対象とした調査では、人事リーダーがスプリッター希望者を少なく見積もっていることがわかった。
これは非常に重要である。なぜなら、従業員が自分の望む働き方をしていない場合(つまりスプリッター希望者がブレンダー的働き方を求められる場合、またはその逆)、従業員のエンゲージメントは低下し、燃え尽きたと訴える可能性が高くなり、転職を希望したり、積極的に転職先を探したりする可能性が高くなるからだ。
好ましい働き方が従業員に与えるインパクト
柔軟な働き方については、2つの重要な希望があることがわかった。スプリッターは、午前9時~午後5時は仕事に集中し、その前または後にプライベートな活動をすることを好む。ブレンダーは、一日を通じて仕事とプライベートをミックスすることを好む。
従業員の勤務スケジュールが希望する働き方と一致している時、「非常に頻繁に/いつも燃え尽きを感じる」人はわずか22%で、仕事に熱意を感じるのは35%、転職を考えているか積極的に転職先を探しているのは46%だった。他方、勤務スケジュールが希望する働き方と一致していない場合、「非常に頻繁に/いつも燃え尽きを感じる」人は35%、仕事に熱意を感じる人はわずか26%で、転職を考えているか積極的に転職先を探している人は60%にも達した。

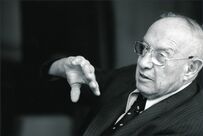




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









