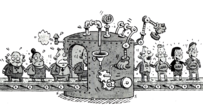手掛かりとなる定性データを分析する
組織で本当に起きていることを明らかにするためには、さらに洗練されたツールが必要とされる場合もある。筆者らは、本稿で取り上げているクライアント企業のために、マサチューセッツ工科大学(MIT)上級講師のドナルド・サルが共同創設したカルチャーXと提携した。カルチャーXは、AI(人工知能)を利用して定性データを分析し、リーダーが従業員に取ってほしいと望んでいる行動ではなく、従業員が実際に取っている行動を明らかにする。
大きな組織には必ず、定性データの中に手掛かりが存在する。職場の働きやすさなどについてのクチコミレビューサイトへの書き込みや、従業員エンゲージメント調査に寄せられるコメント、360度評価への返答、タウンホールミーティング(対話集会)でのアンケートへの回答などである。
カルチャーXが行った分析の結果には、目を見張るものがあった。本稿で紹介しているクライアント企業は、アジリティ重視の文化を育もうとしてきた。そして実際、従業員のコメントによれば、ここ数年の間に、この点で大きな改善が見られていた。しかし、同社のアジリティは依然として業界水準よりも劣っていた。その事実を知った同社のリーダーたちは驚いた。
「いまだに保守的だ」と、ある人は記した。「会社の規模が大きすぎる」と、別の人は記した。「正社員や契約社員の数に対して、マネジャーの数が多すぎる」と指摘した人もいた。「どのプロジェクトにも、3人の別々の上司がいる」
この分析を通じて、同社のリーダーたちは、自社でうまくいっていることとうまくいっていないことについての理解が深まり、それをもとにさらなる対策を打ち出すことができた。
目に見えないパターンをあぶり出す
このクライアント企業で筆者らが観察したイノベーション関連の会議が浮き彫りにしたのは、この会社における目に見えない行動パターンだった。これまで見えていなかったものを明らかにする手立てとしては、どのような方法があるだろうか。その一つの方法は、絵を描くことだ。
「システム・サイコダイナミクス」と呼ばれる心理学分野の権威であるスーザン・ロングによれば、絵を描くことは、心理学で言う「移行対象」のような役割を果たし、難しい会話を促進し、夢や物思いだけでなく「不安を表現する手立て」にもなりうる。そして、絵を描くことにより「『驚くべき事実』に光が当たり、仮説的推論が促される」という。そうした絵は、組織文化の細部をあぶり出せる可能性がある。私たちは概して、複雑で微妙な問題を表現する言葉が見出せなくても、それを絵で表現することはできるからだ。
筆者らは、クライアント企業で変革への取り組みの最前線に立っていた幹部数人を選び、この会社で働くとはどういうことかを絵に描いて表現するよう求めた(大雑把な絵でかまわないと伝えた)。そして、その絵の内容について短い文章に記してもらい、その後さらに90分間、掘り下げて話を聞いた。
とりわけ強烈だった絵の一つは、「複数の光線を発する灯台」の絵だった。一つの灯台が周囲のあらゆる方向に光を放っていたのだ。灯台のまわりの海には、さまざまな小舟が多く漂っていた。説明によれば、一つひとつの光線は、この会社のリーダー層が認識している戦略上の重要課題を表現している。そして、周りの海上の小舟、つまりこの会社で働く人たちは、それぞれ前に進んでいるつもりでいるが、どこへ向かって進んでいるかは、どの光線を指針にするかによってまちまちだ。こうした状況がもたらす結果として、社内に強いフラストレーションが生まれていたのだ。
この会社のリーダーたちは、従業員に向けてメッセージを発してはいたけれど、リーダー層の内部での調整が不十分で、しばしば混乱を生み出していたのである。しかも、リーダー層の面々はそのことに気づいていなかった。筆者らは、この灯台の絵を幹部会議で見せた。すると、それをきっかけに、同社のリーダーたちは、社内のコミュニケーションをより戦略的に、そしてより明確な意図を持って行うための方法を議論し始めた。その中で、社内コミュニケーションを担当するリーダーを決めることになった。
絵を描くといっても、文字どおりの意味で「絵画」を描く必要はない。ストーリーの形で表現してもよいし、頭の中でイメージを描くだけでもよい。そのような方法でも、興味深い思考を表面に引き出せる場合があるのだ。
「私は、アートが得意なタイプではありません」と、筆者らが話を聞いた人物の一人は述べた。「でも、頭に浮かんだことをお話しさせてください」。この人物は、米国の農場で飼育されている七面鳥になった気分だと語った。1年間のほとんどの期間、人生は順風満帆に思えていた。食べる物もたっぷり与えられていたし、よくほめてもらえた。ところが、感謝祭の日が近づくと、斧を握りしめた農場主がやって来るような不安があったのだ。このストーリーは、大企業の内部でイノベーションに取り組む人たちによく見られる不安を浮き彫りにするものだといえる。このような不安が存在することが明らかになれば、その不安に対処することが可能になる。
導き出せる教訓
それまで見えていなかった障壁を明らかにすることにより、変革の取り組みを加速させられる。本稿で紹介した手法は、比較的実践しやすくて、しかもただちに充実した発見をもたらせるものだ。筆者らは、この手法を実践することにより、3つの教訓を得ることができた。
複数のツールを用いる
よい医師がさまざまなツールを活用して患者を診断するのと同じように、組織の問題を診断する際も、大きな成果を上げたければ、さまざまなツールを用いて、できる限り完全な像を描き出すよう努めるべきだ。本稿で紹介してきたクライアント企業は、筆者らの助言の下、さらに旧来型のアンケート調査やリーダー層への聞き取り調査も実施した。そうしたさまざまな方法による分析結果を俯瞰して、それらに共通するパターンを探すことにより、深い洞察を得ることができた。
データを参考に考える
よく知られているように、文化は時としてとらえどころのないテーマだ。その点、カルチャーXの分析には、具体的な数字を使って文化を検討できるという強みがある。従業員エンゲージメントの調査にも同じような利点がある。しかし、ここで意図的に「参考に」という言葉を用いたことに留意してほしい。文化には繊細な側面があり、文化を論じる際に、過度にデータに依存することは好ましくない。データは、あくまでもほかの定性的な知見を補完するものとして扱うべきだ。この点を誤らなければ、目につきにくい現象に光を当てることができるだろう。
アウトサイダーを関わらせる
ある集団のメンバーが無意識のうちに、見えない行動パターンに従っている場合、その集団自身でそのパターンを観察することは不可能に等しい。よく言われるように、魚は自分たちが泳いでいる水を観察できないのだ。と言っても、筆者らにコンサルティングを依頼するよう宣伝したいわけではない。たいていの組織には、すでに内部に十分な文化的多様性が存在していて、言わば「内部のアウトサイダー」の力を借りることが可能だ。
たとえば、自社のR&D部門にマーケティング部門を観察させたり、日本支社にブラジル支社を観察させたり、引退したリーダーたちに次世代のリーダーたちを評価させたりすればよい。ここで忘れてはならないのは、それまで目に見えていなかったものを表面に引っ張り出すには、ある程度のスペースと距離が必要だということだ。
* * *
変革を妨げる要因としては、時間やトレーニング、金銭的なインセンティブの不足が挙げられることが多い。こうした指摘はすべて、間違ってはいないのかもしれない。しかし、ほとんどのケースで、そこにはさらに根深い要因がある。
いま足りていないのは、時間なのか、それとも関心なのか。恥や恐怖の感覚があるのか。トレーニングの機会が十分に活用されていないのではないか。もしそのような実態があるとすれば、理由は何か。
変革を妨げている真の障壁を理解しない限り、莫大な時間と資金を無駄にしたり、事態をいっそう悪化させるリスクを冒したりすることになりかねない。そして、より深く掘り下げて検討するほど、真の障壁を見出せる可能性は大きくなる。障壁が明らかになったら、その問題にエネルギーを集中させよう。そうすれば、進歩のペースが大幅に加速するだろう。時には、目を見張るほど進歩することもある。
"What's Derailing Your Company's Transformation?" HBR.org, October 18, 2023.








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)