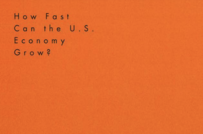情報の非対称性を味方につけよ
企業の目利き力はどのようにして高められるのだろうか。経営学でよく主張されるのは、経験による学習である。このカプロン=シェンの実証研究でも、買収する側の企業が過去に(同じ業界で行った)買収案件の数が分析に使われている。
日本においてM&Aの目利き力のある経営者の筆頭は、間違いなく日本電産の永守重信氏だろう。同氏は日本の経営者には珍しく、多くの企業買収を次々と実現して日本電産の価値を高め、成功して来た。しかし、そのアプローチは「変わっている」と言われることも多い。なぜなら永守氏は、あえて規模が小さく、業績も悪い会社を狙って長い間買収を続けてきたことで有名だからだ。
しかし、ここまでの議論を踏まえれば、永守氏の戦略はカプロン=シェンのロジックと極めて整合的なことがおわかりだろう。通常、小さくて業績の悪い会社は、私的情報を多く持っている可能性が高く、普通の会社は買ってはいけない案件だ。しかし、同社はモーター製造関連業界での企業買収を繰り返しているから、業界内での目利き力が圧倒的に高い。そして、永守氏自身が必ず買収対象企業の現場に行って、外からは見えない社風などの私的情報をつかむプロセスを繰り返し、その経験値を上げている(※2)。永守氏は、その力を持って私的情報を持つ企業の「本当の価値」を見抜き、他社を出し抜いているのだ。
このように情報の非対称性はアドバース・セレクション問題を引き起こすというマイナスの側面も大きいが、そこを乗り切れる経営者・企業には大きなチャンスでもある。先に述べたように、これからもグローバル化、IT化など様々な理由で、情報の非対称性が高い時代は続く。この時代に情報の非対称を味方につけられるか否かが、ビジネスの成否を分ける一因になるといえるのだろう。
【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】
情報の経済学
エージェンシー理論
組織の記憶の理論
【著作紹介】
世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。
その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。
本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。
お買い求めはこちら
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※1 同様の含意を持つ研究に、Laamanen, T. 2007. “On The Role of Acquisition Premium in Acqui-sition Research,” Strategic Management Journal, Vol.28, pp.1359-1369 がある。同研究は1989~1999年の米ハイテク・セクターにおける458の企業買収データを使った統計分析より、被買収企業のR&D/企業価値比率(通常、R&D投資額が多い企業ほど実態が外部から見えにくいので、これは情報の非対称性の代理変数として使われる)が高い企業が買収される時ほど、その企業に高い買収プレミアムが払われる、という結果を示している。情報の非対称性が高い企業を買収できる企業は、その内部の目利きができてライバルを出し抜いてその企業の本当の価値がわかっているので、その分高額なプレミアムを払うというロジックである。
※2 『日経ヴェリタス』2015年1月11日号。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)