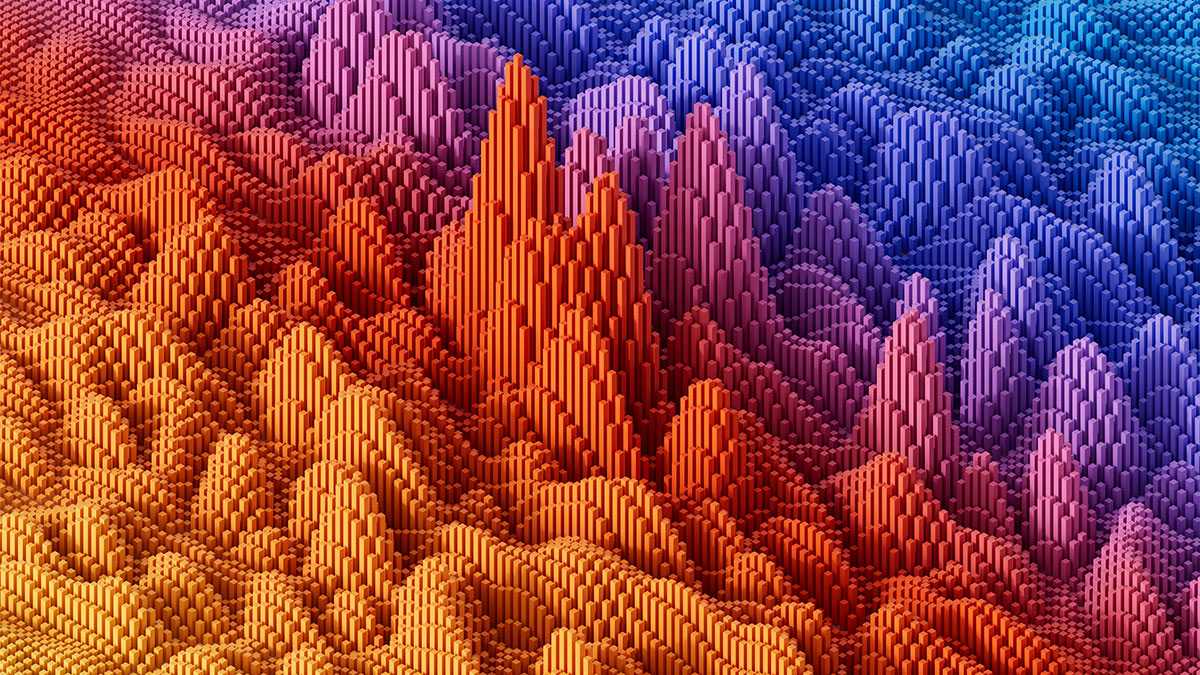
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
これまで融資が難しかった層の債務返済能力を正確に評価する方法
融資は、貧困から抜け出し、健康と教育レベルを改善させ、さらには人生の満足度を向上させる手立てになりうる。問題は、十分に融資を受けられる人ばかりではないということだ。
途上国では、1億3000万の企業と14億の個人が融資を利用できない状態にある。融資を受けられる場合も、ルールが過度に複雑だったり、極めて高い金利を支払わなくてはならなかったりする。マイクロファイナンスでは、金利が25%~100%以上に達することもあるのだ。また、研究によると、女性の借り手は男性よりも高い金利を負担しなくてはならないケースが多いという。ヤミ市場で資金を調達しようとすれば、金利はもっと高い場合もある。
このような状況が生まれていることには理由がある。融資を受ける機会が乏しい社会では、貧困層に融資を行うことが難しい。貧困層の借り手は、自然災害や病気などのショックに見舞われた場合、ひときわ大きなダメージを被りやすい。しかも、融資を受けるに当たって、給与の記録や銀行の口座情報、信用履歴などの書類を提出できない場合がある。その結果、判断材料が十分に集まらず、リスクの大きい借り手と、リスクの小さい借り手を見極めることが容易でないのだ。
要するに、このような市場で融資を行うには、大きなコストが伴い、必要とされる作業がとりわけ複雑なため、融資が行われにくいのだ。しかし、裏を返せば、そうしたコストを引き下げることができれば、人々がもっと融資を受けやすくなるだろう。
融資のコストを引き下げるための一つの道筋は、融資審査に関わるものだ。たとえば、テクノロジーと自動化技術を活用して、昔ながらの「専門家主導の審査」のあり方に変更を加える試みがなされている。それぞれの融資希望者の資産と債務を対面によって調査するのではなく、デジタルツール、オンラインでの面談、リモート形式で行う心理測定検査などを通じて、コストを抑えつつ、十分な情報を獲得しようというのだ。
このアプローチは、先進国において資産家など、他に似たような人がいない顧客を対象とする場合に、民間の金融機関が用いている手法に近い。新興国市場では、一部のマイクロファイナンス機関がこの手法を中小企業向けの融資で用いている。
あるいは、借り手のデータをデジタル化して、「デフォルトモデルに基づいた融資審査」の適用可能範囲を広げる取り組みも行われている。この手法は、膨大な量のデータを用いて、過去の借り手の属性と債務不履行の履歴の間の相関関係を割り出し、その相関関係をもとに、新しい融資希望者ごとに融資の可否を審査するというものだ。
これは、米国など、豊富なデータが手に入る国の個人向け融資を手掛ける金融機関によって以前から用いられてきた手法だが、フィンテックの活用により、新興国市場でも借り手のデータのデジタル化が始まっている。それにより、その人物がどれくらい安定的に収入を得ているのかを明らかにしようというのだ。活用するデータとしては、たとえば携帯電話所有者の通話時間数のデータなどが挙げられる。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









