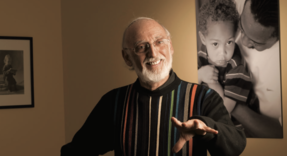-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
結果の公正さのみならず
プロセスの公正さも重要
ロンドンの警察官がある女性に、Uターン違反のかどで切符を切った。その女性が、どこにもUターン禁止の標識がなかったと抗議すると、この警官は、折れ曲がっていて道路からは見えにくい標識を指差した。怒った女性は、裁判に訴えることを決心した。
ついに、審問の日が訪れた。彼女は異議申し立てすることを、一日千秋の思いで待っていた。彼女がその時の事情を陳述し始めようとしたところ、判事は彼女の話をさえぎり、即座に彼女の言い分を認める裁定を下した。
彼女はどのように感じただろうか。自分が正しいと認められた。あるいは勝った。あるいは満足感に浸った。いずれも否である。実は、彼女はいらいらし、ひどくみじめな気持ちを感じたのだった。
「私は、公正さとは何かを問い質したかったのに、判事は、何が起こったのか、私に説明させてくれませんでした」と、彼女は不満をこぼした。言い換えれば、結果には満足だったが、そこに至るプロセスが気に入らなかったのである。
経済学者たちは、理論上、人々は効用を最大化するために、たいていおのれの利益を合理的に計算して行動すると仮定する。すなわち、経済学者は、人々は単に結果を重視すると仮定しているといえる。
この仮定は、マネジメントの理論や実践に過剰に当てはめられてきた。たとえば、経営者が従業員の行動を管理したり動機づけたりする手法、たとえば報奨制度や組織構造などがその好例である。
しかし、この仮定について再考すべきである。現実において、この仮定が常に真実であるとは限らないと、もはやだれもが知っているからだ。もちろん結果も気にするが、ロンドンの女性のように、その結果に至るプロセスについてもまた、気にする。
すなわち、人はたとえ最終的に退けられたにしても、自分の言い分が考慮されたのかどうかを知りたいのだ。結果も問題だが、その結果を生み出すプロセスの公平さも、等しく問題なのである。