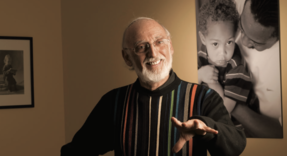-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
トレーニングだけでは「学習する組織」へと進化できない
組織を学習へと導くには、具体的なビジョンを示し、社員たちに適正な報奨を与え、社員教育を充実させれば事足りる──。経営者はこのように考えているかもしれない。この想定は、間違っているばかりか、競争の激化、技術の進歩、嗜好の変化という現実の前では、危険ですらある。
これらの傾向が強まるなか、それと立ち向かう企業組織には、これまでになく組織学習の必要性が高まっている。すなわち、各企業が「学習する組織」に自己変革するしか道はない。
こう申し上げたところで、取り立てて目新しいアイデアではない。1990年代には、マサチューセッツ工科大学のピーター M. センゲが著した『最強組織の法則』[注1]をはじめ、膨大な数の出版物、数々のワークショップやウェブサイトに刺激されて、この考え方が一世を風靡した。そして、知識(ナレッジ)の創造、獲得、移転に長けた人材によって組織を固めるという考え方に、産業界は傾倒していった。
このような人材は、寛容さを醸成する、オープンな議論を促す、全体論的で体系的に思考するといった点で、まさしく組織に貢献する存在だった。また、学習する組織を構築できれば、不測の事態にも競合他社よりも速く対応できると考えられた。いまも我々の周りでは、予測できない出来事が日常茶飯事のごとく起こっている。ところが、学習する組織というアイデアは、いまなお理想のままである。
これまで、その道程の障害となってきた要因が3つある。第1に、学習する組織に関する初期の議論には、具体的な処方箋というよりも、よりよき世界への賛歌と呼ぶべきものがまことに多かった。そのような議論は、森(総論)ばかり強調して、木(各論)についてはほとんど無頓着だった。その結果、それに付随する提案も、ふたを開けてみれば、実現困難な代物だった。つまり、いかに推し進めようとしても、たどるべき道筋を見つけられなかったのである。
第2は、学習する組織という概念は、CEOや経営幹部を想定したもので、範囲は狭いが重大な組織業務の舞台となる現場向けのものではなかったことである。これら現場の管理職たちには、自分が率いるチームの学習が会社全体にどのように貢献するのか、評価しようがなかった。
第3に、評価基準やそのための手法も存在しなかった。その結果、まだ道半ばにもかかわらず成功を宣言したり、分析や相対評価が怠ったまま「学習する組織へと成長しつつある」と言い張ったりする企業が出てきた。
これらの欠点を正すため、本稿では、組織学習の成熟度を評価する包括的かつ具体的な診断ツールについて紹介する。このツールは我々がゼロから開発したもので、ある部課、プロジェクトの学習の実態を評価するものである。重要な仕事をメンバー間で分担したり、重複して担当したりする組織であれば、その規模は問わない。