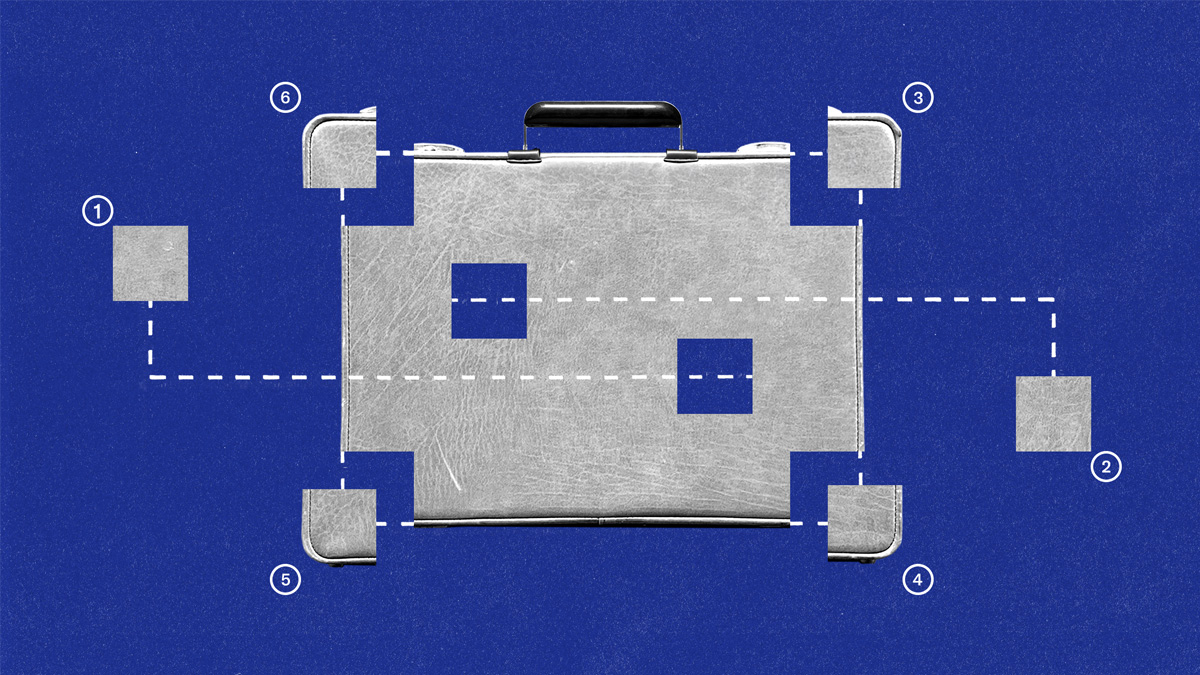
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
仕事のあり方を変える「ジョブ・デコンストラクション」
現代の職場では、従来型の「仕事」、つまり特定の業務を行うことで固定された職種の重要性が薄れつつある。新型コロナウイルスによるパンデミック後の労働力のシフトや世界的な不透明感の高まりによる影響、そして急速に技術が進歩する中で、組織はより柔軟な働き方に軸足を移しつつある。このシフトを象徴するのが、従業員に固定的な役割を割り当てるのではなく、従業員のスキルと具体的なタスクやプロジェクトを動的にマッチングさせる新しい組織のあり方「ジョブ・デコンストラクション」(仕事の再構築)だ。
ジョブ・デコンストラクションとは、仕事を再設計するための幅広いアプローチであり、連続的な流れの中で表れる。ザッポスなどの企業は、さらに急進的なアプローチを取って、従業員が一時的に担う機能的な役割のみに基づき組織を構成しており、従来の肩書きや職層は完全に撤廃されている。組織構造を完全に見直す、大胆なアプローチだ。
急進的なアプローチと従来的なアプローチの中間には、ユニリーバなどが採用するハイブリッドモデルがある。ユニリーバの「Uワーク」プログラムは、選抜された従業員が正社員としての福利厚生を100%維持しつつ、固定的な職位に就くことなく、さまざまなプロジェクトを柔軟に担当できる仕組みだ。
これにより同社は、組織に社会的に溶け込んでいて、社内手続きにもなじみがあり、敏速に動くことができる人材を社内に確保でき、社外のフリーランサーを使うことから生じるコストや統合上の問題の発生を抑えることができる。
最も一般的で、変化という点でさほど急進的でないのは、正社員にプラスアルファとして、デコンストラクト(再構築)された仕事を担当する機会を提供する企業だ。シンガポールのDBS銀行や、電気機器・産業機器メーカーのシュナイダーエレクトリック、そして米連邦政府の社内人材移動プログラムがよい例で、従業員は従来的な職務と並行して、異なる部門の副プロジェクトを引き受けることができる。こうした仕組みは、従業員がメインのポジションを維持しつつ、能力開発やネットワーク拡大、キャリアアップを実現することを可能にする。
ジョブ・デコンストラクションは、部門を超えた人材配置を可能にする画期的な組織原理として浮上してきたが、その実施に課題がないわけではない。こうした課題をよりよく理解するために、筆者らは最近の調査で、組織が仕事を再構築する時に生じる緊張関係を探った。具体的には、ジョブ・デコンストラクションを世界的なスケールで試行している組織と協働してきた研究者およびコンサルタントとしての経験に基づき、さまざまなフォーチュン500と公的機関におけるジョブ・デコンストラクションの取り組みを記録した報告書やケーススタディを分析した。
再構築された仕事における緊張
筆者らは、再構築された仕事に内在する3つの大きな緊張を明らかにした。この緊張を放置すれば、従業員を遠ざけ、ジョブ・デコンストラクションによる恩恵も得られなくなる危険性がある。
自律性と統制のバランス
ジョブ・デコンストラクション・プログラムは、従業員が自分のスキルや関心に合ったタスクを選べるようにすることで、従業員のエンパワーメントを図る設計になっているが、これはマネジャーの権限を脅かすものだ。マネジャーが人材を囲い込んだり、その他の形でジョブ・デコンストラクションに抵抗したりする事例が数多く見られた。こうした態度は、プログラムの有効性を著しく傷つける。
たとえば米政府のオープン・オポチュニティーズ・イニシアティブでは、同職員がサイドプロジェクトという形で再構築された仕事を担当しようとすると、毎回のようにマネジャーが反対した。メインの仕事があるのにサイドプロジェクトを担当する余裕があるのかと懸念を示したり、他の部門と仕事をしたがる理由に疑いの目を向けたりしたのだ。
ある技術コンサルティング会社でジョブ・デコンストラクションを試みているリーダーと話をしたところ、以下のようなことが明らかになった。再構築された仕事を担当するかどうかは、従業員の自発的かつ主導のものとして提示されるが、徐々に従業員の参加は(仕事への)熱意を証明する方法として利用されることが増え、人事考課に織り込まれることが多いのだという。これは従業員の自律性と期待される成果との間に緊張を生じさせる。参加は従業員の自発性に任されるはずだが、事実上、昇進の条件になっているのだ。それでも多くのマネジャーは、従業員が従来の職務に完全に集中することを期待する。また、再構築された仕事に関心のある従業員は、通常の就業時間中ではなく、個人的な時間に新しい仕事をこなすことを強いられるため、本来、このシステムが促進を謳っているはずの自律性そのものを損なっている。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









