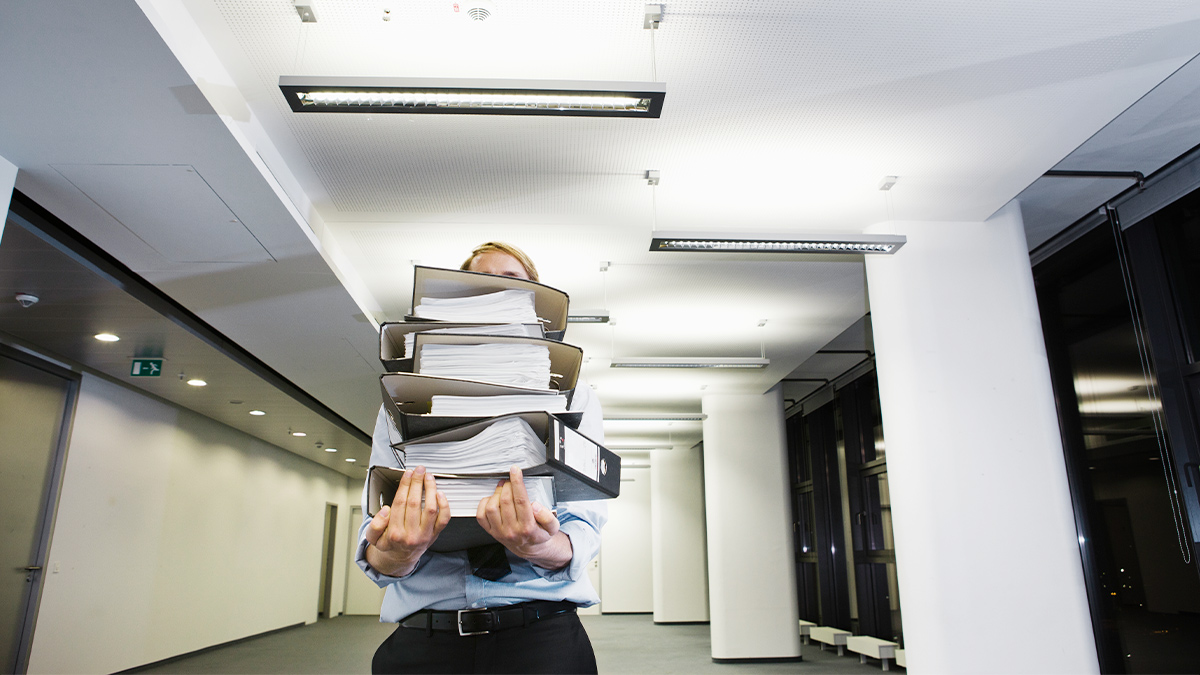
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
人材を失いたくなければ、リーダーはパワーの使い方を熟考せよ
過去10年間のほぼすべての時期にわたって、従業員は職場でかつてないほど多大な影響力を有してきた。労働市場の逼迫、失業率の記録的な低さ、職場の柔軟性を重視する新たな潮流といった要因が相まって、組織は人材獲得のために給与や福利厚生、労働環境の向上に取り組まざるをえなくなった。
だが、そうした時代は終わりつつあり、職場の主導権は再び雇用主側に戻ろうとしている。失業率が4%程度で安定し、求人件数が減少する中、一部のリーダーはこのチャンスに乗じて、柔軟な働き方に関する規定を見直したり、DEIの取り組みを縮小したり、従業員のウェルビーイングプログラムを削減したりしている。
しかし、過去を振り返れば、雇用主が強気の態度を取りすぎると、離職率の高さや企業イメージの低下、長期的な業績悪化などの代償を払わされることになるのは明白だ。主導権を取り戻したいまだからこそ、リーダーはパワーの使い方を考える必要がある。
信頼とエンゲージメントを強化して、長期的成功を収める方向に進むのか、それとも、目先の効率性を追い求める誘惑に負けて、結局はパフォーマンスが静かに低下していく道をたどるのか。雇用主と従業員の間を主導権が行き来する繰り返しを避ける最善の方法は、誘惑を直視し、取るべき代替手段を理解することにある。
本稿では、有利な立場にある雇用主が陥りやすい3つの誘惑と、それに代わって取るべき対応策を紹介しよう。
誘惑1:マイクロマネジメント、過剰な監視、杓子定規の管理
主導権を手にしたと実感した雇用主に最初に表れる兆候の一つが、マイクロマネジメントと監視体制の強化だ。リモートワークやハイブリッド勤務が数年続いた後、企業は従業員をオフィスに呼び戻しつつあるが、その際に厳格な監視ツールを使ったり、杓子定規の出社ルールを課したりするケースが多い。
たとえば、アマゾン・ドットコムの倉庫では従業員の動きを秒単位で追跡する監視システムが長らく批判されてきたが、現在ではそれがオフィス部門にも進出し、キーボード操作を追跡したり、作業時間を記録したりするソフトウェアの導入が進んでいる。ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなどの金融機関でも厳格な出社義務が課され、一部ではルールの遵守を確認するために、社員証による入退室履歴の管理も行われている。こうした動きの根底にあるのは、「出社する人数が多いほど、責任感が強まり、協働が進む」という考え方だ。
しかし、現実はそれほど単純ではない。スタンフォード大学の経済学者ニコラス・ブルームは、体系化されたハイブリッド勤務を行うと生産性は最大13%向上し、離職率は半減することを発見した。また、多くのリーダーが前提としている「求人件数が減っているから、従業員は指示に従うだろう」という考えも誤りで、実際には、その代償は深刻だ。
従業員が「信頼されている」ではなく「監視されている」と感じると、エンゲージメントは急落する。仕事に集中することよりも、監視の目から逃れることに意識が向いてしまうためだ。過剰な監視は、高いパフォーマンスを上げようという意欲を高めるどころか、恐怖と反発の文化を生み出す。そして、ひとたび市場環境が変化すれば、長年、不信感を抱えてきた従業員はそれを忘れることなく、管理ではなくエンパワーを重視する企業へと去っていく。
代わりにすべきこと
全員を満足させるのは不可能だが、杓子定規の出社義務は、特にリモートワークで高い成果を上げてきた有能な人材を疎外してしまうおそれがある。優れたリーダーは、反射的に管理強化に走ることなく、パフォーマンスを引き出す環境づくりに取り組んでいる。
リーダーは、従業員の一日をあらゆる面で管理したいという衝動に抗って、行動ではなく、「成果」に注目すべきだ。目指すべきは、監視ではなく、本人の自律性によって責任が果たされる状態である。
自律性をごほうびではなく、デフォルトとする
マイクロマネジメントの前提には、「従業員は、自分には自律性を与えられるだけの価値があると証明しなければならない」という考え方がある。その発想を逆転させ、誰もが初めから自律性を付与されており、必要に迫られた場合にのみ、それが無効になる、と考えよう。
組織構造も、意思決定ができるだけ現場に近いレベルで行われるよう設計すべきだ。もしも判断すべき課題があまりに頻繁に上層部にまで上がってくるのであれば、それは従業員ではなく、組織構造に欠陥がある。
自律性の高い従業員ほど生産性が高く、エンゲージメントも高くなること、また、自律性の水準が高い企業は、収益性も向上していることが研究によって明らかになっている。
行動ではなく、インパクトに基づく業績評価指標を再設計する
在席時間に基づく指標や、マウスの動きを追跡する監視ツールを廃止し、組織の価値観に沿った形で責任を担う枠組みに切り替えよう。各チームが自分たちの進捗を追跡し、成果を報告し、パフォーマンスの基準をみずから設定するようなシステムを構築すれば、「その場にいるだけ」で評価されることがなくなり、実際に成果につながる業務が明確化される。
たとえば、筆者らのクライアントのある多国籍テック企業では、毎日の義務とされていたスタンドアップミーティングを廃止し、チームごとにその週の「成果トップ3」をダッシュボードで視覚化する方式に切り替えた。これにより、オンラインの滞在時間や参加した会議の数ではなく、主要目標に関する実際の進捗を可視化できる。その結果、マネジャーは業務の監視に費やす時間を減らし、業務の障害を取り除くことに注力できるようになった。また、高い成果を上げている従業員が自身の貢献度をより明確に把握し、周囲をサポートできるようになった。
リモートワークを廃止する前に、無駄な会議を廃止する
リーダーがオフィス回帰を望む一因として、オンライン会議が非効率で、協働作業を行いにくいと感じていることがある。だが、会議に関する文化が劣悪であれば、場所にかかわらず、協働の足を引っ張る要因となる。
まず、進捗状況の報告の大半を、非同期チャネルに移行させる。そして、定例会議をAIを活用したアジャイル型のミーティング、つまり、単に「椅子に座っているだけの会議」ではなく、特定のプロジェクト用に設計された、時間制限つきで、成果重視のミーティングに切り替えよう。
効率的な会議運営は、バリスタが常駐するコーヒーバーを新設して社員の職場復帰を促すよりも、コスト効率が高く、職場に活力をもたらしてくれる。
誘惑2:従業員のウェルビーイングの軽視
労働市場が縮小すると、一部のリーダーは「経済的に安定してさえいれば、従業員の離職は阻止できる」と考えるようになる。その結果、ウェルネスプログラムは削減され、メンタルヘルスの取り組みは消え去り、柔軟な働き方は一夜にして廃止される。そこにあるのは「求人件数を上回る求職者がいるのだから、従業員は多少のストレスは我慢するだろう」という発想である。
しかし、景気後退はバーンアウト(燃え尽き症候群)を解消するどころか、むしろ悪化させる。長年にわたる予算削減や採用凍結によって、限界まで神経をすり減らした従業員は、やる気を失うか、目立たない方法で抵抗を始める。欠勤が増え、生産性が低迷し、顧客対応の質が落ちる。厳しい時期にウェルビーイングに十分な投資をしなかった企業は、労働市場が回復した際に、燃え尽きてしまった従業員たちのケアに追われることになる。
バーンアウトは単に士気を引き下げるだけでなく、莫大なコストも生む。ギャラップが2022年に行った調査によれば、「少なくとも時々、燃え尽きを感じる」と答えた従業員は76%、「頻繁に」あるいは「常に」と回答した人は半数近くに達した。
バーンアウトの従業員が退職すると、代わりの人材を補充するために、辞めた人の年収の50~200%のコストがかかる。一方、世界保健機関(WHO)の推計によれば、職場における不安やうつ病によって、世界経済は年間1兆ドル相当の生産性の損失を被っている。
代わりにすべきこと
組織は、ウェルビーイングを「特典」ではなく、ビジネス戦略の一環と認識すべきだ。従業員の健康と柔軟性を優先する企業ほど、優秀な人材をより長く引き留め、生産性を向上させられる。
回復を必要としない職務設計を行う
メンタルヘルスプログラムを自慢しながら、一方で従業員に神経をすり減らすような働き方をさせている企業は、食中毒の原因を正すことなく、胃薬を配っているレストランのようなものだ。
グーグルの調査プロジェクト「プロジェクト・オキシジェン」は、最高のチームは技術面で優れているだけでなく、心理的安全性があり、業務量も持続可能な水準に保たれていることを明らかにした。バーンアウトは、ヨガのアプリで解決できる類のものではない。解決には、わざわざ心身の回復に取り組む必要がないよう、業務構造を見直すことが必要だ。
バーンアウトを防ぐためには、明確な期待値設定、日によって変わることのない優先順位、従業員が求められる成果を着実に出せるよう導く継続的なコーチングといった基盤が必要となる。また、業務の負荷がスキルセットに応じて均等に配分されるよう、「ジョブ・クラフティング」のツールを活用するのも有益である。
出勤状況ではなく、成果を柔軟な働き方と連動させる
チームが目標を達成しているのであれば、「部下がいつ、その日の仕事を始めるか」は、あなたが思っているほど重要ではない、という現実を受け入れよう。2022年の全米経済研究所(NBER)の調査によれば、ハイブリッド勤務の人はフルタイムで出社している人よりも生産性が5%高く、ナレッジワーカーについてはその傾向が特に顕著だった。
硬直的な勤務体制がエンゲージメントを損なっているのなら、それは単なる方針の選択ではなく、ビジネス上のリスクに直結する。たとえば、一部の企業は「結果のみに基づく勤務環境」と呼ばれる組織設計を導入している。これは、各自のパフォーマンス指標を達成している限り、仕事をする時間と場所を自由に選べるという制度である。こうしたマネジメントモデルは、従来型のチームと比べて、生産性、エンゲージメント、定着率のすべての指標を向上させることが実証されている。
ウェルビーイングを言葉ではなく、予算項目に組み入れる
自社のウェルネス施策が「心身の健康を大切に」というメール送信だけで、その裏でメンタルヘルス支援のリソースをひそかに削減しているのなら、労働市場の逼迫状況にかかわらず、社員が「心身の健康を大切にする」ために退職を選んだとしてもショックを受けるべきではない。ウェルビーイングを人事上の特典ではなく、運営上のコストと見なす企業のほうが、従業員のエンゲージメントが高く、離職率が低く、持続的に高い業績を実現している。
午前中の会議禁止による集中時間の確保、予測可能なスケジュール方針、低コストのメンタルヘルス補助金など、莫大なコストをかけない取り組みでも、現実的な効果をもたらすことは可能だ。たとえば、パタゴニアは有給のアウトドア活動休憩を導入している。また、アサナは「水曜日は会議禁止」の方針によって、深い思考を要する業務の時間を確保している。
誘惑3:「代わりがいる」というマインドセット
何よりも陰湿な誘惑は、従業員を簡単に代替できる存在と見なし、「仕事があるだけでありがたいと思うべきだ」と決めつける発想かもしれない。こうしたマインドセットのせいで、杓子定規の方針や懲罰的なパフォーマンス管理、従業員の貢献を無視する風潮が助長される。
従業員はやむを得ず会社に留まっているかもしれないが、全力を尽くすことはなくなる。指示されたことだけをこなし、それ以上の努力はしない。そして、よりよい選択肢が現れた瞬間に会社を去っていく。取り残された企業は、離職だけでなく、不況が終わった後も長く続く「悪評」という問題に直面することになる。
誰かが辞めたら、別の誰かを雇えばよいと考えたくなるものだが、データを見れば、それが誤りであることがわかる。前述した通り、従業員を一人入れ替えるためには、採用活動、オンボーディング、生産性の損失など、辞めた人の年収の50~200%のコストがかかる。
しかも、離職防止は、単にコストの問題に留まらず、イノベーションに関わる問題でもある。2023年のMITスローンの研究によれば、従業員体験の水準が最上位の企業は、最下位の企業と比べて、特許や新製品などのイノベーションの件数が2倍に達していた。自分が「使い捨て」扱いされている職場で、創造的なリスクを取ろうとする者はいない。
さらに驚くことに、現在のような厳しい採用環境と、全体的な自主的離職率の低さにもかかわらず、75%の業界がハイポテンシャル人材の離職が増加していると報告している。つまり、企業は自社のトップ人材が流出しないよう特に気を配るべきなのである。
代わりにすべきこと
従業員を使い捨て扱いする企業は、人材不足が再燃したタイミングで慌てて採用活動を行うという悪循環に陥ってしまう。企業は、売上げの成長率や収益性と並んで、従業員の定着とエンゲージメントも、リーダーの年間KPI(重要業績評価指標)に組み込むべきだ。主要人材の離職率が市場の平均よりも高い場合、リーダーにはその原因となった職場環境を是正する責任がある。
顧客ロイヤルティと同じように従業員の定着を設計する
企業は顧客の離反に目を光らせているが、従業員の離職を同じように追跡している企業がどれほどあるだろうか。スポティファイでは、データサイエンスを活用して離職リスクを予測し、ハイパフォーマーが離職について考え始める前からエンゲージメントの強化に取り組んでいる。従業員を顧客と見なすリーダーは、彼らが留まりたくなるような企業文化を設計しているのである。
「残るほうが得」と思えるよう、社内の流動性を再設計する
多くの従業員が、「社内での次のステップが見えない」という理由で会社を去る。自社の優秀な人材を外部のリクルーターに奪われる事態を阻止するために、社内の異動がスムーズに行われる仕組みを設計すべきだ。たとえば、すべてのリーダーに対して、各自の後任候補を少なくとも一人育成するよう義務づける制度を設ける、異動に伴う引っ越しや研修の費用を自動的に支給して、社外からのオファーよりも社内の異動に応じるよう促進する、といったアプローチが考えられる。
経営陣のボーナスを定着率と連動させる
リーダーシップ層が優秀な従業員の引き止めに本気で取り組むようにしたいのなら、ハイパフォーマーが会社を去った時に経営陣が経済的な痛みを負うような制度をつくるべきだ。アドビでは、経営陣の報酬の一部をエンゲージメントスコアと連動させることで、目先の利益だけでなく企業文化をインセンティブに連動させている。また、筆者らが関与したある組織では、従業員の残留、離職を予測するエンゲージメント指標を活用して、部下の定着率が最も高いと示されたマネジャーに報奨金を支給するようになった。その結果、望ましくない離職が組織全体で12%減少した。
* * *
現在のような歴史の転換点を利用して、従業員と雇用主の間を主導権が行ったり来たりする「二項対立の振り子」に終止符を打とう。そして、従業員と組織に必要なのは、双方にとって有益な関係だと認識すべきだ。どちらの側にもそれぞれ正当なニーズと、相手への期待がある。相手を「搾り取れるだけ搾り取るべき敵」ではなく、「ともに成功し、成長するために心から助け合う仲間」と見なすことこそ、双方にとって長期的に最善の道なのである。
"As Power Shifts Back to Employees, They Need to Avoid 3 Pitfalls," HBR.org, March 11, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









