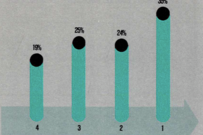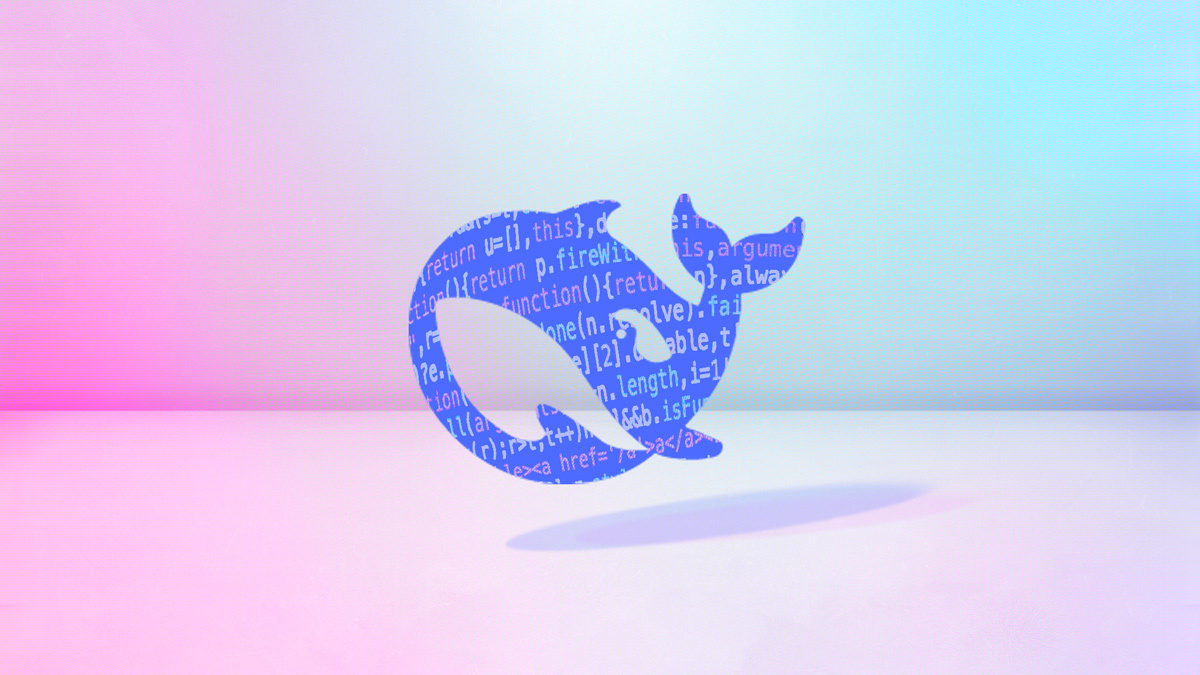
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ディープシークから企業が学ぶべきこと
2025年1月、中国のスタートアップ企業ディープシークはオープンソースのモデルをリリースし、AI業界、ハイテク株、そしてウォール街の寵児エヌビディアを震撼させた。このモデルは米大手企業の製品よりも小規模で効率的、かつ格段に少ない費用で開発された。ディープシークは瞬く間にアプリストアのチャートで1位に躍進し、この出来事は欧米のAI企業にとって警鐘となった。
テック業界はディープシークの影響について考えをめぐらせているが、このように騒がれることで、企業と業界にとってのより深く広い示唆が覆い隠されてしまうおそれがある。
リソースや技術ではなく、リソースフルネス(創意工夫する知恵)こそ、ディープシークが実現したことの裏にある真のストーリーであり示唆なのだ。
リソース対リソースフルネス
リソースは、ほとんどの企業が社内で争いを繰り広げる対象である。リソースは企業が投資家や資本市場の関心を得ようとする理由であり、予算編成プロセスの根幹を成す。リソースにはカネ、モノ、ヒト、知的財産などが含まれる。企業の貸借対照表の資産側に記載されるものすべてだ。
リソースフルネスは対照的に、企業が持つリソースとは関係ない。世界中のさまざまな知識、専門性、リソース、ケイパビリティを、たとえ保有していなくても創造的に活用する能力を指す。リソースフルネスによって、自社のリソースとケイパビリティのみを用いて達成できることよりもはるかに多くのことが実現可能になる。それをより低いコストと少ない資本で、往々にして独力で行う場合よりも優れた専門知識とスピードで成し遂げることができる。
AIのケースで言えば、業界が何千億ドルもの投資の必要性を唱えてきた一方で、ディープシークは最高性能のGPUチップを使わなかったと報じられている。開発に10年もかけず、数十億ドルも費やしていない。最先端のハードウェアにも頼らなかった。強力なAIモデルの構築に必要だと投資家たちが聞かされてきたコストと時間のごく一部しか使わずに、ディープシークのモデルは開発された。
どのように実現したのか。
業界の他の企業のように、力に任せて規模拡大するのではなく、ディープシークは創造性を優先したのだ。合成データと創造的なアルゴリズムを活用し、既存のAIモデルから知識を蒸留し、ゼロから始めるのではなくそれらを足掛かりにすることで、最先端のAIハードウェアにかかる費用を回避できると判断したのである。
だがリソースは、ほとんどの企業が成果を上げるために重視する指標だ。そして競争がより激しい業界や「ホット」な業界──血にまみれたレッド・オーシャンや、急成長中のAI分野など──ほど、より多くのリソースを求める声が高まる傾向がある。リソースフルネスへの道を優先または理解する企業は圧倒的に少ない。
これは大きな機会損失となる。
リソースフルネスを習得するための4つの道
筆者らの過去数十年にわたる『ブルー・オーシャン戦略』と『破壊なき市場創造の時代』に関する研究は、機会の実現に向けて価値を高めコストを下げるうえで、リソースフルネスが中心的な役割を果たすことを強調している。リソースフルネスによる創造性と創意工夫をてこにすることで、企業は市場での勝利と自社の成功をしばしば迅速に生み出すことができる。
企業がリソースを重視する代わりに、リソースフルネスを同程度に重視するとどうなるだろうか。そうすることで、企業が提供できる価値の向上とビジネスモデルのコスト削減がどのように可能となるのだろうか。
本稿では、ブルー・オーシャン企業が日常的にリソースフルネスを活かして機会を実現している4つの方法を検討する。あなたにも実践できる方法だ。
1. オンラインの知識を利用してケイパビリティを築く
自分で調べて答えを見つけたり、新たなケイパビリティを築いたりすることはかつてなく容易になった。費用をかけずに営業のテクニックをポッドキャストで、量産のための3Dプリントをユーチューブで、コーディングをカーンアカデミーで学んだり、デザイン、調達、ファイナンス、パッケージング、税制などに関するスキルを学んだりできる。世の中には誰もが利用できる無料の知識と教育があふれている──にもかかわらず、ほとんどの人や組織はそれを利用しない。オープンAIによってオンラインの知識はいっそう豊かになり、コストをほとんどかけずに利用できる状態にある。
ノット・インポッシブル・ラボという会社について考えてみよう。同社は、耳が聴こえない人でも聴こえる人と同じようにライブ音楽を体験できる、まったく新たな機会の創出に乗り出した。このプロジェクトは「ミュージック:ノット・インポッシブル」と名づけられた。
ノット・インポッシブル・ラボの代表を務めるミック・エベリングもプロジェクトを主導するダニエル・ベルカーも、これを実現するために必要な専門知識を持っていたわけではない。科学者や脳の専門家でも、聴覚学の博士でもなかったが、振動と耳の聴覚機能に関する科学的研究をインターネットで徹底的に調べた。
そして彼らは学んだ。聴くのは耳ではない。耳を通じて取り込まれた振動を脳が感知することで「聴く」のである。何よりもこの発見が、「振動は聴覚障害者の耳で捉えることはできなくても、皮膚を通じて振動を脳に伝え、音楽体験を再現することは可能だ」という気づきにつながった。この知識をもとに彼らは、ミュージック:ノット・インポッシブルを実現するためのウェアラブル技術を開発した。
エベリングとベルカーはリソースフルネスを通じて、世に出ている最も優れた知識を──実質的に無料で──活用することで、ミュージック:ノット・インポッシブルを実現し、開発過程での障壁を乗り越えることができたのである。
自問してみよう:自社のビジネスモデルと機会を実現するために、どの知識が必要だろうか。リストをつくり、インターネットでの検索やAIの活用を始めよう。最初は知識の網を広く張るために、大まかな条件で調べる。その後、クローズアップすべき具体的事項と、自社が学べる専門知識を持っていそうなキープレーヤーが明らかになるにつれて、調査を絞り込んでいく。
2. 外部のリソースを見つけ、自社に有利となる形で利用する
リソースフルネスは、社外のリソースや人材、専門知識、ケイパビリティを見つけ出して利用することで生まれる場合が多い。
例として、ジム・マッケルビーとジャック・ドーシーは、マイクロビジネスや個人向けのクレジットカード決済の市場を創出しようと乗り出した時、スクエアリーダーの構想を持っていた。どこにいようとクレジットカードをスライドさせて支払いができる、小型で邪魔にならないデバイスだ。問題は、決済を処理してクレジットカード会社に送信するにはどうすればよいか、であった。
マッケルビーはリソースを当てにする代わりに、活用できるものを求めて外部に目を向け始めた。そしてiPhoneが新聞、テレビ、カメラ、地図、フォトアルバムやステレオの役割を果たせることに気づいた。ならば、このデバイスに内蔵されている技術をクレジットカードの処理に活かせない理由があるだろうか。
スクエアはまさにそれを実行した。スクエアリーダーは、iPhoneや他のあらゆるスマートフォンのヘッドホンジャックに直接差し込むことができる。ヘッドホンジャックは世界共通かつオープン規格であるため、スクエアは提携も使用料もなしでアップルやサムスンのデバイスを使うことができる。こうして、多額な開発費を要する可能性も大いにあった仕組みが、ゼロに近いコストで実現した。
自問してみよう:自社に欠けているリソースを、社外の誰が持っているだろうか。自社に必要な技術的専門知識やケイパビリティを、どの組織が持っているだろうか。コストを大幅に切り詰め、ケイパビリティの不足をかなりの安価で補うために、彼らの専門知識やケイパビリティ、規模の経済をどのように創造的に活用できるだろうか。
3. 革新的なアイデアやソリューションを求めて他の分野や業界に目を向ける
自社の事業の範囲を超えて、他業界や他分野、または類似した状況に意図的に目を向け、自社の機会の実現に応用できそうな創造的手法を見つけることがリソースフルネスにつながりうる。
キックスターターを創業したペリー・チェン、ヤンシー・ストリックラー、チャールズ・アドラーは、芸術家が歴史的に活動資金をどのように得てきたのかを知るために、はるか昔に目を向けた。そして芸術活動に出資していたのはメディチ家や教会だけではなかったことを突き止めた。大勢の客たちが創作活動に出資した例が多くあり、アレキサンダー・ポープが『イーリアス』をギリシャ語から英語に翻訳した時もそうであった。この翻訳事業には750人が資金を提供し、見返りとして初版に彼らの名前が記載された。
これはキックスターターにとって、出資者に金銭的インセンティブではなく他の報酬、たとえばアーティストのウェブサイト上で感謝を表明するといった方法を考えるための重要なヒントとなった。
同様の例として、ジョーン・ガンツ・クーニーはテレビ番組『セサミストリート』の実現に向け、子どもたちの注意を引きつけてアイデアを強く印象づけるために、歌、色、スピード、韻の踏み方に至るまで、広告業界の手法を借りた。
ビデオゲーム業界は、eスポーツのリーグを立ち上げて世界的なeスポーツ選手権大会を開催する方法について知見を得るために、世界規模のスポーツに目を向け、熱狂の生み出し方、情報の広め方、放映権の供与を通じて大会を収益化する方法などを探った。
自問してみよう:自社の課題を解決する方法について、他にどのような業界、領域、類似した状況、時期や時代が洞察をもたらしてくれるだろうか。直面しているハードルを乗り越え、解決を目指すパズルの欠けたピースを迅速かつ安価に埋めるための、革新的なアイデアや方法を自由に幅広く考えながら答えを探ろう。
4. 社会資本を活用して機会を実現する
社会資本(ソーシャルキャピタル)とは、特定の社会やコミュニティに属する人々の規範、理解、つながり、相互のコミットメントであり、リソースフルネスを発揮するもう一つの機会になりうる。
1970年代後半にムハマド・ユヌスは、バングラデシュの農村部に住む貧困層に信用と銀行サービスを提供する方法を見出したいと考えていた。これらの顧客には担保がないという現実を克服するために、ユヌスは彼らの緊密な社会的つながりを活かすことで、融資が確実に返済され、借りた資金が貧困の連鎖を断ち切るための生産的な手段に使われるようにした。
ユヌスは初のマイクロファイナンス機関であるグラミン銀行を創設した。融資条件として、まず最低5人の村民が集まって互助グループをつくる必要があり、銀行はグループで指名された一人のメンバーに少額の融資を行う。その人物が数カ月にわたり定期的に返済した場合にのみ、他のメンバーが融資を申請できる。
この手法によって、誰も返済を怠ってはならないという明らかな同調圧力が生まれる。そしてグループのメンバーとして選ぶ対象は、仲間意識を感じられ、他のメンバーを失望させまいとする道義的責任を持つ者に限るというインセンティブが自然に働く。この相互依存はまた、苦境に陥っているメンバーがいれば進んで助けようとする動機にもなり、その過程で各借り手の信頼がさらに高まる。
すでに存在しているが未活用の社会資本を見つけて活かすことで、グラミン銀行は極貧層に初めて金融資本へのアクセスをもたらしただけでなく、継続的に90%を上回る返済率を達成した。さらに、融資の承認、実行、回収、契約に伴うコストを大幅に低く抑えた。
自問してみよう:市場ベースの経済的手段以外に、自社が活用できる社会資本はあるだろうか。どのような社会規範、確立されている信頼関係、相互コミットメント、または高次元で一致している利害を、自社のビジネスチャンスの実現に向けて活用できそうだろうか。
* * *
多くの組織にとって、リソースは大きなハードルだ。これは自己資金のみで運営する小規模企業だけでなく、リソースをめぐる争いが同様に厳しいであろう大企業にも当てはまる。リソースが限られている今日の環境においては特に、リソースフルネスを発揮する方法を習得することはこの上なく有益だ。
AIの枠を超えて、ディープシークの成功は、戦略のカギを握る要素としてリソースフルネスがいかに重要かを思い出させてくれる。
"What DeepSeek Can Teach Us About Resourcefulness," HBR.org, April 03, 2025.








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)