
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
CEO候補者を適切に評価できる「成長計画」
ピーターを選べば間違いない……はずだった。次期CEOの選定を進めていた取締役会にとって、彼はCスイートの中でも突出したスター的な存在だった。与えられたすべての役職で成功を収め、過去の業績評価から幹部評価報告書、マネジメントスキル評価まであらゆる指標で秀でていた。
しかし、ピーターのCEO就任から半年後、会社が苦境に陥った。彼は当初、対応策を用意していると語っていたが、時間が経つにつれて、取締役会はその計画が自分たちの望む方向性と合致していないと感じるようになった。ピーターは情報をオープンに共有していないのではないか、会議の場で弁解ばかりしているのではないか──。そのような懸念を募らせた取締役会は、1年後、彼を解任し、白紙の状態から人選をやり直すことになった。
CEOの選考プロセスがうまく機能しなかったのはなぜか。原因は、候補者の過去のデータにばかり目を向けていた点にあると、取締役会は気がついた。
もちろん、面接の場では将来のビジョンについても質問したが、ピーターの返答が一般的かつ安心できる内容だったため、それ以上深掘りすることはなかった。後になって思えば、ピーターの過去の成功を重視しすぎて確証バイアスに陥った結果、人選を誤ったのである。
こうしたケースは珍しくない。企業の取締役会がCEOを任命する際には通常、過去の実績や成果に注目して選考を行う(Cスイートのリーダー選定でも同様の課題が生じている)。候補者がこれまで、どのようにビジネスを組み立て、成長を実現してきたかに関する情報はふんだんにあっても、目の前の課題や差し迫るプレッシャーを認識し、それに対処する力については十分な情報を持ち合わせていない。
面接を通して有用な情報が浮かび上がるのは確かだが、このレベルの幹部になると、短時間の質疑応答では、新たなポジションでどのような働きをするかについて体系的かつ明確な見解を得られないケースも多い。また、大半のデータは候補者同士の比較がしにくく、指標を揃えて評価することができない。しかも、面接で語られる言葉は、魅力的ではあっても、一般的な内容になりがちだ。
過去の実績や面接を補完するために、企業は自社の未来に関する各候補者のビジョンについて、体系的で比較可能かつ詳細な検討を行うべきだ。その際に有効なのが、候補者に「成長計画」を策定させるという手法である。成長の道筋を具体的に描かせることで、取締役会は未来に関わる軸を選考基準に加えられる。そして、企業の戦略的コミットメントに対する各候補者の対応を予測することが可能になる。
筆者はリーダーシップアドバイザーとして、幅広い業界の主要なグローバル企業で何十件ものCEOおよびCスイート任命の案件に携わってきた。その際には、会社の将来へのビジョンと、優先順位の見極めという観点から候補者同士を比較するツールとして、成長計画を頻繁に活用している。
成長計画に含まれるもの
成長計画を策定することで、候補者はCスイートの選考委員会に有益な情報を提供し、同時に、みずからの能力を活かすことより先に、まず会社のニーズについて振り返ることができる。選考委員会の側も、候補者に成長計画を書面で提出させることで、昇進後や採用後の実際の言動について一定の説明責任を担保できる。
成長計画の狙いは、成功のビジョンの根幹を成す4つのセクション──1)ビジネスへの影響、2)組織への影響、3)ステークホルダーへの影響、4)個人としてのリーダーシップへの影響──を含む簡潔な2ページの文書を作成することだ。候補者は各セクションについて、1年後に実現させたい成功の中身と、その測定方法について具体的に述べる必要がある。
候補者に「宿題」として個人で計画書を作成させる代わりに、チーフ・ラーニング・オフィサーや上級のリーダーシップ開発専門家、あるいは外部のリーダーシップアドバイザーに、ファシリテーターとして候補者の計画策定をサポートさせる企業もある。このプロセスには、ホワイトボードを活用した対話や議論などの対面セッションが含まれる場合もある。
こうした場で重要なのは、候補者が「選考委員会には最終的な書面による計画のみが共有される」という確信を持って、自分の思いを自由に表現し、ブレインストーミングをし、思ったことを口にできることだ(ファシリテーターは会話の内容を口外しない)。また、書面に記される計画は、会社の意向を汲み取った内容ではなく、各候補者独自の内容であるべきだ。
対話を活性化するために、ファシリテーターはさまざまな工夫をする。たとえば、成長計画を頓挫させるリスク要因について議論する場合によく用いられるアプローチの一つに「プレモーテム」がある。これは、この経営幹部が1年後に失敗すると仮定したうえで、失敗の可能性を低減させるために、どのリスクを減らすべきかを検討する手法である。
また、成長計画の内容を、新たなポジションの就任初日に取り組み始める優先事項に落とし込む方法について候補者に議論させるという方法もある。4つのセクションのうち、どれに集中すべきか、どのような行動を始めるべきか、あるいはやめるべきか、そして、どのようなリーダーシップ行動を優先すべきか。望ましいのは、明確かつ具体的で、測定可能な行動を伴う回答だ。
最後に、これらの問いへの返答は候補者本人の個人的および職業上の志向や価値観と合致しているだろうか。候補者は、自分は準備万端で、意欲に満ちており、課題に安心して取り組めると答えるだろうが、言葉の端々に興味深いディテールがにじみ出る場合もある。
成長計画が完成したら
各候補者による成長計画が出揃ったら、取締役会はすぐにフォローアップ面接に進める。筆者が関わってきた選考委員会は、成長計画を活用して、構造化され透明性の高い対話を実現している。
面接を通して選考委員会は、候補者の持つ前提や思考スタイル、志の高さ、リスク要因に関する思慮深さ、自己認識、弱さをさらけ出す姿勢などについて理解を深められる。その過程で、選考委員も、自分たちの会社へのビジョンが思っていたほど一致していないことに気づかされたりする。
選考委員会は、候補者が描く成功のビジョンと、それが同僚にもたらすインスピレーションやモチベーションに注目することが多い。また、候補者のビジョンと会社の戦略の整合性についても検討する。
こうした対話を通じて、課題に柔軟に対応できるか、質問に対して防御的にならないか、特定のアプローチについて自信を持ちすぎていないかなど、候補者の「成長アジャイル」の度合いを測ることができる。
サーチコンサルタントやリクルーターから提供される外部評価と違って、成長計画は候補者自身が主体的にプロセスを管理できる。自分の立てた計画次第で、その後の面接のアジェンダが決まるのだ。
この成長計画はもちろん、商業的な目標設定やKPI(重要業績評価指標)の設定を補完するものになりうる。そうした領域では、将来を見据えた計画や透明性が一般的だ。そして理想を言えば、このプロセスが選考委員会だけでなく、候補者自身にも洞察をもたらす機会となることが望ましい。
ひとたび新たなCEOが着任したら、選考委員会は成長計画に照らしながら進捗を追跡できる。また、それ以上に重要なのは、このプロセスによってガバナンスが強化される点だろう。取締役会とCEOの関係が通常よりスピーディに立ち上がり、予想外の事態が起きにくいスタートを切れるのである。
取締役会が具体的かつ比較可能な情報を得られる一方、この選考プロセスは選ばれなかった候補者にもメリットをもたらす。全員が、自分の成長に真剣に向き合ってもらえたと実感し、「本物」の経験をしたと感じるのである。多くの候補者が初めは懐疑的で冷めた態度を取っているが、やがて自分がこのプロセスに主体的に関われることに気づき、積極的になっていく。彼らは、オープンで内省的な探求プロセス──しかも、構造化されており、彼らの洞察を効率的に引き出してくれるプロセス──を経験できたことに感謝している。
成長計画には、経営幹部がみずからの成長を企業ニーズの文脈の中で考えざるをえなくなるという付加的なメリットもある。長年の経験を持つ幹部の中には、自身を成長させる努力をやめてしまった者も多い。地位を追い求め、自己実現や真の意味での成長を置き去りにしているのだ。
さらに候補者たちは、取締役会との間で、ふだんと異なるタイプのファシリテートされた対話ができたことにも感謝している。たとえ互いをよく知っていたり、他のトピックについて頻繁に話し合ってきたとしても、この手の対話は特別で、どちらの側に対しても弱さをさらけ出すことを促す力がある。
選考委員会にとっては、このプロセスを通じて、候補者がCスイートでどのように振る舞う可能性があるかという新たな次元の情報を得られるというメリットがある。上位の幹部ポジションは極めて重責で、同時に消耗の激しいポジションでもある。選考を通過した候補者には、重大な問いに対して本気で取り組む覚悟が求められる。
会社がある方向に進もうとしている一方で、候補者が別の方向を目指しているのであれば、選考委員会はその点を把握しておく必要がある。それが、あらゆる関係者の利益となる。
理想を言えば、社内のCEO候補者は、その座を模索するずっと前から、後継者計画にリストアップされている上級幹部に毎年課されるプロセスの一環として、成長計画の策定に取り組んでおきたい。ただし、選考の際に初めて計画書を作成する場合も、成長計画が有益なのは変わりない。
成長計画が「危険信号」をあぶり出す
成長計画が、ふさわしくない候補者を採用するリスクを回避する助けになることもある。筆者が関わったある成長著しい企業の取締役会を例に取ろう。この会社は、次の成長フェーズを牽引する新たなCEOを探していた。候補者の中で際立って優れた人材がいたが、取締役会がM&A(企業の合併・買収)を主軸とする成長を目指していたのに対し、彼女の成長計画はオーガニックな成長を志向していた。面接によってこの認識のずれが明確になり、結局、取締役会は別の候補者を選んだ。
地域ごとに分権化されたある大企業の取締役会は、別の課題に直面していた。同社は、最大規模の地域部門を率いるCEOを選定しようとしていた。ある候補者が描いた成功のビジョンは「自分の地域の売上げシェアを全社の中で最大にすること」で、地域単位で運営される同社の方針にはそぐわないものだった。
このビジョンは、取締役会にとっては「危険信号」だった。取締役会が求めていたのは、社内競争ではなく対外的な競争に注力するリーダーだったからだ。
成長計画を通して、懸念すべきレベルのナルシシズムが浮き彫りになるケースもある。ある候補者が提出した成長計画は、自分にとってその役職が素晴らしいものである理由に主眼が置かれ、その役割を通じて、自分がどう貢献できるかという視点はほとんど記されていなかった。
成長計画を活用して、最終的に選ばれた候補者に重要なフィードバックを提供した取締役会もある。この候補者は自身の弱点の改善に取り組もうとしていたが、取締役会は、彼自身が強みと認識している分野、つまり、他者に挑戦を促して、高い成果やパフォーマンスを引き出す力こそが最大のリターンをもたらすと考えていた。
* * *
CEOはもちろん、Cスイートやそれに準ずるあらゆるリーダーシップポジションの後継者を選ぶに当たって、成長計画は価値の高いツールとなる。未来の可能性について候補者に探究させるプロセスは、取締役会に重要な情報をもたらすだけでなく、選考から漏れた候補者にも有意義な経験になるのだ。
"When Picking a New CEO, Ask Them for a Growth Plan," HBR.org, May 08, 2025.

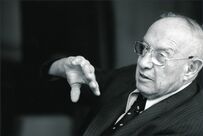




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









