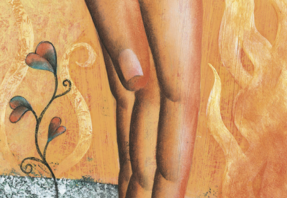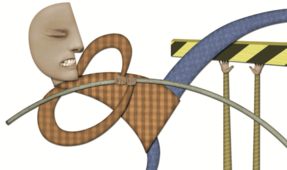-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
失敗は成功の反対ではない
「成功への最短距離は、失敗の確率を2倍にすることだ」
IBMの創業者、トーマス・ワトソン・シニアはこう言った。近年、このような見解を支持する経営者が増えている。イノベーションの担い手たちにすれば、以前より自明の理であったことを、経営幹部たちもようやく理解しつつあるようだ。
失敗なくして、技術革新など起こりえない。リスク・テイキングを奨励することなく、それゆえ必然的な失敗に学ぶ意欲に乏しければ、画期的な商品や優れたプロセスなど、とうてい開発できない。このように失敗に寛容となることで、技術革新へのアプローチはだんだんと変わりつつある。
たとえば、あらかじめプロジェクトの撤退を戦略に組み入れている企業がある。不運な活動が際限なく繰り返されるのを防ぐためだ。
また、クレジットカード会社のキャピタルワンのように、市場調査を何度も実施し、これを繰り返し続けるという企業もある。これらのほとんどが費用に見合うほどの成果に至らないのは覚悟のうえだ。たとえ失敗に終わっても、顧客の嗜好を把握するうえで貴重な洞察を与えてくれるだろうという趣旨ゆえなのである。
そのほか、同一の目標に向けて複数のプロジェクトを同時に立ち上げ、各チームを異なる方向に送り出すところもある。このアプローチは、都市工学のアレクサンダー・ローファー教授によって「同時進行管理」(simultaneous management)と命名されたもので、新たなアイデアや技術を相互かつ健全に交換し合う可能性が高い。
さて、経営方針やプロセス、事業慣習において、失敗に秘められた価値は大まかには認められつつある。しかし、これが個人のレベルになるとまったく違う。だれだろうと、やはり失敗は忌み嫌うべきものなのだ。理屈はともかく、失敗すればおろおろするし、尊敬や信頼を失ってしまうかもしれないと悪く考える。
ビジネスという競争社会以外に、これほどまでに人々に失敗を恐怖させ、それによって意気消沈させるものがほかにあるだろうか。この世界では、失敗のおかげで、ボーナスが下がったり、昇進が白紙に戻されたり、場合によっては仕事そのものを失いかねない。
ロバート・シャピロがモンサントのCEOを務めていた時、社員たちがどれほど失敗を恐れているかを知り、びっくりしたという。モンサントの社員たちには、失敗製品や失敗プロジェクトを不名誉と恥じる習慣が染みついていたのだ。
シャピロはこのような考えを改めさせようと頑張った。言うまでもなく、ビジネスの原動力である創造力が阻害されてしまうからである。