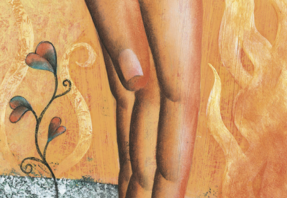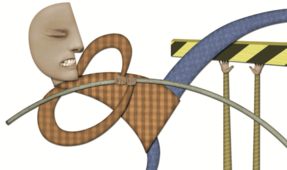-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
思いやりと組織力との相関
悲劇的な出来事は、前もって備えようもない難題を突きつけてくる──。
こう言うと、2001年9月11日の同時多発テロがまず頭に浮かんでくるが、このような例外中の例外といった事態のほかにも、経営者にしろ、社員にしろ、不幸は訪れる。そう、不幸は組織であろうと個人であろうと、おかまいなしなのだ。
ガンと診断されることもあれば、思いも寄らぬ病気で家族を失うこともあるだろう。また、天災によって街全体が被害を受け、何百人という人たちが亡くなったり、怪我を負ったり、住居を失ったりするといった、よりスケールの大きいものもある。
このような出来事は、当事者のみならず、同僚や友人、時には見知らぬ第三者やこの光景を目の当たりにした人たちに耐えがたい精神的苦痛を強いる。そして、この痛みは職場へも伝播していく──。
将来への希望を求めて、人々が意味と理由を探そうとしている状況では、マネジャー読本などまったく役に立たない。とはいえ、このような艱難辛苦、ましてや混乱に集団が陥っている時、リーダーとしてやれることがある。あなたはその立場を生かして、みんなへの気配りを通して、組織全体に思いやりの輪を広げ、個人と会社に癒しをもたらすことができる。
ミシガン大学とブリティッシュコロンビア大学のコンパッション・ラボが実施した調査によれば、思いやりという能力は万人に備わっているものの、組織がこれを制限する場合もあれば、逆に奨励する場合もあるという(囲み「コンパッション・ラボの概要」を参照)。
人間性という至極当然ともいえる理由を超えて、組織に思いやりがあふれていることがなぜ重要なのだろうか。
職場に思いやりの気持ちを呼び起こすことで、精神的ダメージを受けた人々の苦悩を和らげるだけでなく、挫折からいち早く回復できることにもなり、その結果、同僚との一体感が高まれば、会社へのロイヤルティも強まろうと考えられるからだ。
だれかを思いやる、もしくはその様子を目の当たりにすることの効果は絶大である。このような気配りがあれば、自らの再起力と組織へのロイヤルティもより向上しようというものだ。