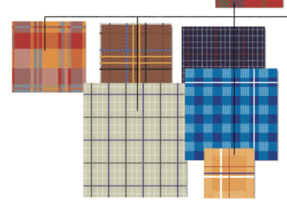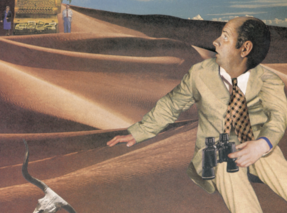-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
シナジー追求の副作用
シナジーを創造しようという動きが、多くの大企業で広がりつつある。コラボレーションを効率化させるために、会議や研修でアイデアを出し合う。部門横断的なチームを結成し、重要顧客向けプランを練り、新製品開発を調整し、ベスト・プラクティスを社内に広める。ノウハウや人脈、顧客を共有するためのインセンティブを複雑な報酬方式に組み込む。ビジネスプロセスや手順を標準化し、新たに設けられた部門横断的な職位が機能するように組織構造を再編する。
このような活動から、いったい何が生まれてくるのだろうか。長年にわたるシナジーに関する研究によれば、シナジーを実現させる活動は経営陣の期待に応えられないままに終わる例が多いようだ。形式的な会議が数回実施されただけで立ち消えになるものもあれば、一気に活動を開始したものの徐々に尻すぼみしていくものもある。所期の目的を何も達成できないまま、恒例行事として続けられるケースもある。
こうした失敗の努力の産物が、せめて失望と無力感だけであれば、これも学習的経験と寛大に受け止めることもできよう。とはいえ、シナジーを追求する場合、かなりの機会コストが発生することが多い。通常業務からマネジャーの注意をそらし、利益活動を阻害しかねない。
時にはシナジー活動が明らかに裏目に出て、顧客との関係が悪化し、ブランドに傷がつき、社員の士気ががた落ちになることすらある。つまり、多くのシナジー活動は、価値を創出するどころか、破壊を招いているのだ。
もちろん、この類の失敗は避けられる。ただし、それにはシナジーについてまったく新しい見方や考え方が求められる。経営者は「そもそもシナジーは存在しているから、すぐ実現可能で、利益がもたらされる」などと決めてかからず、もっとバランス感覚を持って、「眉に唾する」くらいの気持ちで臨むべきである。自らの直感を吟味したうえで、シナジーの誘惑に打ち勝たなければならない。
新しいアプローチを採用すれば、見込みの薄いシナジー活動に貴重な経営資源を注ぎ込まずに済むだろう。さらに重要なのは懐疑的なスタンスを取ることであり、組織のどこに真のシナジーの可能性が埋もれているのかを把握することである(囲み「シナジーとは何か」を参照)。