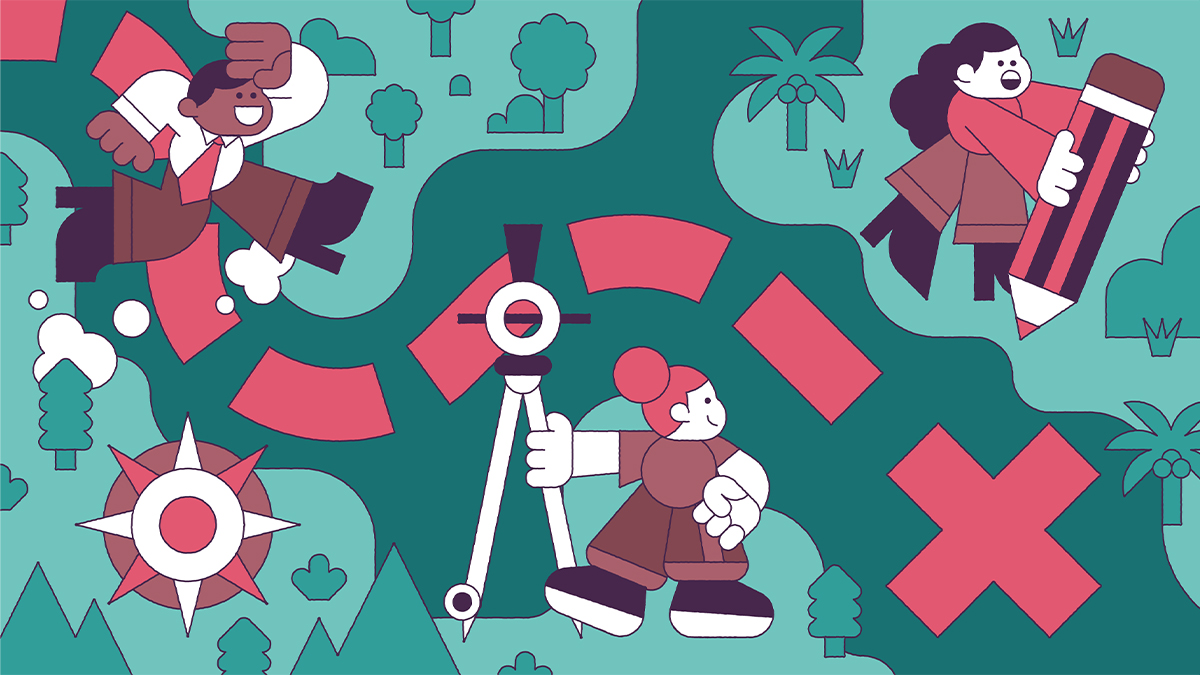
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業の気候変動対策は後退も、リスクは消えていない
ここ1年、企業の気候変動対策に対する政治家や投資家からの反発が強まっている。2021年以降、米国の州議会には、反ESG法案が320件近く提出された。フロリダ州やテキサス州などでは、公共投資におけるESG配慮事項の使用を制限した。米国証券取引委員会(SEC)は気候関連開示規則を事実上撤廃し、審議中だったカリフォルニア州の気候関連開示法は、訴訟を提起されている。
こうした反発を受けて、米国企業の一部に後退の動きが見られる。気候関連開示の縮小、サステナビリティ部門の人員削減のみならず、排出削減目標の放棄に踏み切るケースもある。ブラックロック、ゴールドマン・サックス、ステート・ストリート、JPモルガン・チェースなどの大手金融機関は、国際的な気候アライアンスから脱退し、アルファベットやマクドナルドなどの企業は公式声明から「ESG」を削除した。エクソンモービルは、より厳しい排出削減目標を提案した株主を提訴するという異例の措置を取った。
しかし、サプライチェーンの混乱や資産の減損、消費者の嗜好の変化など、気候変動に伴うリスクは依然として消えていない。むしろ加速している。気候変動による影響が具体化する中、企業には、緩和策(排出削減)と適応策(物理的および事業運営上の気候リスクへの耐性強化)の両方が必要になる。世界的に、企業はこうしたリスクを認識しているようである。ESG後退に関する報道があるにもかかわらず、PwCの調査によれば、2024年にCDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)に気候目標を報告した4000社以上のうち、37%の企業が目標を引き上げたのに対し、目標を引き下げた企業は16%にすぎなかった。とすれば、企業の取締役会にとっての課題は、気候ガバナンスに取り組むべきかどうかではなく、監視が強化される時代に、その取り組みでいかに信頼性、合法性、効果を実現するかということである。
変化する情勢に向けた指針
2024年、筆者らは、『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)の論文「気候変動をめぐる意思決定に取締役会が関与すべき理由」の中で、環境への取締役会の意義ある関与の証となる8つの特徴について説明した。本稿では、この論文を発表してからの政治的、社会的変化を踏まえ、アップデート版として、今日の気候を取り巻く情勢の変化を乗り越えるための指針を提供したい。
1. いまこそ自社の気候プロファイルを把握する
監視が強化される中、取締役会が自社の気候プロファイルに関して基本的な知識を持つことは、第一の防御線である。取締役会は、自社の気候リスク、つまり自社が気候にどのような影響を及ぼしているか、そして何より気候からどのような影響を受けているかについて、揺るぎない理解を築かなければならない。気候データは、社内的に正確であるだけでなく、社外に対して説明できるものである必要がある。
それはすなわち、排出量指標の第三者検証、仮説の厳格なストレステスト、世間の批判への備えが不可欠ということである。シナリオプランニングでは、法規制の断片化、政策実施の遅延、サプライチェーンの不安定化、税制優遇の減少、物理的気候影響の増大といった想定可能な未来を、幅を持って加味する必要がある。各シナリオについて、自社にとってのリスクと機会、それが企業市民としての責任にどのように影響するかを理解しなければならない。
2. 取締役会の役割を定義する
気候変動に関する監督から撤退するように迫る圧力に対して、取締役会は、気候リスクがESGのトレンドではなく、事業の中核的なファンダメンタルズそのものと結びついていることを認識すべきである。以前の論文で述べたように、気候問題の監督における取締役会の役割を明確に定義した上で、定款、委員会要綱、株主総会資料に明記すべきである。
リスク管理、戦略的レジリエンス、長期的価値創造といったフィデューシャリー・デューティー(FD、受託者責任)との関連性も同様に明確にする。ガバナンス文書は、法務担当者のレビューを受け、変化する期待との一致を確認することが推奨される。
3. 組織防衛可能な監督体制を構築する
監督機能を独立したESG委員会に集中させるよりも、分散型のガバナンスモデルのほうが堅牢であり、攻撃を受けにくい。独立した「ESG委員会」は、活動家の恰好のターゲットになる。
気候問題の監督の調整責任は、主要な委員会(ガバナンス委員会や指名委員会)に委ねるが、気候関連のさまざまな分野の責任を、それぞれの分野に関連した委員会に持たせることを引き続き推奨したい。つまり、監査委員会(開示対応)、リスク委員会(リスク対応)、報酬委員会(インセンティブ対応)などである。この統合的なアプローチは、批判を受けた時にさらに価値を発揮する。なぜなら、気候変動に対する配慮が事業の中核的なプロセスに組み込まれていることを示すからである。最新の流行を追従するのではなく、事業への統合をアピールできる。
取締役会がいかに説明責任と一貫性を支える構造を持っているかを明文化し、意思決定を恣意的に行っているという印象を持たせないことが重要である。政治情勢が再び変化した場合でも、取締役会は構造を全面的に変えることなく、重点を調整するだけで済むだろう。
4. 用意周到に専門知識を磨く
有意義な監督を行うには、情報に基づいた関与が不可欠である。取締役が気候に特化した知識や経歴ではなく、移行経済、エネルギーシステム、法規制リスクなど、事業に関連した専門知識を有するよう注力する。独自のブリーフィング、現地視察、中立的な教育機関との提携などを通じて、多角的学習アプローチを実践する。
意図的かつ継続的に関与する姿勢を示すことで、取締役はみずからの信頼性と理解の両方を向上させられる。トレードオフがかつてないほど複雑になる中、気候リテラシーを欠いた取締役は、情報に基づく選択を行うことや、懐疑的なステークホルダーに気候に関する自社のスタンスを説明することに苦慮するだろう。
5. 気候に関する自社のポジショニングを明確に。一貫性が重要
企業は、自社のコミットメントやステークホルダーの期待を放棄したように見せずに、自社の気候問題に対する姿勢を定義するという微妙な課題に直面している。リーダーシップを取るのか、追従するのか、遵守するのか。いずれの立場を目指すにしても、明快さが極めて重要である。以前から筆者らが強調してきたように、取締役と経営陣は、気候に対する自社の姿勢を一致させなければならない。
また、会社の姿勢を正確に伝える必要がある。気候に関するコミットメントや活動などの情報の公表を控える「グリーンハッシング」は、注目を避ける合理的な方法のように思えるかもしれないが、透明性の欠如は、他のステークホルダーを疎外する可能性があり、財務上重要な気候関連情報を開示しなければ、法的な問題につながりかねない。透明性の欠如によって、気候変動に対する共同アクションも困難になる。
ポジショニングの透明性や一貫性の欠如は、不要なリスクを生む。ステークホルダーは、従業員を含め、企業が表明している気候問題に対する姿勢や企業理念に沿った行動を一貫して取っているかどうかを注視している。それはすなわち、内部戦略と公的な声明、投資家向け発表、規制当局への提出文書とを整合させなければならないということだ。目標を縮小する場合には、技術的限界、景気変動、資本再配分などの理由を説明する。こうした姿勢は、政治的な都合ではなく、事業戦略の結果であるべきである。
気候対策への懐疑論がある中、意欲の度合いに関係なく、気候問題に対する一貫したスタンスを取ることこそが信頼につながる。
6. 経営陣の計画を精査し、明確さと説明責任を求める
ESG決議に対する株主の平均支持率が、2021年の33.3%から2024年には19.6%に低下する中、取締役は、外部メカニズムからは提供されない説明責任を、みずからの監督機能で果たせるようにしなければならない。筆者らは、前出の論文で提唱したアプローチを引き続き推奨する。つまり、取締役は、財務予測と同程度の厳格さで、気候戦略をレビューしなければならない。
これには、排出削減目標、資本配分、事業計画が含まれる。明確なロードマップのない野心的な目標は避ける。問うべきは、目標の根拠となる前提条件は何か。責任者は誰か。これらの前提の正当性を公に、つまり株主、メディア、政策立案者に説明できるのか。独立検証と取締役レベルのダッシュボードがあると、気候問題の監視に信頼性や透明性が高められる。戦略縮小や、排出目標の緩和計画には、強化計画と同レベルの精査を実施すべきである。
「議会の公聴会に呼ばれたとしたら、自社の気候関連計画を明確かつ信頼性を持って説明できるだろうか」は、有用な試金石である。
7. インセンティブと事業運営を結びつける
賛否あるが、気候目標を経営陣のインセンティブと連動させることで、真剣な意思を示すことができるかもしれない。2025年のデータはまだ入手できないが、こうした方法を取る企業は、2024年においてわずかに増加している。2023年にはS&P500企業のうち23%だったが、2024年には28%が経営陣の報酬と気候指標を連動させている。気候連動型報酬を採用する際は、監査に堪え、事業成果と明確に結びつき、それに見合ったものでなければならない。
気候関連のパフォーマンスを外部評価や格付けではなく、どのように事業成果と結びつけるかを考える。インセンティブが政治的に微妙ならば、業績レビュー、戦略レビュー、バランスドスコアカードなど報酬ではない手段を活用する。目標は、説明責任メカニズムを通じた整合性の創出である。
8. トレードオフを認め、複雑性を受け入れる
気候ガバナンスはもはや(当初から、というべきか)ウィン・ウィンの物語ではない。これには、短期リターン対長期リターン、投資家の要求対排出削減目標、レジリエンス対リスクなど、現実の対立要素を調整する必要がある。トレードオフについて率直に議論し、「善い行いをして成功する」といった単純化しすぎたESGトークは避けるべきである。
代わりに、取締役会が競合する優先事項やシナリオをどのように天秤にかけているかを文書化する。洗練と透明性は、誠実さの証である。政治化した批判に対する最良の防御は、事業実態に根差し、文書化された合理的な意思決定プロセスである。競合するステークホルダーの利益や時間軸を、取締役会がどのように考えているかを明確に説明する。
取締役会は、いまこそ気候ガバナンスに対して現実的な視点を持ち、それに伴う複雑さや不確実性を認識すべきである。気候アクションが批判に直面する中、単純化しすぎたストーリーを語るのではなく、透明性を持って課題を認め、それを克服する思慮深いアプローチを示すことがより大きな信頼とレジリエンスを育む。
* * *
現在の政治情勢下で、気候ガバナンスから撤退することは、短期的には楽な選択になるかもしれないが、長い目で見れば戦略的なリスクを伴う。気候変動は、依然として深刻なビジネス課題である。反発が強まっても、保険会社や従業員など一部のステークホルダーは、今後も明瞭性と説明責任を求め続けるだろう。それはすなわち、政治的ジェスチャーとしてではなく、戦略的必然性として、気候問題をガバナンスの中核に組み入れるということである。そして、監視を恐れずに、それに備えることを意味するのだ。
"Boards Can Continue to Lead the Way on Climate Governance," HBR.org, August 18, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









