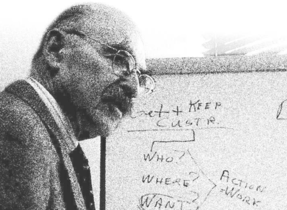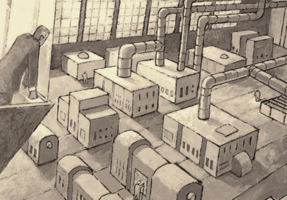-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
マーケティング界のドラッカー
いつの時代にあっても、マーケティングは再発見される。そのたびに新語やツールが紹介され、あたかもカレード・スコープ(万華鏡)が見せる模様のように様変わりする。とりわけ変革期には、「マーケティング志向の組織へ変わらなければならない」とその必要性が説かれてきた。
では、なぜマーケティングは不在なのか。理想のマーケティングと現実のそれはどれくらい乖離しているのか。そもそもその本質とは何なのか。
セオドア・レビットは「マーケティング界のドラッカー」とも称されることからも、学術研究よりも実学に貢献してきた人物である。その著作はアメリカのみならず、日本やヨーロッパでも広く流通し、数々の賞を受賞してきた(囲み「T. レビット小史」を参照)。
Biography of Theodore Levitt
T.レビット小史
1925年 8月25日生まれ
49年・カリフォルニア州にあるアンタキア大学を卒業
51年・オハイオ州立大学でPh.Dを取得
ノースダコタ州立大学にて初めて教鞭を執る
55年・Innovation in Marketing(邦訳『マーケティングの革新』ダイヤモンド社、1983年)を上梓
59年・ハーバード・ビジネススクールの講師となる
60年・歴史的名論文"Marketing Myopia"(「マーケティング近視眼」)を『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌に発表
62年・Industrial Purchasing Behavior(未訳)を上梓
・Innovation in Marketingの執筆者として「アメリカ経営学会賞」を受賞
64年・Marketing: a contemporary analysis(ジョン B. マシューズ・ジュニア、R. D. バズル、ロナルド E. フランクとの共著)を上梓
65年・同校のエドワード W. カーター寄付講座教授、ならびに『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌の編集長となる
69年・The Marketing Mode(邦訳『マーケティング発想法』ダイヤモンド社、1971年)を上梓
・The Third Sector: New Tactics for a Responsive Society(未訳)を上梓
・ビジネス・ジャーナリズムへの高い貢献が認められ、「ジョン・ハンコック(大陸会議の議長を務めた、独立宣言の最初の署名者)賞」を受賞
70年・「マーケティング・マン・オブ・ザ・イヤー」として「チャールズ・コーリッジ・パーリン賞」を受賞
73年・The Marketing Imagination(邦訳『マーケティング・イマジネーション』ダイヤモンド社、1984年)を上梓
74年・The Marketing Modeの改訂版としてMarketing for Business Growth(邦訳『発展のマーケティング』ダイヤモンド社、1975年)を上梓
76年・「ジョージ・ギャラップ(アメリカで最も信用度の高い世論調査の1つである「ギャラップ調査」を開発したジャーナリスト)賞」を受賞
78年・米国マーケティング協会がマーケティング・サイエンスの発展に貢献した研究者へ授与する「ポール D. コンバース賞」(1946年に創設)を受賞
83年・Thinking About Management(邦訳『レビット教授の有能な経営者』ダイヤモンド社、1998年)を上梓
88年・母校アンタキア大学の理事となる(1990年まで)
89年・国際経営会議(IMC:米国YMCAの下部組織)の「ウィリアム M. マックフリーリー(アメリカの著名なジャーナリスト)賞」を受賞
91年・"Futurism and Management"を『アンタキア・レビュー』に寄稿
・『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌への寄稿論文のアンソロジー、Levitt on Marketing(未訳)が発行される
マーケティング史上、あまりに有名な"Marketing Myopia"(邦訳「マーケティング近視眼」)は1960年に執筆された論考だが、これまで何百万人ものビジネスマンに影響を与え、いまだにテキストとして活用されている。
なお、レビットはこれまで14編の論考をHBR誌に寄稿しているが、先の"Marketing Myopia"を含めて、4回のマッキンゼー賞に輝いている(囲み「HBR誌への寄稿論文」を参照)。
T.Levitt On Marketing
HBR誌への寄稿論文
The Changing Character of Capitalism, July-Aug., 1956.
未訳
★Marketing Myopia, July-Aug., 1960.
「マーケティング近視眼」1982年4月号(初出)*1975年の再掲載論文の翻訳
「[新訳]マーケティング近視眼」2001年11月号(再掲)
Exploit the Product Life Cycle, Nov.-Dec., 1965.
未訳
★Innovative Imitation, Nov.-Dec., 1966.
「模倣戦略の競争優位」(2001年11月号)
The Johnson Treatment, Jan.-Feb., 1967.
未訳
★Why Business Always Loses, Mar.- Apr., 1968.
未訳
The Industrialization of Service, Sep.- Oct., 1976.
「サービス活動の工業化」1977年2月号
★Product-Line Approach to Service, Sep.- Oct., 1972.
「サービスに生産ライン方式を」1982年12月号(初出)
「サービス・マニュファクチャリング」2001年11月号(再掲)
Marketing When Things Change, Nov.-Dec., 1977.
「転換期のマーケティング」1978年4月号
Marketing Success through Differentiation, Jan.-Feb., 1980.
「差別化こそマーケティングの成功条件」1980年6月号
Marketing Intangible Products and Product Intangibles, May-June, 1981.
「無形製品と製品の無形性をどう売り込むか」 1981年10月号(初出)
「無形性のマーケティング」2001年11月号(再掲)
The Globalization of Markets, May-June, 1983.
「地球市場は同質化に向かう」1983年9月号
After the Sales Is Over..., Sep.- Oct., 1983.
「売り手に欠かせぬ買い手との関係強化」1984年1月号
The Case of the Migrating Markets, July-Aug., 1990.
「20年後の衰退に有効な対策はあるか」1990年11月号
*ケーススタディの編者として
Advertising: The Poetry of Becoming, July-Aug., 1993.
「広告──その幻想と素顔」1993年11月号
★はマッキンゼー賞受賞論文
あらゆる著作において、レビットは「顧客は商品を買うのではない。その商品が提供するベネフィットを購入しているのだ」と訴え続けてきた。
現在、マーケティングを再発見しなければならない時期が訪れている。これまでの轍を避けるならば、最新理論を考察するよりも、レビットの主張にいま一度耳を傾けたい。道に迷った時は出発点に戻るのが何よりの最善策である。
すべてがマーケティング
マーケティングがすべて
DHBR(以下色文字):レビット教授、あなたはこれまでに10余冊の書籍、数十の論考を執筆し、スタンダード・オイルをはじめ、数多くのアメリカ企業にその慧眼と知見を提供してきました。
アメリカ同様日本でも──残念ながら若いビジネスマンにあなたの存在を知る者は少ないですが──あなたの信奉者は数多くおります。