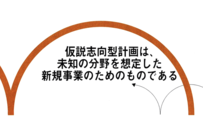年末などに大掃除をして、不要な物を大量に捨てると、それだけで達成感・充実感を味わえたり、整理された部屋にいると、なんだか思考や考え方まで整理されたような気になって、仕事がはかどったという経験はありませんか? このような職場の秩序化による心地良さが、活動の継続に繋がり、さらなるグレーゾーンの物の発見に繋がるのです。
ただ、この第2の論理は、「整理」が促進される論理ではあるのですが、新たな目的や事実の認識に直接繋がる論理ではありません。いわば心地よさによって活動が継続され、第1の論理が促進されることで、新たな問題発見に繋がるのです。
2.「清掃」が問題発見・活動継続に結びつく論理
次に、「清掃」がさらなる問題発見・活動継続に結びつく論理には、以下の3つが考えられます。
第1に、自らの手で自らの職場・設備の清掃を行い、この行為が習慣になってくると、「この職場・設備は自分たちのものだ」というオーナーシップの感覚が芽生えてきます。そして、このオーナーシップの感覚を通じて、例えば、日々隅々まで掃除をして点検することで、以前よりも自職場や設備を見る目が緻密になり、普段何気なく使ってきた設備や治工具に対するより深い技術的な理解が可能になったり、また逆に設備や治工具の様々な使いにくさが感じられるようにもなります。
「清掃」がさらなる問題発見・活動継続に結びつく第1の論理は、このようなオーナーシップの感覚によって、以前には気付かなかった様々な新たな事実を認識することに繋がり、その結果、新たな問題の発見に繋がるというものです。
第2の論理は、同じオーナーシップの感覚から派生して、職場や設備に対する愛着が湧くことで、「清掃」が促進される論理です。例えば、日々掃除をしてこまめに点検している設備に対して、徐々に愛着が湧き、さらにきれいにしていつもピカピカにしておこうとか、あるいは、いつもきれいにして点検しておいてあげなければ、設備が「可哀そう」といった感覚に結び付き、その結果、「清掃」が促進されます。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)