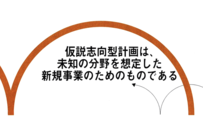第3の論理は、「整理」が促進される論理と同じで、身の回りのものを常にきれいにしておくこと自体が心地よいという、ある意味で単純な論理です。例えば、身の回りのものをきれいにするという行為は、乱雑な職場に対して一定の秩序を回復する行為ですが、様々な外部要因によって乱雑になってしまった職場に秩序を回復することは、思考や感情の秩序化に繋がり、すっきりとした感覚を感じることができ、この感覚をさらに味わいたいために、「清掃」が促進されます。
以上、第2・第3の論理は、「清掃」が促進される論理ですが、新たな目的や事実の認識に直接繋がる論理ではありません。いわば、職場や設備に対する愛着や心地よさによって活動が継続され、第1の論理が促進されることで、新たな問題発見に繋がるのです。
3.「整頓」が問題発見・活動継続に結びつく論理
最後に、「整頓」がさらなる問題発見・活動継続に結びつく論理について整理してみましょう。「整頓」では、3定や手元化が製造現場全体に義務付けられ、この状態が達成できているか「見える化」されます。そして、この「見える化」によって、自分自身のみならず、他人の目・管理者の目から見て、いつもこの状態が達成されているかどうかが見えるようになります。ここに、「整頓」がさらなる問題発見・活動継続に結びつく論理があります。
いわば、「整頓」を通じて、職場内部の秩序化ルールが「見える化」されることで、この職場に関わる全員がきちんと「整頓」されているかどうか一目で判断できるようになり、それ故に秩序化ルールに合致していない物や行為が、問題としてクローズアップされやすくなり、結果として新たな問題の発見に繋がるのです。
4.3S活動全体が継続する論理
以上、「整理」「清掃」「整頓」がそれぞれ新たな問題発見・活動継続に繋がる論理について述べてきましたが、これら3つの活動はそれぞれ独立している訳ではなく、相互に関連しています。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)