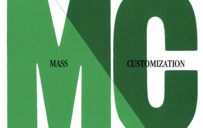いち早く西欧の文明を受け入れた堀田正睦
剛毅果断な判断で日本を救った「開国の元勲」井伊直弼
正弘の後を受けた老中首座・堀田正睦は、天保年間に一度老中を務め、佐倉藩に戻り藩政改革を推し進めます。農村対策や藩士教育を重視し、藩校・成徳書院を創設、西洋の兵制を採用し、西洋医学をすすめ、蘭医・佐藤泰然(たいぜん)を招き順天堂医院を開設、牛痘(ぎゅうとう)による種痘も実施しました。正睦は蘭癖(らんぺき)と揶揄されながら、「西の長崎、東の佐倉」といわれるように、いち早く西欧の文明を受け入れ、日本の文明開化に尽くしました。佐藤泰然門下からは、養嗣子尚中(たかなか)、次男で初代陸軍軍医総監の松本良順(りょうじゅん)、五男で後に在英日本公使としてロンドンで日英同盟に調印した外交官の林董(はやしただす)、明六社の西村茂樹(しげき) など明治各界の有能な人材を輩出しました。
1855年(安政2)に再び老中となった正睦は、外国掛(外交事務を掌握する)も兼任し、心血を注ぎます。しかし、通商条約締結に際しては勅許によって諸大名の反対を抑えようと上洛するも失敗し、将軍継嗣問題では、朝廷に信任のある一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)を推します。ところが、政変により、井伊直弼が大老となります。堀田正睦の老中首座は変わりありませんが、大老のほうが権力上位者です。しばらく後に老中を罷免されましたが、勅許工作と将軍継嗣問題での失敗が正睦の外交の失敗を意味するわけではありません。
強烈な使命感により一貫して日本の進むべき道は開国、貿易の開始しかないと主張し、その外交を主導し、通商条約締結時はすでに井伊直弼が大老に就任していましたが、正睦の老中罷免は、通商条約締結を待ってなされました。以上が、堀田正睦もまた「開国の父」と呼ばれるゆえんです。
 井伊直弼(1815~1860)
井伊直弼(1815~1860)
その後、1858年(安政5)4月に大老に就任し、1860年(安政7)3月の桜田門外の変に斃(たお)れるまで幕政を主導したのが井伊直弼です。直弼は、朝廷の許可をいっさい得ずに、日米修好通商条約の調印に踏み切ります。直弼とすれば、江戸幕府の草創期に武家諸法度、禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)が制定されて以来、政治のことについていちいち朝廷に伺いを立てる必要はないと思っていました。しかし、これが攘夷派を刺激し、桜田門外の変へとつながっていきます。
直弼は、開国に際しての違勅調印を独断したことで、「国賊」と批評される一方で、幕末動乱期の対外的に困難な立場にあった日本を剛毅果断な判断により救った「開国の元勲」として評価されます。いずれにしても、日本人としては稀な、強力な「リーダーシップ」を発揮した指導者であることは間違いありません。そして、その強力なリーダーシップによって、日本を開国へと導いたことも疑いのない事実です。
通商条約締結の結果、箱館(函館)、神奈川(横浜)、新潟、兵庫(神戸)、長崎の五港を開港します。現在、横浜港を眼下に見下ろす高台にある桜の名所、掃部山(かもんやま)公園(横浜市西区紅葉ケ丘)には、横浜開港の功績者として直弼の銅像が立っています。「掃部山」は、直弼の官位掃部頭(かもんのかみ)から名づけられました。彼が「開国の父」と称えられる証です。
(つづく)
「開国の父」三人の墓所
阿部正弘墓所(谷中霊園・東京都台東区谷中)
堀田正睦墓所(甚大寺・千葉県佐倉市新町)
井伊直弼墓所(豪徳寺・東京都世田谷区豪徳寺)
※タイトル写真出所:国立国会図書館ホームページ





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)