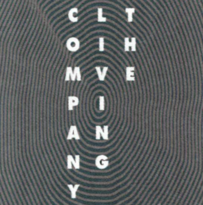25歳で宰相の位に就き39歳で早世
激動の時代を駆け抜けた阿部正弘
阿部正弘は1845年(弘化2)、徳川幕府創設以来最年少の25歳という若さで老中首座(宰相)に就きます。そして、老中首座としてペリー来航に直面し、鎖国政策を固守することなく開国に踏み切りました。これについては、外圧に屈した主体性を欠く外交という批判もありますが、正弘が幕府の総責任者として各国と結んだ和親条約を見ると、非常に困難な局面で欧米列強の勢力関係を冷静に分析し、欧米の最大の要求事項である通商開始を断固拒否するなど、巧みな交渉術を駆使しています。
外圧というプレッシャーは相当なものであったと思いますが、一方で、国内的にも、改革や制度変更時にしばしば見られるような、保守勢力(抵抗勢力)からのプレッシャーも相当なものでした。諸大名の九割以上が攘夷派という状況のなか、正弘は、攘夷派の巨頭である徳川斉昭(なりあき)島津斉彬(しまづなりあきら)らと積極的に交流します。正弘は、すでに開国を決断しており、それには攘夷派との妥協が成否の鍵を握ると見極めていたのです。もちろん、身内である幕閣内の先輩老中たちには礼を以って接し、閣内も掌握していきます。
老中首座となって一年ほど経った頃、当時禁制の軍艦製造が国防のために必要であることから、他の三人の老中に意見を求めたところ賛同者はなく、あっさりと諦めます。軍艦製造の実現はそれから七年後、正弘によってなされました。彼は、現実的かつ信念の人でありました。見識が高く、世界情勢に明るいという「政策能力」に加え、冷静な状況分析と現実的な判断で手腕を発揮する高度な「政治力」をも持ち合わせていたのです。
阿部正弘の業績は、開国という外交政策のみにとどまりません。踏み絵制度の廃止、品川と長崎での砲台築造(海防力の強化)、長崎・海軍伝習所の開設(近代海軍の基礎)、さらに、講武所の開設、大砲射撃場の設置、蕃書調書(ばんしょしらべしょ)創立(洋書の講習)など、200数十年続いた幕府の諸法制、行政制度を大胆に改革しました。
さらに、阿部正弘が国家百年の大計を考え断行したのが、大胆な人材抜擢と全国200数十名の諸大名および幕臣400数十名からの開国に対する意見の徴収です。攘夷派の巨頭、徳川斉昭を海防参与として幕府外交の顧問に仰ぎ、将軍からの叱責を覚悟でこの諮問政策を断行しました。
人材抜擢された者の多くが開国に尽力すると共に、近代化の扉を開けるうえでの功績を残しています。川路聖謨(かわじとしあきら)、松平近直(ちかなお)、江川英龍(ひでたつ)、勝海舟、岩瀬忠震(ただなり)、永井尚志(なおゆき)などがその代表的人物です。
この人材登用や開国の意見徴収こそ、幕府の力を弱めることになったということもできます。外国との交渉に当たった幕臣の多くが本来の身分を越えて高い地位に就き、大藩の外様大名が幕府の諮問を受けるようになるなど、従来の政権運営では考えられないような大きな変革であり秩序の崩壊だったからです。正弘は幕府の政権運営責任者でありながら、幕府の保身に走ることなく、あくまでも国家百年の大計を考え行動したといえるでしょう。
正弘が老中首座の地位を堀田正睦に譲った翌年の1856年(安政3)、「外国通航貿易を開き、富強の基本となすべし」という書簡を幕閣の有力者に送っています。この時期すでに、後に明治新政府の国家目標となった「富国強兵による近代国家建設」を正弘が提唱していたのです。阿部正弘が「開国の父」であると同時に「日本近代化の父」と呼ばれるゆえんがここにあります。
わずか25歳にして一国の宰相の位に就き、激動の時代を駆け抜けた正弘は、生命を完全燃焼させるほど、みずからの信念に基づき国家の運営に当たりました。堀田正睦に後を託して一年半後の1857年(安政4)6月17日、正弘は39歳の若さでその生涯を閉じました。まさに死力を尽くして国家を主導したといえるでしょう。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)