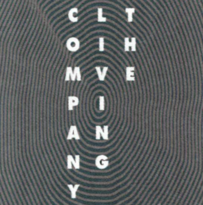関西、東北、沖縄――各地の自由民権の父たち
板垣や片岡の創設した立志社が先駆けとなって自由民権運動は全国的な広がりを見せます。その一角で、関西自由党の重鎮として活躍し、「関西の自由民権の父」と称されるのが、丹波篠山(たんばささやま)藩出身の法貴発(ほうき・はつ)(1846~90)です。明治新政府で大蔵省や福岡県庁に出仕した後、郷里篠山に戻り、『国安論』など多くの著書を残した法貴は、関西の民権運動の先駆者として知られています。
東北地方でも、立志社設立の翌年、1875年(明治8)に自由民権運動の拠点が築かれます。その中心的な役割を果たし、「東北民権運動の父」というべき存在が河野広中(こうの・ひろなか・1849~1923)です。
 河野広中(1849~1923)
河野広中(1849~1923)
河野は二三歳の時から郷里三春町(現福島県田村郡三春町)近くの常葉(ときわ・現福島県田村市)戸長や石川(現福島県石川郡石川町)区長を務め、自由民権運動に共鳴して石陽社を結成。立志社の片岡と共に国会開設請願書を太政官・元老院に提出します。
残念ながら、これは却下されますが、その後も福島自由党を設立するなど民権運動を繰り広げます。1881(明治14)には福島事件に連座して6年余を獄中で過ごしますが、大日本帝国憲法発布の大赦で出獄後、1890(明治23)の第一回総選挙で衆議院議員に当選し、以後、連続一四回の当選を果たしました。
衆議院議長や第二次大隈重信内閣の農商務大臣を歴任。晩年も普選運動の先頭に立ち、立憲政治の実現を目指しました。自由民権運動のリーダーとしての活躍により、「西の板垣退助、東の河野広中」といわれた河野は、いまなお福島県、東北地方の誇りとして語り継がれています。
東北から遠く離れた南国にも、他府県の人たちと同じ権利を勝ち取るため、民権運動を主導する社会活動家が現れました。沖縄の謝花昇(じゃはな・のぼる・1865~1908)です。
沖縄師範学校で留学生に選ばれ学習院で学んだ謝花は、帝国大学農科大学(現東京大学農学部)に進み、近代農業を学びます。在学中に中江兆民(ちょうみん)と交遊し、その思想的影響を受けました。卒業時、恩師から東京に残り学問を究めることを勧められますが、沖縄県民のために働くことを決意して帰郷。沖縄初の学士として、沖縄県庁に出仕します。
ところが、当時の県庁は他府県出身者が多く、故郷沖縄に対する思いが強い謝花は、ことごとく彼らと衝突します。結局、他県出身の県知事と対立して県庁を退職します。そして、「沖縄倶楽部」を結成し、沖縄県民の自治権と参政権の獲得を訴えました。ここに、沖縄における自由民権運動、参政権運動が始まるのです。
しかし、反対勢力からの弾圧が激しく、一連の運動は潰されてしまいます。全財産を投じた謝花は、仕事を求め他県に向かう途中、志半ばにして倒れ、1908年(明治41)、44歳で病死しました。
沖縄県民が選挙権を獲得し、国会へ代表を送るのは、謝花没後四年の1912年(大正元)、日本本土から遅れること32年のことでした。沖縄の人々の権利を獲得するために戦った謝花の運動は、存命中は実を結びませんでしたが、彼の勇猛心と行動力は、いまも沖縄の人々の心に刻まれ、謝花は「沖縄民権運動の父」として語り継がれています。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)