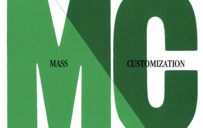分県の父
1871年(明治4)、廃藩置県によって261藩が消滅し、旧幕府直轄地と合わせて三府三〇二県が置かれ、明治中央集権国家が誕生します。真の近代国家は、ここから始まったと言っても過言ではありません。
以後、府県の統廃合が進み、1876年(明治9)には三府三五県まで統合されます。しかし、地域によっては、面積が大きすぎるために、地域間の対立が起きたり事務手続きが非効率であったりと問題が噴出したため、逆に県の分割が進められ、1889年(明治22)には一道三府四三県に落ち着きます。
地域間の対立とは、要するに、予算の取り合いです。廃藩置県によって急速に近代化が進むなか、予算配分いかんによっては死活問題となる地域もありました。
こうした状況の地方自治草創期に、全国各地で議会運営や地域振興に尽力し、地域を代表して分県(県の分割)を成し遂げた「父」たちを紹介しましょう。
当初、新川(にいかわ)県と呼ばれた越中(富山)地域は、廃藩置県後の府県統廃合により石川県に合併されました。ここで問題になるのが、公共事業の予算分配を巡る石川と富山の利害の対立です。石川は道路の改修、富山は治水というように、それぞれの重点政策が異なることが、合併以来の懸案でした。
富山は、3000メートル級の立山連峰からおびただしい量の水が野を駆け抜けるため、河川の氾濫による水害対策が宿命づけられていました。そこで、水害に苦しめられてきた人々のため、現在の富山県下新川郡入善町(にゅうぜんまち)出身で当時石川県会議員だった米澤紋三郎(よねざわ・もんざぶろう・1857~1929)を中心に、富山は石川県からの分県を国に嘆願します。
「分県之建白」には、「富山は地理的、歴史的、風俗からも完全に一つの区域で、加賀や能登中心に動く『大石川県』では、富山の利益になる事案を進めにくい」と、富山を(石川から分離した)一県にすべき理由が端的にまとめられていました。
翌1883年(明治16)、明治政府は富山の分離独立を認め、石川県から分県して富山県が誕生しました。米澤が「富山分県の父」と呼ばれるゆえんです。
富山県と同時期に、宮崎、奈良、香川の三県も分県を認められています。
「鹿児島県」に合併されていた宮崎県の分県に尽力したのは、飫肥(おび)藩出身の鹿児島県会議員、川越進(かわごえ・すすむ・1848~1914)です。川越は、分県後も宮崎県会議長や衆議院議員を務め、宮崎県発展の基礎をつくり、「宮崎の父」と呼ばれます。国政や県政の推進のため私財を投げ打ち、政界引退の時には財産のほとんどを失っていたといわれています。
現在の奈良県は、1876年(明治9)に「堺県」に編入され、1881年(明治14)には堺県が「大阪府」に編入されました。奈良県の分県運動は、現在の生駒(いこま)郡安堵(あんど)町出身で当時大阪府会議員だった今村勤三(きんぞう・1851~1924)を中心に進められ、1887年(明治20)、大阪府からの独立が認められました。
今村も、分県運動に私財を投じ、分県後の初代奈良県会議長に就任し、「奈良県置県の父」と呼ばれます。後年、立憲改進党の衆議院議員として活躍するほか、奈良鉄道会社や郡山(こおり やま)紡績会社の社長として、故郷奈良の実業界を牽引しました。
現在の香川県も、1888年(明治21)に愛媛県からの分県が認められました。愛媛県議会議長としてこれに奔走したのが、高松藩出身の中野武営(ぶえい・1848~1918)です。
「香川分県の父」と呼ばれる中野は、後に衆議院議員、東京市会議員と議長を務めた政治家ですが、実業家としても成功しています。渋沢栄一の盟友としても知られ、渋沢の後を受けて第二代東京商業会議所会頭に就任しました。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)